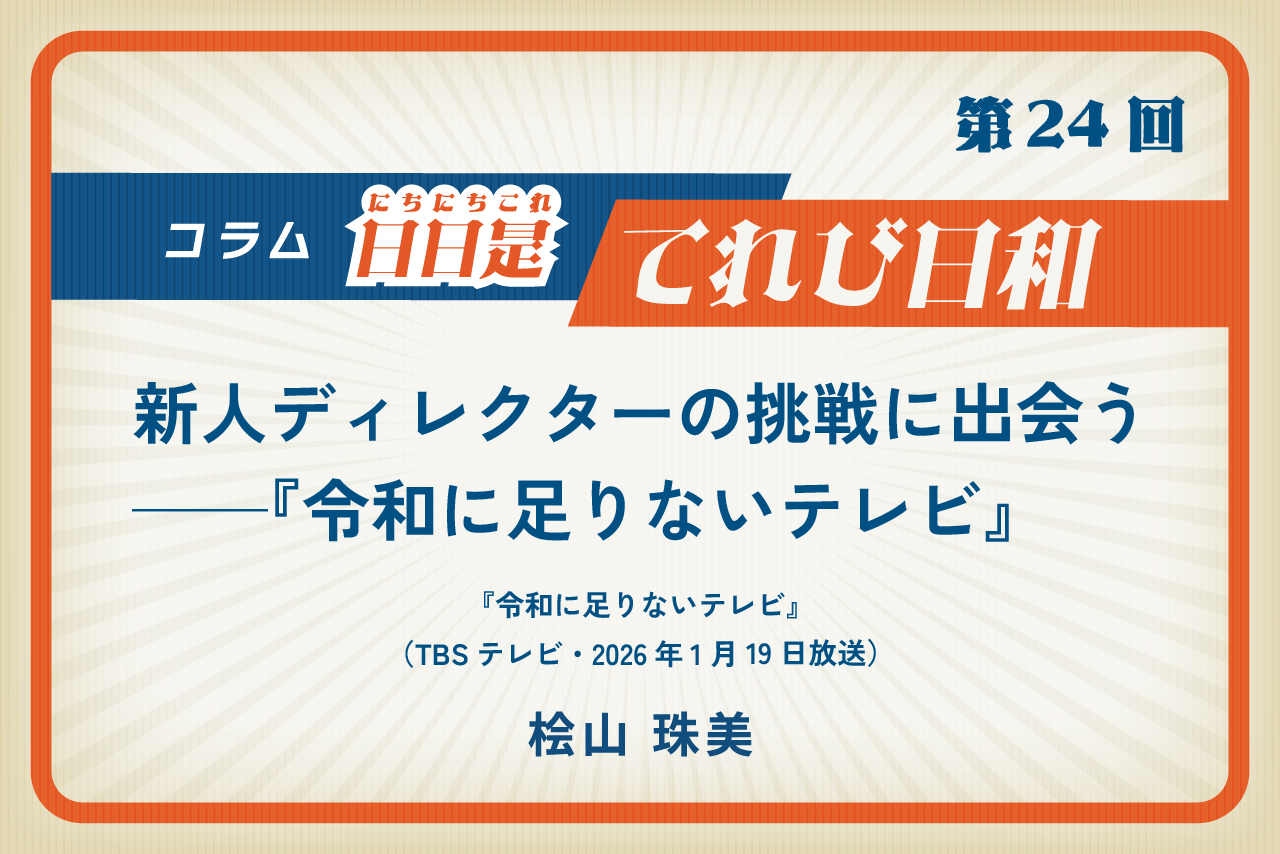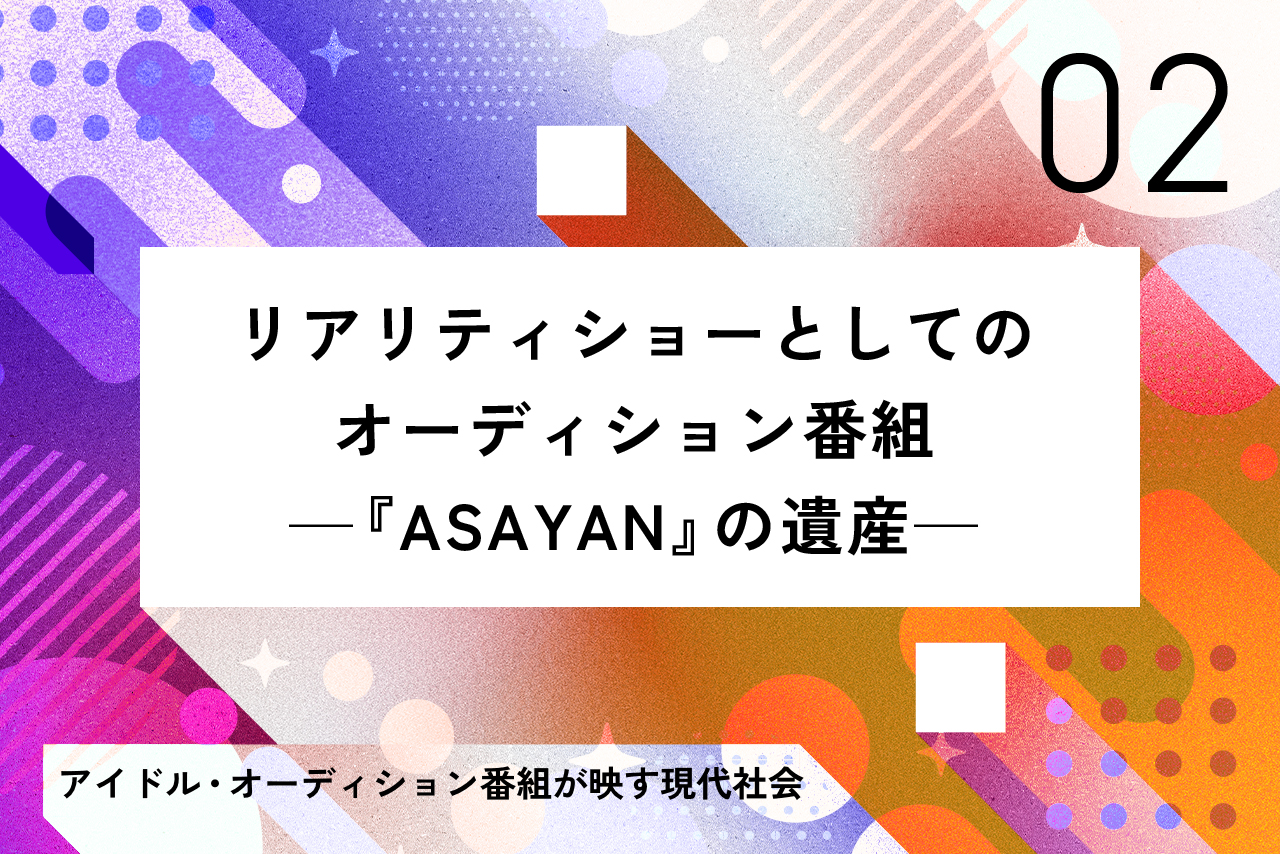助成
「アナウンサーが現場で学ぶ、防災報道のリアル」【伊藤隆佑 TBSアナウンサー】
2024年度助成 イベント事業(後期)

NHK・民放6局のアナウンサーが集い、「命を守る放送」を考える「防災アナウンサー会議」。第27回となる今回は、南海トラフ地震をテーマに和歌山県と高知県を訪ね、防災の取り組みや課題を共有しました。本稿は、今回の勉強会の幹事社であり、その現地取材の成果を報告会で発表したTBSアナウンサーの伊藤隆佑さんによる寄稿です。
災害報道に潜む“アナウンサーあるある”
どんな職業にも「あるある」は存在する。それは全国放送を担うテレビ局のアナウンサーも例外ではない。アナウンサー同士で話していると「だよね〜」という場面が、スポーツ中継でもバラエティ現場でもなんと多いことか。また、それが日常の些細な出来事だと「あ~、その気持ち分かります」と初対面の相手でも妙な親近感が湧いたりする。
だが、災害報道となると、その「あるある」は「放送における共通の課題」であることが多い。そして、それを解決することは「命を守る」ことに繋がるのではないか、という思いがある。
たとえば、7月30日に発生したカムチャツカ地震による「遠地津波」。各局のアナウンサーは、気象庁の情報が注意報から警報へと引き上げられる中、各地から届く津波観測情報に戦々恐々としながら終わりの見えない報道特番に臨んでいた。迅速な避難を呼びかけながらも、屋外の避難場所で強烈な日差しにさらされる人々の映像を見て、「津波」と「熱中症」のリスクの狭間に揺れた。その場では答えが出せなかったという声も多かった。
NHK民放6局による防災アナウンサー会議の原点へ
どうすればよかったのかーー。その問いが「NHK民放6局防災アナウンサー会議」で議題に上がった。
この会議は、東日本大震災を契機に放送局の垣根を越えて「減災・防災を推進する取り組み」として有志の勉強会でスタートし、2か月に1回のペースで内閣府や気象庁、そのほか防災研究機関などから講師を招いて開催されてきた。
第27回を迎える今回は、放送文化基金の助成を受けたこともあり、原点に立ち返ってアナウンサーの視点から課題を設定することにした。
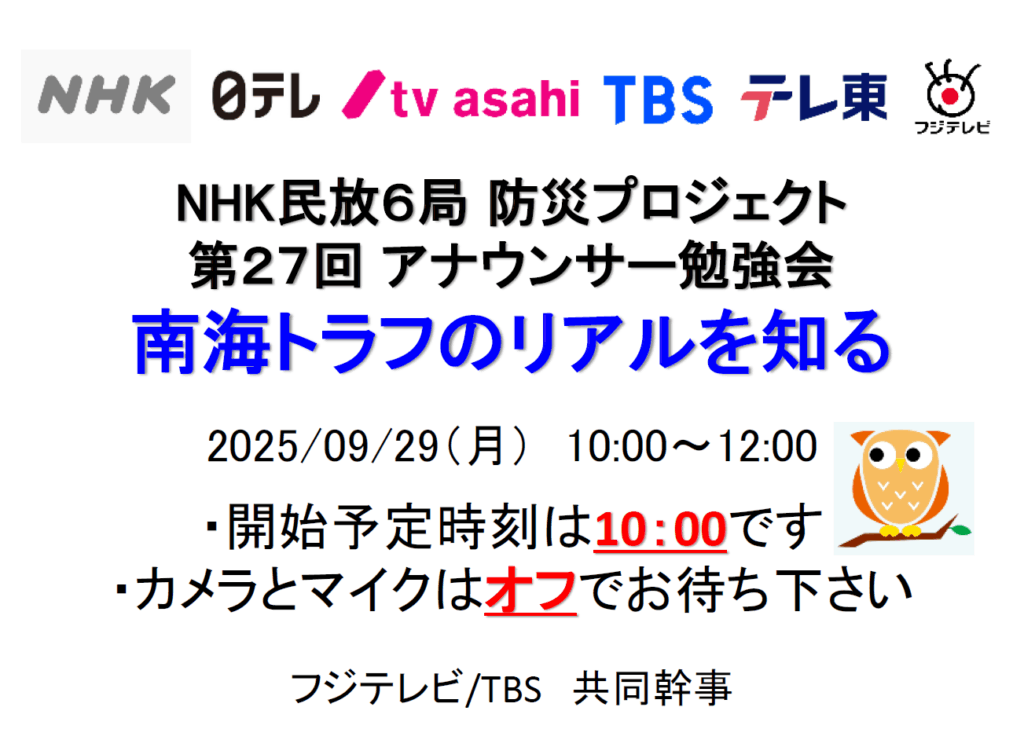
南海トラフのリアルを知る~和歌山・高知での現地取材
主題となったのは「南海トラフのリアルを知る」だ。背景には今年3月に新しい被害想定、8月に政府の新しいガイドラインが発表されたことがある。住民や自治体の取り組みを知ることで「実情に寄り添ったアナウンスメントを追究したい」という6局の目的も一致した。
取材先として、民放の現地局が少ない和歌山県にNTV河出奈都美アナウンサーとTBS伊藤隆佑(筆者)が、日本で最も高い津波が想定される高知県にNTV瀧口麻衣アナウンサーとCX高崎春アナウンサーが訪れることになった。

瀧口さんと高崎さんは入社2年目同士で、この視察をきっかけに意気投合したフレッシュなふたり。一方、河出さんと私は13歳の差があり、たどってきたキャリアも全く違う。どちらの取材も「防災報道」に一丸となって取り組もうという6局の総意があって初めて実現したものだった。

現場を歩き、住民と向き合うことで見えたもの
9月29日、現地視察の報告会がTBSで開かれた。対面でキー局18人、リモートを含めると全国から130人以上のアナウンサーが参加した。
和歌山では「遠地地震」による津波で住民が避難場所に向かったが、揺れによって開錠される避難施設の「キーボックス」が開かず立ち往生したという事例や、津波到達まで時間的猶予があった中で避難したが、結果的に長時間、酷暑の屋外に留め置かれた住民もいたことが確認された。
他方、津波防災の町として知られる広川町では屋内の避難施設に整然と住民が集まり、大きな混乱は起きなかった。
また、和歌山では能登のように半島という地形的特徴を持つため、災害関連死への対策に力を入れていること、自助共助の意識を高める独自の避難所運営ゲームで啓発を行っていることに感銘を受けた。

34メートル級の津波が想定される黒潮町のリアル
高知では、黒潮町に6基の「津波避難タワー」建設、昭和南海地震で被災した「91歳の証言」、漁師による船舶の「沖出し問題」など、34メートル級の津波が襲来するとされる黒潮町のリアルを瀧口・高崎コンビが詳細にリポートした。
報告の中では、災害時に東京のアナウンサーの声が届いているのかという葛藤、アナウンサーが平時からできるアクションの模索についても語られた。若い2人の率直で、真摯な言葉に「その気持ち、分かる」と頷いたのは、私だけではなかったはずだ。

新しい防災報道のかたちを探して
さらに、勉強会は東京のアナウンサーによる報告に終始せず、TBS系列・SBS静岡放送の野路毅彦アナウンサーとCX系列・高知さんさんテレビの川辺世里奈アナウンサーから、現地局として地域に根差した放送についての共有もあった。
当初は在京の有志による意見交換会として始まったこの勉強会も、いまでは全国へと輪を広げ、これまでの2年間で延べ約2000人のアナウンサーが参加している。

ともに学び、ともに守るために
今回、和歌山市、広川町、美浜町、高知黒潮町と4つの自治体の視察を通して、所属の異なるアナウンサーがともに街を歩き、住民と言葉を交わした。しかし、「あの時」の答え、「その時」に向けての正解が見つかったわけではない。むしろ新たな問いが生まれた気もする。
まさに、スタジオでニュースを読み、想像をめぐらせるだけでは知り得ない「リアル」がそこにはあった。
だからこそ、伝え手であるアナウンサーが災害に直面する現場ごとの特徴的な施策と当事者が置かれている背景を知り、その知見を共有することで、新しい防災報道のあり方が見えてくるのではないだろうか。
少なくとも、最初の妙な親近感は、防災に取り組む過程で、確かな連帯感へと変化してきたはずだ。
しかし、我々の目標は「ともに学ぶ」ことではない。ひとりでも多くの命を「ともに守る」こと。その使命をアナウンサーは担っているのだ。決して大げさではなく、このプロジェクトに参加する全員がそう信じている。
著者・プロフィール

伊藤隆佑(TBSアナウンサー・防災士・保育士)
2006年TBS入社。2011年の東日本大震災の際、福島第一原発のリポートやJNN三陸臨時支局での現地業務などを経験し、2017年に防災士、2025年に保育士の資格を取得。災害報道に携わる経験や資格を活かし、未就学児から社会人まで防災教育やセミナーの講師を務める。学習院大学文学部哲学科~早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了。担当番組は報道特集、ひるおび等。
2024年度助成 イベント事業(後期)
「災害から命を守る放送とは?~NHK民放6局防災勉強会~」
NHK民放6局防災プロジェクト
代表 浜野 高宏(株式会社 グローカル ヴァンガード東京)
関連記事を見る
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/xb894950/hbf.or.jp/public_html/wp-content/themes/theme/single-magazine.php on line 86
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る