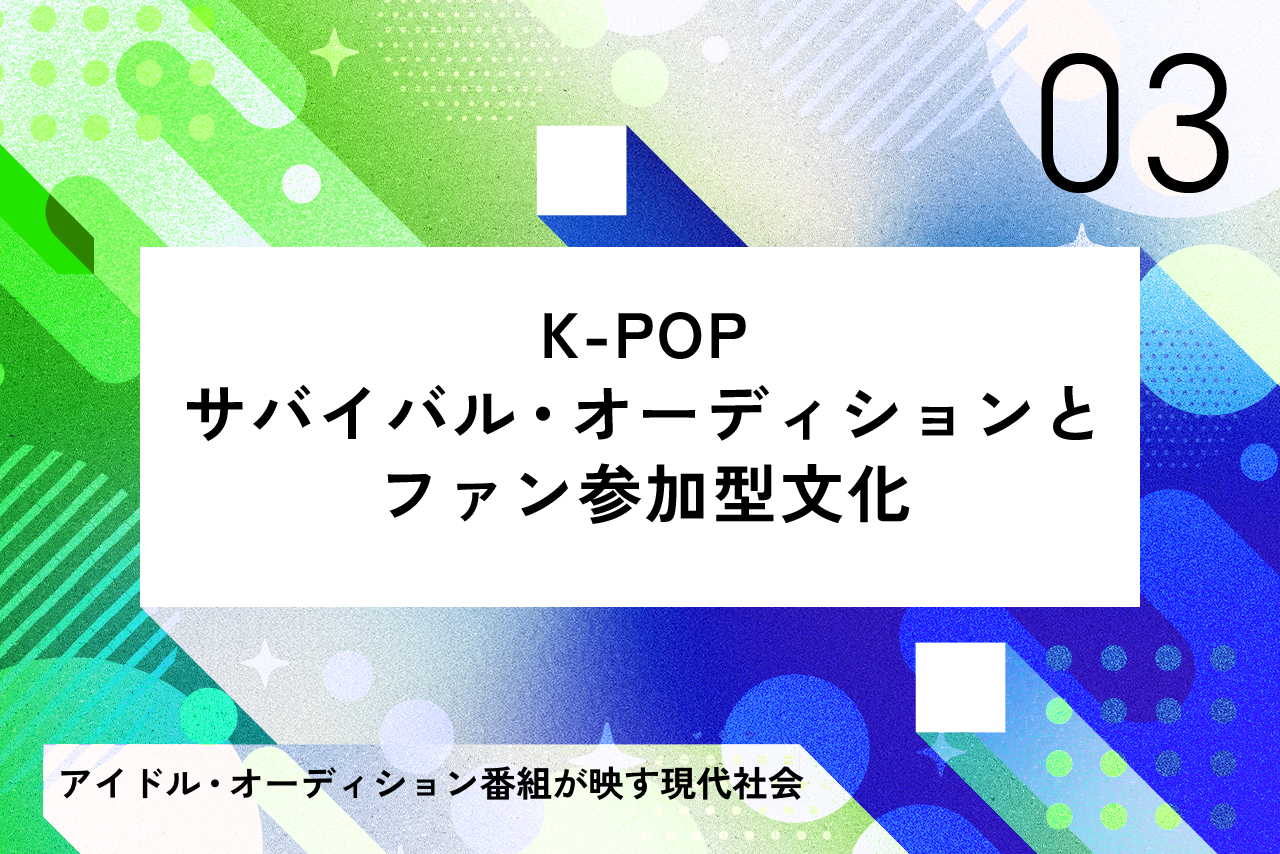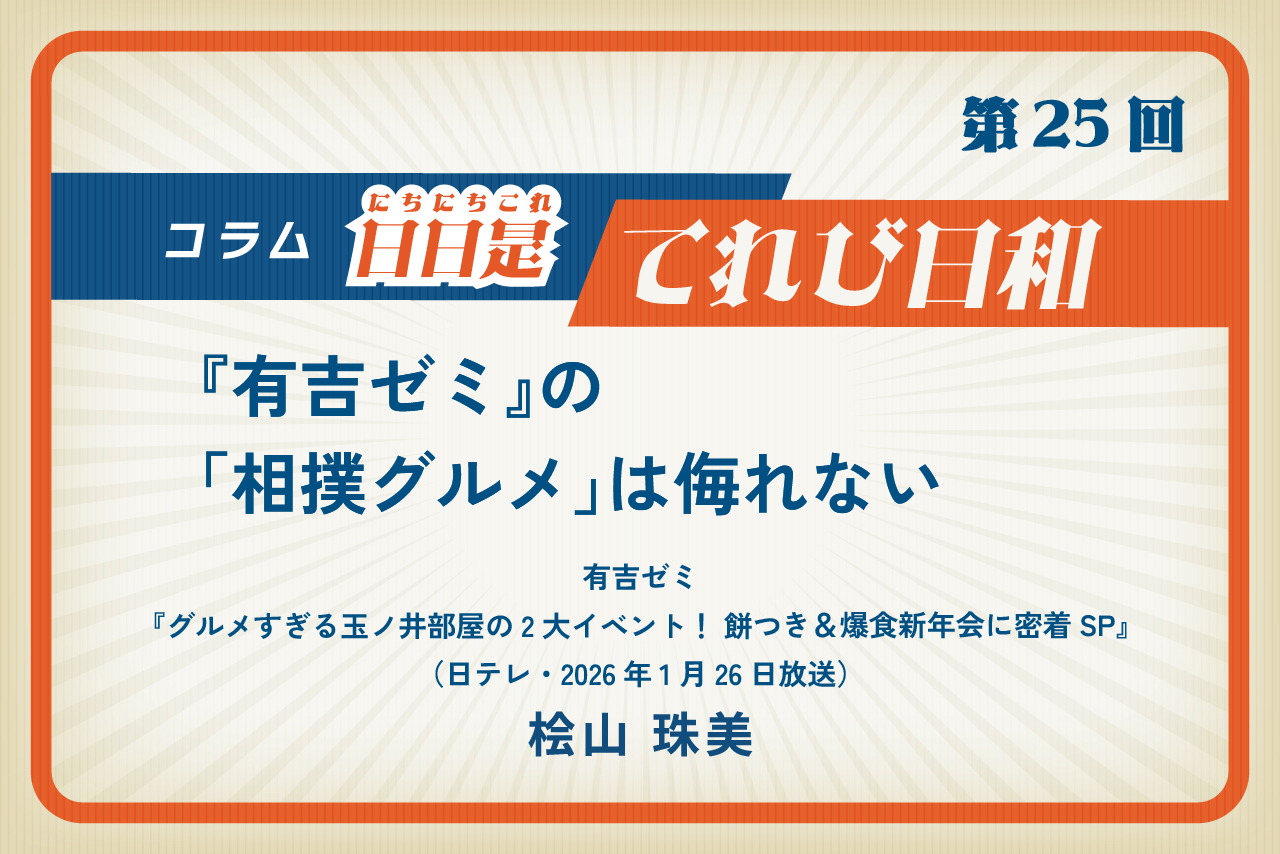HBF CROSS
坂元裕二が生み出した『Woman』アラビア語版の成功の秘密【長谷川朋子】
連載コラム▶▶▶いま、気になるコンテンツ “その先”を読む #4

シングルマザーを主人公にした坂元裕二脚本の名作ドラマ『Woman』のアラビア語版が、8月17日から放送配信スタートし、早くも反響を呼んでいます。過酷な状況ながら力強く生きる女性キャラクターと、その複雑な家族事情を細やかに描いたストーリーは、異なる文化を持つ地域でも深い共鳴を得て、国際的な成功事例と言えそうです。
ドラマ『Woman』が日本で初放送されたのは2013年7月クールです。日本テレビ系の水曜ドラマ枠で坂元裕二脚本、水田伸生監督タッグによる『Mother』(2010)に続く第2弾の社会派ドラマとして当時から話題を呼んでいました。
作品内容を振り返ると、満島ひかりが演じる2児のシングルマザーである小春を主人公に、貧しいながら愛する我が子のため命をかけて生きる女性の生き様が見どころにあるドラマです。加えて、背景にある貧困問題にも目を向けています。社会から取り残されたひとり親の苦労が、セリフや演技を通じてリアルに表現されているのが印象的です。
たとえば、第1話で小春が言い放つこのセリフは、彼女の苦悩を端的に表現しています。
「2人だったら簡単にできることが1人だと急に難しくなる。ただ、ごはん作ったり、ただ電車で3つ先の駅に行くのが1人だと難しくなります。『母の愛があれば大丈夫』って言われてます。そうか…そうかな…。」
小春の心の葛藤が伝わるこの場面は、小春を幼い頃に捨てた母(田中裕子)の会話の中で生まれています。小春は「母親」としての顔だけではなく、過去のトラウマと闘う複雑なキャラクターでもあるのです。それが作品の独自性を強めています。
小春の母親の視点、母親の再婚相手である義理の父(小林薫)、そしてその娘の栞(二階堂ふみ)など複雑に絡み合う周囲のキャラクターの事情や内面的な葛藤も掘り下げ、奥行きのある物語が展開されています。
今から12年前に制作、放送されたドラマですが、母親の愛や苦悩を描くテーマは時代も国境も越え、貧困というあらゆる国が抱える問題にも向き合い、キャラクターたちの個性を引き出したセリフに溢れています。つまり、国際的に成功するドラマの条件の核となる普遍性と独自性を兼ね備えている作品だと言えます。今回、アラビア語にリメイクされたのは必然の流れなのかもしれません。
ドラマ『Mother』トルコ版のヒットがきっかけ

そもそもドラマ『Woman』の国際展開は、『Mother』がドラマ大国のトルコでヒットしたことがきっかけです。『Mother』のトルコ版は『Anne(アンネ)』(「母」という意味)というタイトルでリメイクされ、オリジナル版で魅せた松雪泰子と芦田愛菜、田中裕子の渾身の演技と遜色ないトルコの女優たちによって、親から虐待を受けていた少女と絆を深める物語が新たに描かれています。
2016年から17年にかけて現地で放送されると、熱狂的に支持され、この勢いに乗って『Woman』もトルコでリメイクされます。『Kadin(カドゥン)』(「女」という意味)というタイトルで17~18年に放送され、こちらも絶大なる支持を得たというわけです。
さらに『Kadin』にはオリジナルストーリーが加わり、3シーズンも続く圧倒的なヒットに繋がりました。制作された計81話が60ヵ国以上に輸出される実績も作っています。
これらトルコ版の成果だけでも日本発ドラマ史上、最も成功した国際展開と言えますが、ここにきて中東と北アフリカをカバーするMENA地域向けのアラビア語版まで作られたことは影響力を拡大するものとして注目すべきものです。
日本テレビはアラビア語版の展開にあたり、トルコのヒットメーカーである制作会社のMedyapim(メッドヤプム)と、サウジアラビアに本社を置くMENA地域最大のメディア・エンターテインメントネットワークであるMBCグループとの間でフォーマット合意を結び、国際コンテンツパートナーシップを構築しています。
日本テレビの海外戦略センターの話によると、MENA地域で人気コンテンツのフォーマットを現地向けにリメイクする流れが強まっていることが背景にあるようです。MBCはリメイク権の購入に積極投資し、既に『Mother』のアラビア語版『Oumi』も作られています。またトルコの名作ドラマの1つと言われる2010年放送の『Time Goes By』のアラビア語版も制作することを発表しています。
興味深いのが『Mother』『Woman』との共通点です。『Time Goes By』は力強い女性キャラクターと複雑な家族関係の描き方が評価された作品で、家族の絆というタイムレスなテーマを扱ってもいます。これらの要素はまさにトルコやMENA地域で求められるドラマの重要なポイントなのかもしれません。
トルコの制作陣が撮影、全90話を計画
トルコのドラマがMENA地域で展開される動きを牽引するのがトルコのMedyapimであることも見逃せない点です。というのも、Medyapimはこれまで世界ヒットドラマ『デスパレートな妻たち』や『Doctor Foster』などをリメイクし、トルコ版の『Mother』と『Woman』を手がけたのも同社なのです。
以前、トルコ版の制作現場に足を運んだ水田監督にどのように作られているのか聞いたことがあり、その際、水田監督は「自分と同じようにドキュメンタリータッチに撮っていた」と答えていたのが印象的でした。
「役者の方にどんな風に演じてもらいたいか、それなりにイメージを持ってはいるものの、言ってみれば、ドキュメンタリータッチに撮ります。カットに芝居を当てはめず、『カメラに向かってどうぞご自由に』とやってもらうと、リアリティが生まれてくるからです。トルコも同じような撮り方でした。日本のオリジナル版を尊重してもらったのか、使っていたカメラもレンズも同じだったこともあり、演出に違いはありますが、映像のタッチが(日本のオリジナル版)と近いものがあります」(水田監督)
この高い制作力をサウジアラビア側も求め、『Women』のアラビア語版を、トルコの制作陣が現地で撮影しているそうです。2025年8月17日から放送・配信開始され、タイトルは主人公が持つ強さや優しさを象徴する『Salma』というもの。90話の制作を予定し、MBCでの放送に加えて、傘下の地域最大級のストリーミングプラットフォームShahidを通じて約20ヵ国で配信もされています。
視聴率や再生回数は一般に公式発表されてはいませんが、民間の調査サイトによると、アラビア語版『Woman』は再生回数1位の好スタートを切っています。同じくアラビア語版の『Mother』もトップ5に入り、MENA地域での成功が手堅いことを示しています。
2019年のことですが、フランス・カンヌの世界最大級の見本市MIPに来場した坂元氏にも『Mother』『Woman』の海外ヒットを受けて、どう感じているのか尋ねたことがありました。
「『Mother』『Woman』はこれまで書いているものの中でもストーリー性が強いと思います。でも、脚本を書いているとき、実はとても怖かったんです。田中裕子さん、松雪泰子さん、満島ひかりさんら、皆さんのお芝居にどのように応えることができるのかと。だから、僕の実力以上のものを引き出してくれたというか、全力でぶつかっても敵わないような俳優の方々をキャスティングしてくださったことが今につながっているのだと思います」(坂元氏)
この坂元氏の言葉を改めて受け止めると、脚本力と演出力、俳優たちの実力がそれぞれアラビア語版という新たな展開に繋がり、世界ヒットストーリーを広げているのだと思わずにはいられません。
▷▷▷この連載をもっと読む
【#1】SFドラマ『ブラック・ミラー』がNetflixのカルト的人気番組になった理由
【#2】是枝監督が語る「今、残したいテレビドラマ」、短編映画『ラストシーン』にあるヒント
【#3】アニメ『映画 えんとつ町のプペル』復活のカギは「カナリア諸島」との協業にあり?
連載コラム▶▶▶いま、気になるコンテンツ “その先”を読む
多様化する映像コンテンツの世界で、いま本当に注目すべき作品とは?本連載コラムでは、国内外の番組制作やコンテンツの動向に精通するジャーナリスト・長谷川朋子さんが、テレビ・配信を問わず心を動かす作品を取り上げ、その背景にある社会の変化や制作の現場から見えるトレンドを読み解いていきます。単なる作品紹介にとどまらない、深い洞察に満ちたコンテンツガイドです。
著者・プロフィール

長谷川朋子 (はせがわともこ)
ジャーナリスト/コラムニスト。国内外のドラマ、バラエティー、ドキュメンタリー番組制作事情をテーマに独自の視点で解説した執筆記事多数。「朝日新聞」「東洋経済オンライン」などで連載中。フランス・カンヌで開催される世界最大規模の映像コンテンツ見本市MIP現地取材を約15年にわたって重ね、日本人ジャーナリストとしてはコンテンツ・ビジネス分野のオーソリティとして活動中。著書に「Netflix戦略と流儀」(中公新書ラクレ)など。
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る