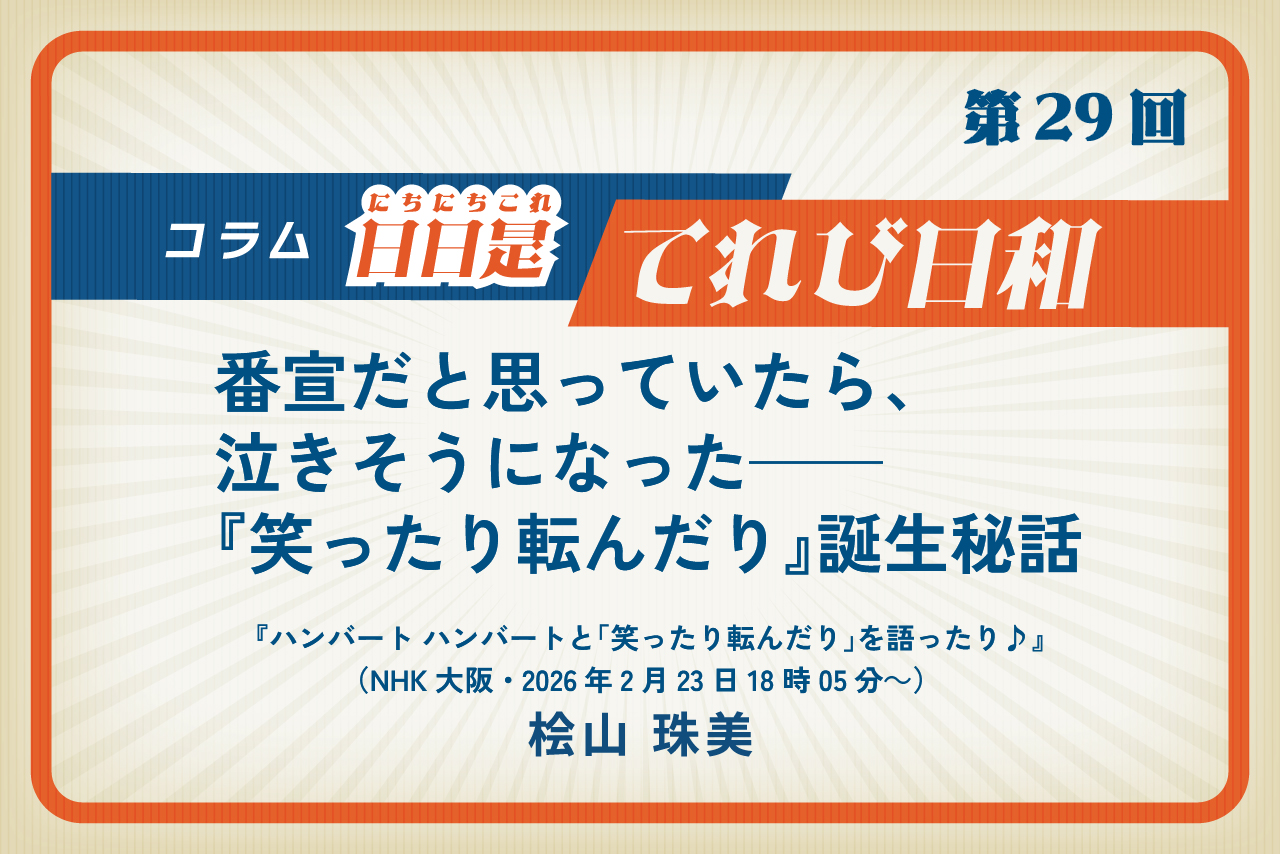HBF CROSS
見えなくなった真実──SNS時代における報道と政治のリアル
「いまメディアを考える」連続シンポジウム報告/全3回(放送文化基金協賛)【第2回】
長井展光(元毎日放送、同志社女子大講師)
連続シンポジウム第2回目は、2025年6月8日、日本メディア学会春季大会(立命館大学)において、「SNS時代の選挙とテレビ報道」をテーマに、放送研究部会のワークショップとして開催され、研究者ら55人が参加した。問題提起者/曺琴袖氏(TBSテレビ「報道特集」編集長・当時)、討論者/渡邊久哲氏が登壇した。

テレビ vs SNS:情報戦を制するのは誰か?──選挙報道の現在地
ゲストに招かれた曺琴袖氏(TBSテレビ「報道特集」編集長・当時)は以下のように問題点を指摘した。
既存の報道がSNS中心の世代の人達には伝わっていないのではないかという危機感がある。テレビの選挙報道に問題はないのか、都知事選挙、衆議院選挙、兵庫県知事選挙と続いたが、SNSを駆使し、“バズらせた”陣営が成功し、マスメディアの予測が覆された。テレビの報道スタイルは長く変わってこなかった。これに対して如何なものか、という意見がある。
過去の衆議院選挙を振り返ってみると、TBSは小泉首相時代に政権批判を選挙運動期間中も堂々とやっていた。選挙期間中の報道時間も、その当時9時間もあったものが、今は4時間しかない。どの辺りで変わったか?2014年の第2次安倍政権時代に自民党萩生田副幹事長(当時)が衆院選報道の「公正中立、公平の確保」を求める文書を送った辺りから非常にナイーブになった。放送側に委縮が生じ、報道を控えるようになったのではないか。
兵庫県知事選挙を巡る「報道特集」での報道は、斉藤知事のパワハラ、公益通報者保護・文書問題について追及し、内部告発者捜しがどう行われたのかなど検証してきた。不信任された斉藤氏が再選されると見込んでいた既存メディアはなかった。選挙運動期間中の報道は控え気味になった。「報道特集」では11月30日と12月28日に特集を組んだ。“NHK党”(頻繁に名称が変わるのでこの党名で)の立花氏が選挙に加わり、斉藤候補側との「2馬力選挙」を繰り広げ、ライバル候補をマイナス材料で攻撃し、パワハラなどを告発した元県民局長について下品なイメージを流布したこと(9割位は事実ではないと考えられる)を伝えた。「報道特集」には立花氏支持層から凄まじいスポンサー攻撃もあった。スポンサーリストが流布され、電話攻撃が行われた。また、斉藤候補サイドの動画拡散についてはネット上の仕事紹介サイトを通して「切り抜き動画」作成作業が有償で募集されていたこと、内容の真偽よりセンセーショナルで再生数が増える動画が求められること、作成者は真偽の確かさや自分の信条よりもお金になるから作成したことなどを報道した。
「放送時間の長さが同じだからと言って公平とは言えないのでは?」「自分たちが取材して正しいと思うことを伝える」「弱者に寄り添うのが報道」。SNSをチェックしない人は現状、ネット空間で何が起きているか知らないが、チェックし始めてみると「違う色に見える世界が広がっている」。みなさんに考えていただきたい、と曺氏は結んだ。
信じるのは“誰が言ったか”より“どう見えたか”——Z世代の直感的選挙観とメディア不信
かわって登壇した渡邊久哲上智大学教授は、Z世代のアンケートから次世代の選挙と報道について検証していった。昨年3月に全国の有権者を対象にしたネット調査、衆議院選挙後に上智の学生対象に行った調査・インタビュー、全国の有権者を対象にした郵送調査の3つだ。
列挙すると若者はタイムラインを気にしている。「テレビの前には座っていられない」世代。SNS発信することで自分が「ジャーナリスト気分の高揚感」がある。マスメディアより政治家本人の言葉を信じる傾向。「情報ソースに近いところにいる」という感覚を持つ。「政治家は(真実を)隠す、マスコミはそれを暴く」という概念はもう通じない。
SNSのタイムライン上の情報は若い有権者にHeuristic判断(必ずしも正しくないが、経験や先入観・イメージによって直感的、無意識になされるとりあえずの判断)を強いる。Z世代はイメージを信じ、無批判で、目の前にあるもの、タイムラインのショート動画を信じやすい。本来の選挙、民主主義はシステマティックなもので、「注意深く、網羅的に、論理的に、批判的に」判断されるべきものだ。ショート動画には危うさがある。見たものがすべてイメージで理解。自動的に結論に飛びつく。
昔はテレビでも議論したが、Z世代は「おすすめ」「結論」「正解はナニ?」を求めている。テレビの選挙報道に求められるもの【正確さ70% / 中立性公平性45% / 速さ16% (全国郵送調査】。「わかりやすく説明されると正しいような気がする」(きれいな字、濃い文字は信じやすくなる)「どこに頼っていいのかわからない」「偏向報道、何か隠しているんじゃないか」など、すべてイメージだけから来ている。取材の手の内、報道しなかった理由を見せる透明性が大事ではないか。以前はブランド力、「朝日だから大丈夫、TBSだから大丈夫」だったが、今は個々人がジャーナリスト気取り。Z世代は自分たちにもっと学校で政治について教えてほしかったと回答している。
フロアからの声に見えた“報道と信頼”のいま──質疑応答で浮かび上がった新たな課題
この後、フロアからの発言を含め質疑応答、登壇者の補足発言があった。
まず「取材経過と取材した上で報道しない理由を丁寧に開示した方が良いと思う」との意見が出された。死者のプライバシーなど既存メディアは報道しないできたが、今の世間からは「隠ぺいしている」と糾弾される。取材相手でさえ「インタビューされたことの8割は使っていない、都合のいいところだけしか使っていない」とSNSなどで主張する。嘘を排除し、事実確認をするよりも若い世代は文脈、ストーリーを重視、(既存メディアを)既得権益だと非難する。
またフロアからはSNS上で追いつめられているが、取材者のケアはどうしていたのかという質問が出た。これに対して曺氏は「取材の様子の動画がSNSに上げられるなどこれまでにない経験を試行錯誤しながら乗り越えてきた。ちゃんとSNSをチェックしていこうと思うと疲労、心理的プレッシャーでメンタルがおかしくなってしまった。ナレーターにも攻撃の言葉がきた。殺害予告もきた。会社も『現場判断レベルではない』と対応にスイッチが入った。訴訟に持ち込むための準備もして、投稿を野放しにするのではなく削除申請もしたなどの回答があった。
その他、オールド(既存)メディアは数々の失敗をして、その教訓の下で活動している。SNSなど新しいメディアの現状はひどい状態でもあるがルール構築の途上ではないかなどの意見が出された。
第1回、第2回のテーマについては、まだまだ動いているのが現状で、到底「中くくり」も出来る状態ではないと言える。ただ、現状をより深く分析し、より健全なメディア、情報空間を構築するために様々な検証、意見交換の場が必要なことは間違いない。このような機会にご援助いただいた放送文化基金に深く感謝するとともに、今後も様々な機会を作っていきたいと考えている。
プロフィール

長井展光 ながいのぶみつ
1959年生れ。同志社大学卒。1983年毎日放送入社、
アナウンサー、報道記者・デスク、マニラ支局長、
地デジ化やメディア施策担当などを経て役員室エグゼクティブ。
2024年退職。現在は同志社女子大学、関西大学講師、放送批評懇談会、放送人の会理事など。
6月8日(日) 日本メディア学会放送研究部会企画ワークショップ(立命館大学)
「SNS時代の選挙とテレビ報道」
問題提起者:曺琴袖(元・TBS「報道特集」編集長)
討論者:渡邊久哲(上智大学教授)
司会者:音好宏(上智大学教授)
▶次回は最終回、7月下旬に「変わる政治情報の受容と選挙報道 ~参院選を振り返って」(仮)を開催予定(会場は東京)
討論者など決まり次第お知らせいたします。
▶第1回目「なぜフジテレビはまた過ちを繰り返したのか?」ー崩れるガバナンスと放送の自立性
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る