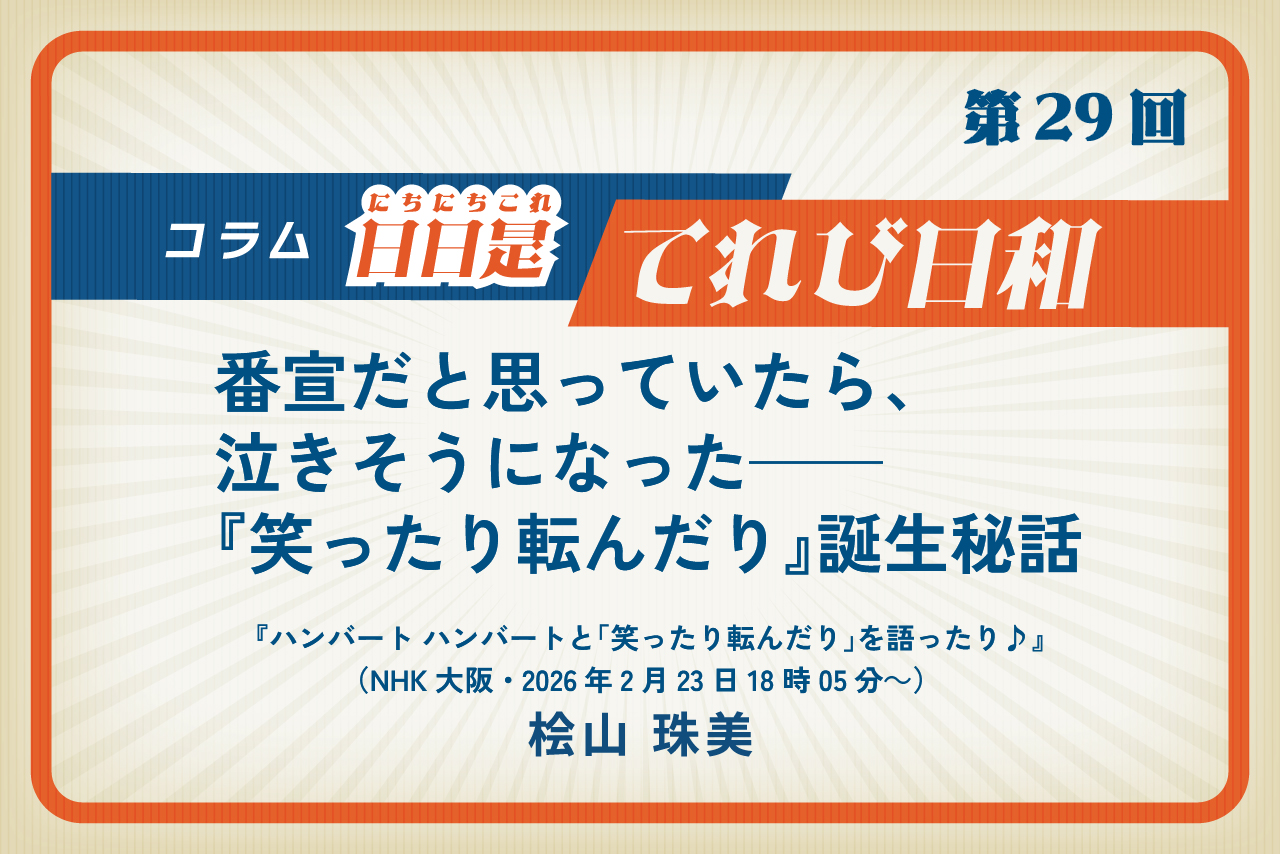HBF CROSS
「なぜフジテレビはまた過ちを繰り返したのか?」ー崩れるガバナンスと放送の自立性
「いまメディアを考える」連続シンポジウム報告/全3回(放送文化基金協賛)【第1回】
長井展光(元毎日放送、同志社女子大学講師)
「これはフジテレビ個社の体質なのか、放送業界全体が時代の変化を読み切れていなかったのか?」「ネット、スマホ中心時代の世の中の民意生成はここまで来たのか、そのバックにうごめいていたものは? メディアはどう役割を果たしていくべきか?」
こうした問題意識を起点に、関西と東京で計3回にわたり開かれるシンポジウムを取材し、その議論のあらましを報告する。今回は第1回として研究会形式でフジテレビ問題を取り上げた大阪での議論を伝える。

「教訓はどこへ消えた?」―フジテレビを襲う終わらないガバナンス危機
「フジテレビでは過去の教訓が血肉化されていないのではないか」6月6日(金)に上智大学音好宏教授が主宰する関西メディアジャーナリズム研究会と日本メディア学会放送研究部会の共催で開かれ、関西、名古屋の放送関係者、研究者など約50人が出席した研究会は音教授のこんな指摘で始まった。
音氏はさらに続ける。人権意識について、民放総体としては2023年に民放連の番組基準が大幅に改定され、ビジネスと人権をどう考えるのかが問われてきた。総務省、民放連からもガバナンスについて指摘され、スポンサー離れが起きた。現在のグローバルスタンダードは「人権を守る」で、それが出来ない企業は「グローバル市場に出てはいけない」。フジも方針を定めていたが、組織としてそれが血肉化されていなかったのではないか。会社の閉鎖的な雰囲気からガバナンスの欠如があり、社会からの批判を予期できていなかったのではないか。報道機関としての自覚のなさ、コンプライアンス部門へ報告せず意思決定から排除し、編成・制作ラインだけで判断したことはガバナンスができていなかったと断じざるを得ない。フジ系列では2007年に関西テレビによる「あるある」問題が発生していたのに、この教訓は活かされていなかったのではないか。
総務省はコンプライアンス、ガバナンスという点から行政指導を行ったがこれは大きな問題だ。この面で行政指導が出たことは痛恨の極みだ。これまで番組内容以外での指導は1993年のテレビ朝日の椿発言事件、96年のTBSのオウム問題、97年の福岡放送のCM間引き問題、2003年の日本テレビの視聴率買収問題がある。放送業界は「自主自律」が基盤で、自浄能力がないといけない。政治からの介入の動きも出ている。「あるある」問題の時は再発防止計画の提出など法制化しようという動きが出たが国会で廃案になった。この時はBPOに放送倫理検証委員会を設置することで自主自律を守った。放送法の枠組みである、放送の目的、自主自律、編集の自由、番組基準の遵守、番組審議機関の設置など、再度、認識しておかねばならない。
放送は誰のものなのか。上場企業は株主のもの、とも言われるが、放送の持つ公共性、公益性を大切にしなければならない。かつてのホリエモンによるフジ買収未遂問題もあり、認定放送持ち株会社には3分の1以上は支配できないという制限が設けられた。新聞の株式保有は日刊新聞法で守られている。放送会社が「市場の中で評価される」で良いのだろうか。フジテレビは再生、改革に向けて8つの具体策を実行すると表明している。自律した放送人を育てる、現場の自主自律の確保、「内部的自由」の確保が重要だ、と音教授は発言を結んだ。
18年前の傷が癒えない―“あるある”の呪縛から抜け出せるか
かわって登壇した元毎日新聞記者の北林靖彦氏は以下のように語った。

混乱とちぐはぐな対応だけが目立った。思い出したのが系列局、関西テレビが「あるある」問題の時、再発防止のために編集した「番組制作ガイドライン」だ。会社の経営体質が問われているフジと番組捏造では次元が違うものの、コンプライアンス責任者による組織全体の意思疎通の円滑化や、「逃げない、隠さない、そしてスピーディーに」を軸にした危機管理広報についての記載は今のフジが問題視された課題だった。18年前の教訓をキー局であり、関西テレビに社長も送り込んだフジは学んでいなかった。 最初の港浩一社長の会見は、目立たないようにと目論んだのかもしれないが、テレビで港社長の静止画が流れるたびに傷口は深くなるばかりだった。フジは「あるある」や「真相報道 バンキシャ!」(日テレ)の岐阜県庁裏金誤報事件という他局の「しくじり」も学んでいるはずにもかかわらず今回のしくじりを犯した。“長期政権による経営”が現場を麻痺させたのかもしれない。
その後、質疑応答に移り、“長期政権”による経営が与えた影響、放送事業者の自主自律という意識を徹底させるためには入社する前からの大学などでのジャーナリズム教育が重要ではないか。タレント対応政策を含め、グローバル市場でも太刀打ちできるようにするためのコンテンツ政策の重要性などが議論された。
プロフィール

長井展光 ながいのぶみつ
1959年生れ。同志社大学卒。1983年毎日放送入社、
アナウンサー、報道記者・デスク、マニラ支局長、
地デジ化やメディア施策担当などを経て役員室エグゼクティブ。
2024年退職。現在は同志社女子大学、関西大学講師、放送批評懇談会、放送人の会理事など。
日本メディア学会放送研究部会連携 「いまメディアを考える」連続シンポジウム(放送文化基金協賛)
【第1回】「大阪から、改めてフジテレビ問題を考える」
日時:6月6日(金)
会場:上智大学大阪サテライトキャンパス
関西メディアジャーナリズム研究会・日本メディア学会放送研究部会の共催
討論者: 音 好宏(上智大学教授)
北林靖彦(ジャーナリスト・元毎日新聞文化部記者)
進行: 長井展光(同志社女子大学講師)
▶次回は、【第2回】見えなくなった真実―SNS時代における報道と政治のリアル
「SNS時代の選挙とテレビ報道」と題し、問題提起者として曺琴袖(元・TBS「報道特集」編集長)を迎えて開催した日本メディア学会放送研究部会企画ワークショップについての報告。
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る