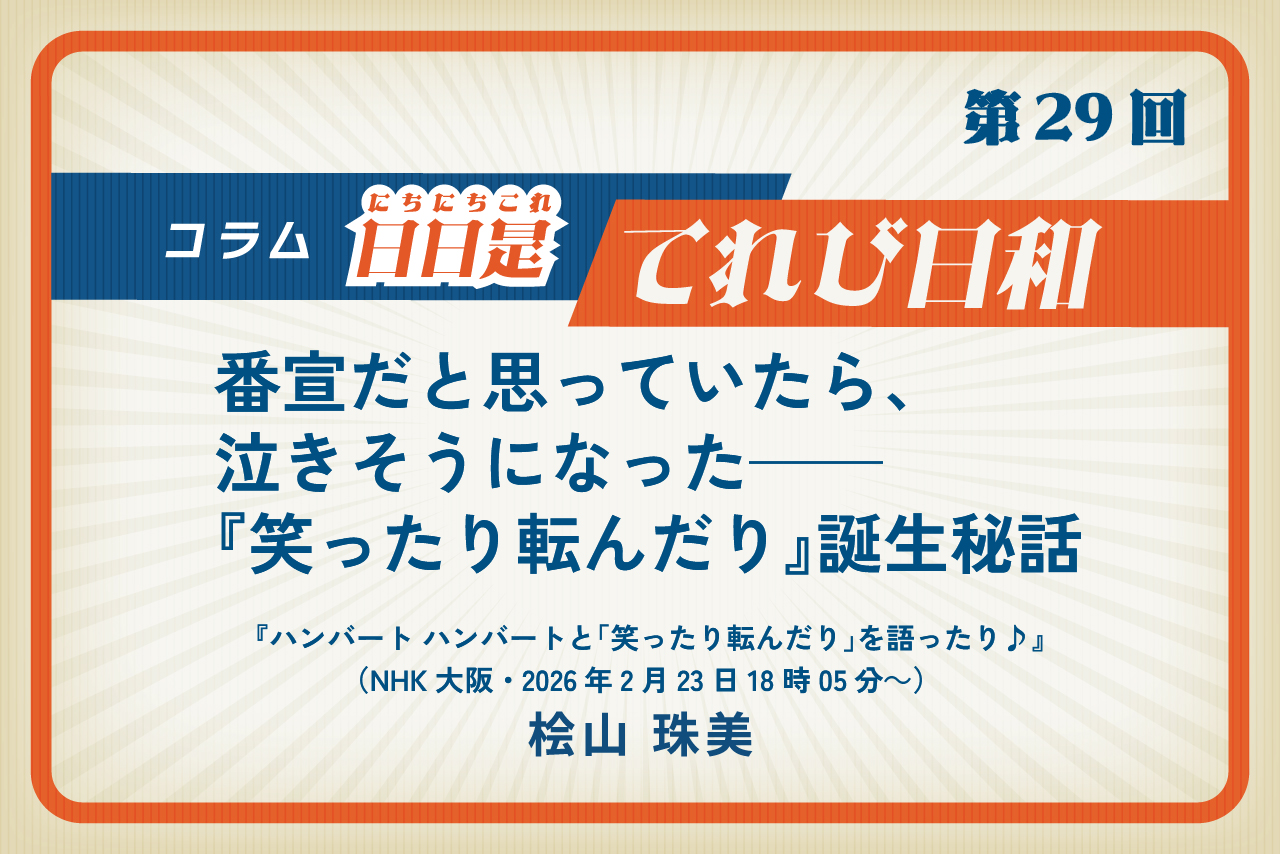放送文化基金賞
【藤井亮×丹羽美之】タローマンの「でたらめ」な世界観、でたらめにあらず。
エンターテインメント部門 優秀賞&脚本・演出賞

『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(NHK、NHKエデュケーショナル、豪勢スタジオ)が、第49回放送文化基金賞エンターテインメント部門優秀賞を受賞しました。この番組は、岡本太郎が残した数々の言葉を主題に、岡本作品を特撮ヒーローや奇獣に見立てた短編特撮番組です。放送後、SNSで大きな話題を集め、展覧会まで開催されるほどの人気になりました。
構成・脚本を手掛けた藤井亮さんには、脚本・演出賞が贈られました。
放送文化基金賞エンターテインメント部門の丹羽美之委員長は、藤井さんに制作の舞台裏を伺いました。

下調べを欠かさない
丹羽
番組として優秀賞、個人としても脚本・演出賞おめでとうございます。
藤井
ありがとうございます。本当に驚きました。賞を頂いた『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(以下、『TAROMAN』)は、深夜に放送されて、しかも1話5分しかない番組でしたので。
丹羽
いい意味で“くだらないこと”に本気で挑んでいた番組でした。エンターテインメントの本質にも感じましたね。
藤井
そう言っていただけるとありがたいです。今回、岡本太郎の作品を特撮のヒーローや怪獣にするにあたって、岡本太郎ファンにも特撮ファンにも納得してもらえているのか、常に怖さはありました。きちんとディテールにこだわらないと内輪ノリでふざけたものに見えてしまうので、なるべく誠実に“くだらないもの”を作りたかったんですよね。今でもこれで完璧だとは思っていないですし。
丹羽
双方のディープなファンを満足させるのは大変だったと思います。そもそもこの番組はどのように生まれたのですか。
藤井
以前、一緒に仕事をした倉森プロデューサーから「岡本太郎の展覧会があるから、岡本の言葉を使って何かPRになるような映像を作ってほしい」と依頼を受けました。彼女とはNHK Eテレの『テクネ 映像の教室』(※1)の中で僕が『サウンドロゴしりとり』を制作した縁がありました。実際には存在しない企業ロゴをたくさん作って、しりとりをしていく映像です。そのイメージで、岡本の言葉を使って面白い映像に、という依頼でした。
丹羽
まず番組のコンセプトとして岡本太郎の言葉があったのですね。藤井さんはそれ以前から岡本太郎のファンだったのですか。
藤井
もともと好きで、家に『太陽の塔』の大きな像を飾っていました。ただ岡本の人柄や作品についてそれほど詳しくはなくて、今回のオファーを受けて川崎市岡本太郎美術館に通ったり、図書館で本を片っ端から読んだりして改めて調べなおしました。僕は勢いでものが作れないタイプなので、今回もいつも通り緻密に下調べをしっかりやって、映像にする上で自分に強く刺さった言葉を選んでいきました。100個くらいは書き出したと思います。
丹羽
その中から10個を選び出して、各話のタイトルにしていったわけですね。藤井さんに一番刺さった言葉は何ですか。
『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(全10話)
第1話 「でたらめをやってごらん」
第2話 「自分の歌を歌えばいいんだよ」
第3話 「一度死んだ人間になれ」
第4話 「同じことをくりかえすくらいなら、死んでしまえ」
第5話 「真剣に、命がけで遊べ」
第6話 「美ってものは、見方次第なんだよ」
第7話 「好かれるヤツほどダメになる」
第8話 「孤独こそ人間が強烈に生きるバネだ」
第9話 「なま身の自分に賭ける」
第10話「芸術は爆発だ」
藤井
やっぱり「でたらめをやってごらん」ですね。「でたらめをやろうとしても、結局みんな自分が知っている何かをもとにしてしまう。だから、でたらめは難しい」という話ですが、『TAROMAN』の世界観を決定付けた言葉になりました。僕自身「でたらめ」をやれているのか、常に意識していたい言葉でもあります。
丹羽
何か新しいものを作ったつもりでも、実は自分が知っている何かに似たものであることが多い。いざ「でたらめ」をやろうとしても意外に難しいですよね。
藤井
新しいものを生み出そうとするときに、過去にあったものをいかにサンプリングしていくかという発想になりがちですが、「でたらめ」であることを忘れずにいたいですね。
遊びたくなる嘘
丹羽
岡本太郎の言葉を映像化していくとき、どうして「特撮」という選択をしたのですか。ドキュメンタリーやドラマなど、いろいろなアプローチが考えられますが。
藤井
NHKだけでも岡本太郎は何度も取り上げられているので、そこで勝負するのはもう難しいなと思いました。みんなが思ってはいたけど、まだ誰もやっていないことは何だろうと考えていたとき、特撮にするというアイデアが浮かびました。『太陽の塔』が動き出して、レーザーなんか発射したら…という妄想はするんですけど、意外に映像化はしていないな、と。
丹羽
岡本太郎の作品ってたしかにどれも怪獣に見えなくもないですね。1972年に放送された番組という設定も斬新でした。
藤井
現代の設定で特撮にしてしまうとCG制作等にお金がかかるので、まず予算的に厳しかった。それに岡本太郎が活躍した70年代、特に大阪万博(1970年)の雰囲気が出せる時代の特撮がいいなと思いました。岡本の筆跡はしっかり残っているので、手作りっぽさや、アナログの感じがよく似合う気がしたんです。
丹羽
70年代はウルトラマンシリーズも名作揃いで特撮が輝いていた時代でもありますよね。岡本の作品と70年代の特撮の雰囲気が見事にハマっていました。撮影時の苦労などはありますか。
藤井
その時代にいそうな顔をしつつ、当時の喋り方ができる演者を探すのが大変でしたね。なかなかどちらの条件も満たす演者さんはいなくて、結局、顔と話し方を分けて収録しました。70年代っぽい顔の演者さんに演技だけをしてもらい、声は後で声優さんにアフレコしてもらいました。だから現場の音声はほとんど使っていないです。
丹羽
特に話し方は70年代と今では全然違うでしょうね。今回関わったスタッフの方は、70年代の特撮に詳しい人を集めたのですか。
藤井
何人か好きな人がいるくらいで一緒に試行錯誤しながら作り上げていきました。
丹羽
番組の構成もユニークでした。1話5分という短い時間の中で、番組前半が『TAROMAN』の本編、後半は『TAROMANと私』と題して山口一郎(サカナクション)さんにインタビューという二部構成になっていました。『TAROMAN』が1972年に放送された番組であり、山口さんは幼少期にその再放送を視聴していたという設定で、山口さんは嘘の思い出をひたすら語っていましたね(笑)。あのフェイクの設定はどういう意図で入れることになったのですか。
藤井
特撮部分だけだと、これが岡本太郎の作品だという説明の余地がなかったんですよね。かといって、普通に説明するのも興ざめする。そこで、当時放送を見ていたときの思い出を語ってもらうことで岡本の作品を紹介することにしました。ただ人気の俳優さんや芸人さんに話してもらうと嘘っぽくなる気がしたので、リアリティのラインとして絶妙な、歌手の山口さんにしました。彼も岡本太郎が好きなんですよ。

丹羽
『TAROMANと私』はハッシュタグになってTwitter上でも盛り上がりましたね。視聴者それぞれが『TAROMAN』の思い出について、まるで本当のことのように語り出す現象が起きました。こうしたことは予想していましたか。
藤井
1人2人くらいはそういうことをツイートしてくれるかなと期待はしていましたが、予想以上の広がりで驚いています。誰かの記憶の中に「なんか変なのやってたよね」と、ちょっと残っていてくれたら嬉しいなと思っていたので。
丹羽
SNSで盛り上がりを見せ、イベント、グッズ発売、さらにスピンオフ作品の放送と『TAROMAN』の世界は今も広がり続けていますね。続編『帰ってくれタローマン』も8月に放送されました。みんなが集まって遊びたくなるような『TAROMAN』の魅力についてご自身でどう捉えていますか。
藤井
番組として丁寧に説明しない、いわば不親切な構造になっていたので、視聴者が自分で状況を理解する必要がありますよね。特撮部分は当時本当に放送されたかのようなリアルさがあり、山口さんの語り部分はモキュメンタリーの手法でさらに嘘を重ねている。そういう構造になっていることに気づく楽しみもあったかもしれないですし、ツイートでさらに嘘を重ねていけるところが面白い要素になったのかなと思います。
丹羽
たしかに、かなり不親切な番組ですよね(笑)。一度見ただけでは、何が何だかよくわからない。多くの視聴者が「なんだ、これは!」と感じたと思います。でもそれがかえって、みんなの想像力を掻き立て、自分も参加したいという気持ちにさせたのかもしれません。
藤井
作品の全体像を把握するには、情報不足で隙間だらけの番組になりました(笑)。
ルールの隙間に「でたらめ」がある
丹羽
私は『TAROMAN』を拝見して、今のテレビに対する批評的なメッセージがあると感じました。「同じことをくりかえすくらいなら、死んでしまえ」という強烈な言葉もそのひとつですね。テレビでは、何かヒット番組が出ると同じような番組がいくつも誕生してしまうことがあるんですが、『TAROMAN』では新しいものにチャレンジしていく大切さを訴えていました。
藤井
僕自身も常にその言葉を肝に銘じて作品作りをしています。ただ同じ人が作品を作ると、見た目が違っているように見えても言いたいことは同じになってしまうことがあります。その難しさはありますが、毎回違う作品を作り続けられたらなと思っています。
丹羽
さきほども出てきた「でたらめをやってごらん」という言葉も、テレビに対するメッセージとして私は受け取りました。今のテレビは「でたらめ」をやりづらい状況になっていると感じています。藤井さんは、その点についてどう思いますか。
藤井
コンプライアンスが厳しくなっている領域で、もともと表現や作品作りをしていないので、まだまだ「でたらめ」をやれる余地はたくさんある気がします。僕はルールを破るより、いかにそのルールの中で隙間を見つけて遊べるかを考えるのが好きです。今回の場合、岡本太郎の言葉や作品に関する部分はきちんと作らないといけないですが、それ以外のところでなるべく遊びがあるようにしています。
丹羽
そういった遊び心は『TAROMAN』にたくさん詰め込まれていましたね。お話を伺っていると、各話に登場する言葉は藤井さんの仕事観、人生観にもつながっている気がしました。今後も藤井さんの「でたらめ」な作品を楽しみにしたいと思います。本日は、ありがとうございました。
藤井
『TAROMAN』を作る過程でも悩んだり、迷ったりしたとき改めて岡本の言葉に戻って何度も助けられました。これからも「でたらめ」を続けていきたいと思います。こちらこそ、ありがとうございました。

※1『テクネ 映像の教室』は、映像に興味を持つ若い人やクリエーター向けに、映像の見方を教え、映像制作の本質を伝える番組。NHK Eテレで放送された。
プロフィール

藤井亮さん(ふじい りょう)
映像作家/クリエイティブディレクター/アートディレクター
1979年生まれ。愛知県出身。武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン科卒。電通関西、フリーランスを経てGOSAY studios設立。考え抜かれた『くだらないアイデア』でつくられた遊び心あふれたコンテンツで数々の話題を生み出している。アニメーションなどの多くの工程を自ら行うことでイメージのブレのない強い表現を実現している。

丹羽美之さん(にわ よしゆき)
エンターテインメント部門審査委員長
1974年生まれ。東京大学大学院情報学環教授。専門はメディア研究、ジャーナリズム研究、ポピュラー文化研究。主な著書に『日本のテレビ・ドキュメンタリー』、『NNNドキュメント・クロニクル:1970-2019』(いずれも東京大学出版会)などがある。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る