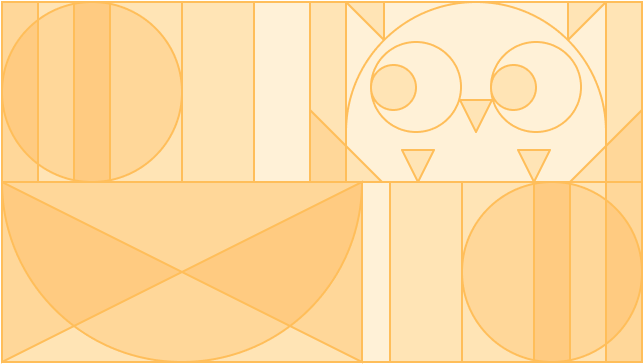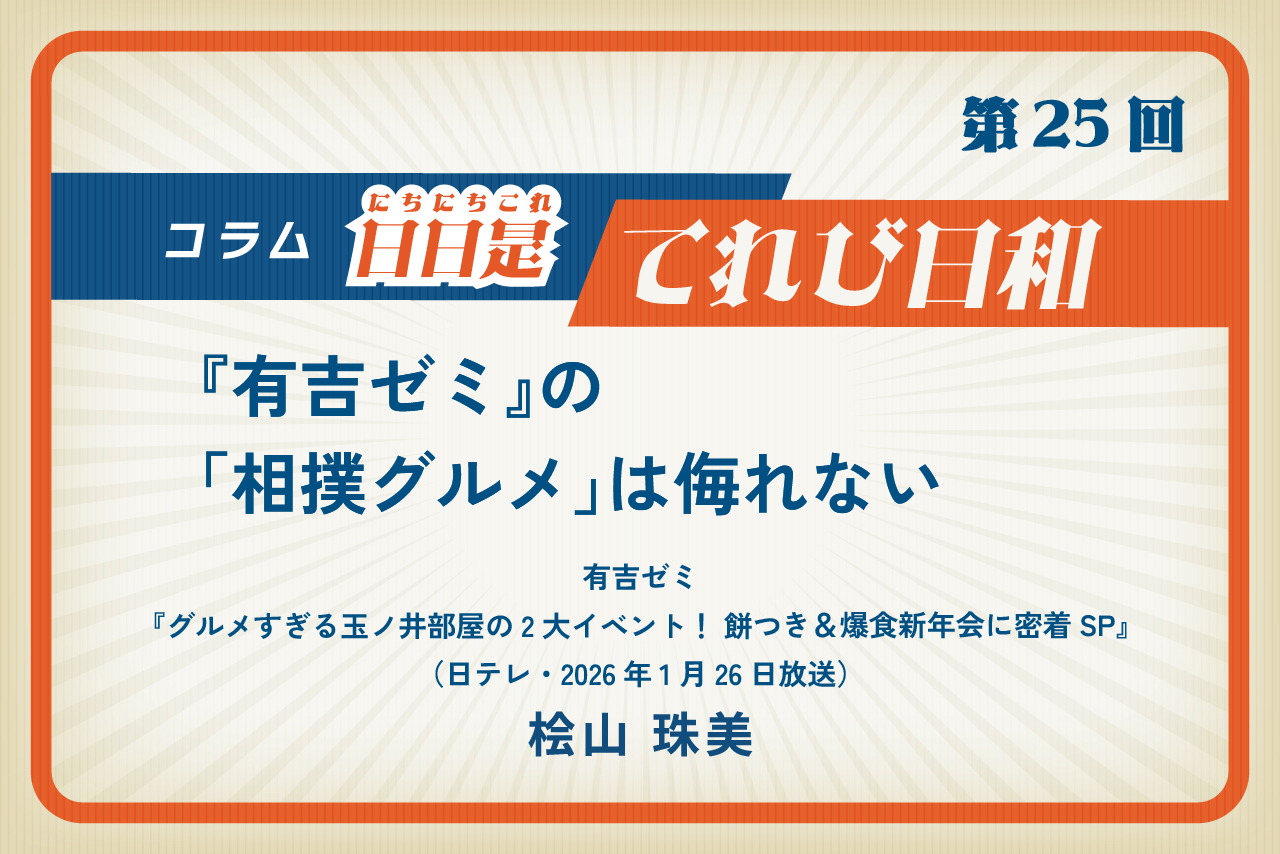放送文化基金賞
【金田一秀穂ルポ】ラジオのこちら側と向こう側『受話器の向こうから~026-237-0555』(信越放送)
番組部門 ラジオ番組 奨励賞&企画賞

信越放送ではリスナーからのメッセージを電話でも受け付けている。リスナーからかかってくる電話は毎日平均50件ほど。第43回放送文化基金賞ラジオ番組部門で奨励賞を受賞した「受話器の向こうから~026-237-0555」はリスナーと電話オペレーターとのやり取りを題材にした作品だ。受話器を通して語られる笑い、ドラマ、そしてリスナーの人生。ラジオの裏側にいる存在に焦点を当てる、そのアイデアと企画力が評価され、制作したディレクターの笠原公彦さんは企画賞を受賞した。
どのようにしてこの番組ができたのか話を聞くため、金田一秀穂ラジオ番組審査委員長が長野市にある信越放送を訪ねた。



今年のラジオ番組部門の奨励賞と企画賞は、信越放送の「受話器の向こうから〜026-237-0555」に決まった。
ラジオ部門の審査員を引き受けて10年以上になるが、このような番組は初めてだった。審査委員一同、こんな手があったかと思わされた。
この番組は、しいて言えばドキュメンタリーであるのだが、ふつうドキュメンタリーと言うのは、何らかの事件や人の生き方を追ったものであるだろう。そこで扱われるのは、だいたい決まっている。このような括り方は乱暴であるけれど、東日本大震災などの災害モノ、沖縄やシベリア、原爆などの戦争モノ、病気や介護などの障害モノ、過疎化や自然破壊などの環境モノ、貧困や犯罪などの社会モノ、ラジオの特性を生かした音楽モノ等々である。取材の対象になるものが見つかったり気付いたり思いつかれたりして、そのテーマが決まる。そこにみんなが集中してデータや資料を集めに走り、関係者に会いに行き、話を聞いて声を拾う。おおむねそのようにして、番組が作られていくのだろうと推察される。
信越放送は、その前に大きなひねりを加えて、ラジオについてのラジオを作ってしまったのだ。
言葉についての言葉による表現をメタリンガルと言うのだが、ラジオについてのラジオは、メタラジオである。これはとても特殊なことで、たとえば、音楽についての音楽を作ることができないし、絵画について絵画で表現することは出来ない。しかし、ラジオという媒体は、ラジオ自身について、自家撞着にならずに表現できてしまうのだ。そして、そのことは、今回の番組ができるまでは、ラジオ制作者たちの誰もが思いつかなかったことなのだ。
最初はたぶん、そんなにひねろうと思っていたわけではないに違いない。結果として、そのような不思議な形になった。それは番組の制作過程がふつうではなかったことにもよる。
信越放送では、聴取者の声を一日中電話で直接受けている。今、多くの放送局は、ネットやファックスで意見を集めるのが主になっているらしい。いまだにアナログ的なやり方で、電話を通して聴き手の感想を集めている。これが宝の山であることに気付いた人がいた。そうして集められた聴取者たちのとても自然な生の声の録音を編集して、番組にしてしまったのだ。マイクを向けられていないおしゃべりは、とても気持ちがよく、貴重である。
通常は、テーマがあってそれに向けて取材して材料を集めるのだろうと思われるのだが、これは、はじめに材料があって、そこから番組を作り出している。素材の編集が、制作のほとんどの過程を占めている。そんな安直でいいのだろうかと思わせる。
しかし、圧倒的に面白い。番組として、聴かせる。大人たちの鑑賞に堪える質がある。
これはどんな人たちが作っているのだろうか。
夏の盛りの始まる前に、長野へ出かけたのだった。
信越放送へのクレームは1日1件!?
お迎えの車が来て、快適なまま、東京駅へ向かう。
わたしは、平日の朝の都心には、めったに来ない。申し訳ないような気分になってしまった。仕事場への勤め人たちが、ぞろぞろと歩いているのが車窓の外に見えるのだ。とても多くの人たちが、無言のまま、ぞろぞろと歩いているのだ。こんなにも多くの人たちが東京にいて、毎朝この光景が繰り返されていることに、改めて思いを致す。これはなんだかとんでもないことなのではなかろうか。この人たちが、たぶんラジオを聴いている人々なのだろうか。
新幹線は早い。オリンピックで建て替えられたモダンな駅舎から、タクシーで信越放送に向かう。早速運転手さんに取材する。

「ラジオ聴きます?」
「いやあ、あんまり聴かないねえ。」
「え。どうして。」
「テレビ見てるよ。」
「へ?」
「ナビで、テレビが見られるんだよ。待っている間、テレビをつけてる。」
そうなのか、車の中ではラジオを聴くというのは、私なぞのボンヤリした先入観にすぎない。いまや、自動車の中でワンセグを見る。渋滞情報は、ナビでわかる。車の中で聴かれなければ、ラジオは聴かれるところが無くなってしまうではないか。ラジオは聴かれなくなった。ラジオ局取材の早々から、幸先悪いことおびただしい。
信越放送の玄関で迎えてくれたのは、番組ディレクターの笠原さん。局の玄関の鏡に映った像を写真にしていて、凝っている。(写真・右)「企画賞なんで、趣向を凝らしてみました」と言う。少しシャイで、頭がくるくると回るように見える青年。上の階に上司たちがいて、応接室に通される。
信越放送は、テレビも持っている。長野県唯一の民放AMラジオ局である。役割が大きい。
長野県は、実は県内が4つの地域に分かれていて、それぞれ文化が違う。バラバラのまとまらない県として有名であるが、最近はそうでもなくなってきたらしい。以前は長野市のことばかり放送するなと言う意見もあったのだが、今は、CMが違うくらいで、同じ放送を画一的に流しているという。
聴き手からの電話を集めるというとき、私が考えるのはクレーム電話である。訳の分からない人からの苦情や、明らかに不条理な内容の文句が寄せられるのではないか、そうしたことは面倒くさくはないか、番組には、好意的な内容のものばかりが取り上げられていたけれど、どうなっているのか。
局の上司たちは、ニコニコしながら、そんなに多くないよなあ、という顔をしている。一日に一本ぐらいかなあ、と平然としている。あっても何とかなるし、などと落ち着いている。たったひとつのクレームで、全体がビビって自己規制してしまうような風潮にあって、この態度は極めて鷹揚である。と言うか、善意に満ちている。
確かにラジコなどのネットと、どのように共存していったらいいかは考えている。しかし、ネットに関しては、むしろテレビの方が課題が多い。ラジオはわりあいと楽観的である。
「え、そうなんですか。今も来るときタクシーの運ちゃんが…」
「いやあ、大丈夫でしょ。」
ラジオに関して、あまり心配していないのはなぜなのか、スタジオに案内されて分かった。
ラジオスタジオは、広いフロアの一角にある。ガラスに仕切られているのはもちろんなのだが、その外は完全なオフィスである。デスクの上にはパソコンや書類が雑然と積まれていて、壁にはテレビモニターが何台も並んでいる。そうして、この受賞作品のキモである電話交換台が、スタジオのガラスに向かって並んでいる。
スタジオと調整台と交換台が、隣り合わせになっている。お互いの関係がとても近い。ディレクターは、スタジオの出演者のおしゃべりを聞きながら、交換台での反応を見つつ、指示を出すことができる。どうしたらいいか、何をすべきか、みんなわかって仕事ができる。この放送を今聴いている人々と、直接につながっているという安心感が、放送を作っている人たちに見える。
交換台には二人の女性オペレーターが座っている。この人たちが、この番組の実質的な心臓部である。

聴取者のことを一番わかっているのは、出演者でもディレクターでもなく、この人たちなのです、と言われた。
何人もの人々から電話がかかってくる。そのうちの何人かは、声を聞くだけで分かってしまう。あまりかかってこなくなったと思っていると、新聞の訃報欄に名前が載ってたりすることもある。クレームの電話もあるけれど、上手に応対できるようになった。ベテランである。個人情報を訊かれることもある。特定のオペレーターにファンがついたりすることもある。
番組を作るに当たって、電話をかけてきた人たちに、放送していいかどうかの許可を求めたところ、長野県人は人見知りで、皆嫌がるかと思っていたら、全員が直ぐに了解してくれた。「お役に立てるならどうぞ」と言ってくれた人さえいた。リスナーは番組を育てる保護者の気持ちになっているらしい。
笠原氏は言う。ラジオは癒しを提供することが主目的だと思っている。ネットの情報は刺激が強い。刺激で対抗しようとは思わない。むしろ笑い、むしろ安心感、むしろゆったり感を提供していきたい。リスナーの一人は、ラジオを農具の一つとして畑に持っていく、と教えてくれた。ラジオを枝にひっかけて、果実の世話をする、リンゴを収穫するらしいのだ。
信越放送では、送り手と聴き手が一つの家族のようにつながって、お互いにしっかり信頼し合っている。それをオペレーターたちが作り出しているのだ。
ラジオは一人一人とつながるコミュニケーション

受話器の向こう側、と言う番組タイトルが、テーマそのものなのだ。
ラジオの向こう側というとき、私たち一般的な人々は、ラジオ受信機の向こうにいる人々のことを思うのではないか。どんな人が、どんな顔をして、どんな人たちと番組を作っているのだろう。
しかし、放送局の人の側からすると、こうしてマイクの前でしゃべってはいるが、どんな人たちが何をしながらこの放送を聴いていてくれているのだろうかと思う。マイクの向こうで聴いている人たちのことが、ラジオの向こう側である。
受話器の向こう側は、私たちが聴いている放送局のスタジオの、更にそのまた向こう側のことであり、つまり、聴いている私たち自身のことになっていく。私たちがどんな暮らしをして、どんなことを日々感じ考えたりしているのか、どんなことに喜んだり腹を立てたり悲しんだり楽しんだりしているのか。
テレビやラジオで聴く情報は、なんとなくわざとらしい。私達とは違う人が、紋切り型の感想を述べ合い、なあなあですませていき、表面的な和やかさだけで終わらせていく。そのようなことに、半分飽きているのだろう。つまらない。
この番組を聴いているのは、私たち自身のことなのだ。だから満足させられてしまうのだ。
テレビは第三者の匿名性、群衆と言う巨大な塊のなかで棲息している。人々の互いの信頼はいっさい求められない。偽善か虚構か、その全体は得体のしれないシステムになっている。そこで語られる言葉は、当たり障りがない代わりに、誰の心にも訴えることのない空疎な記号にすぎない。言いっぱなしの一方通行になって、とらえどころのない闇の中に消えて行ってしまう。ラジオは、かつて深夜放送がそうであったように、一人一人とつながっていくコミュニケーションである。ラジオの言葉はいわば1対1の対者言語であり、気持ちを通じさせ心を揺るがせる言葉である。人間の言葉が使われている。信越放送は、それをこの町でしっかりと実現させている。
東京都心の朝、ぞろぞろと無言で歩いていた人々も、じつはこのようなつながりを求めているのではないか。長野では可能でも、東京では難しいのかもしれない。どうなのだろうと考えながら、帰京した。
プロフィール
笠原 公彦 さん (かさはら きみひこ)
1973年生まれ。早大政経学部を6年かけて卒業。ラジオ制作志望で信越放送に入社。以来、テレビ制作5年、ラジオ制作6年半、報道3年半を経て、現在、2度目のラジオ制作5年目。ワイド番組はじめ各種番組のディレクター&プロデューサー。連盟賞最優秀ほか受賞多数。
気になることは、メディア環境が変化・進化するなかでのラジオの価値。
好きな番組は、「ドキュメント72時間」(NHKテレビ)、「テレフォン人生相談」(ニッポン放送)、「五木寛之の夜」(TBSラジオ・1979~2004終了)。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る