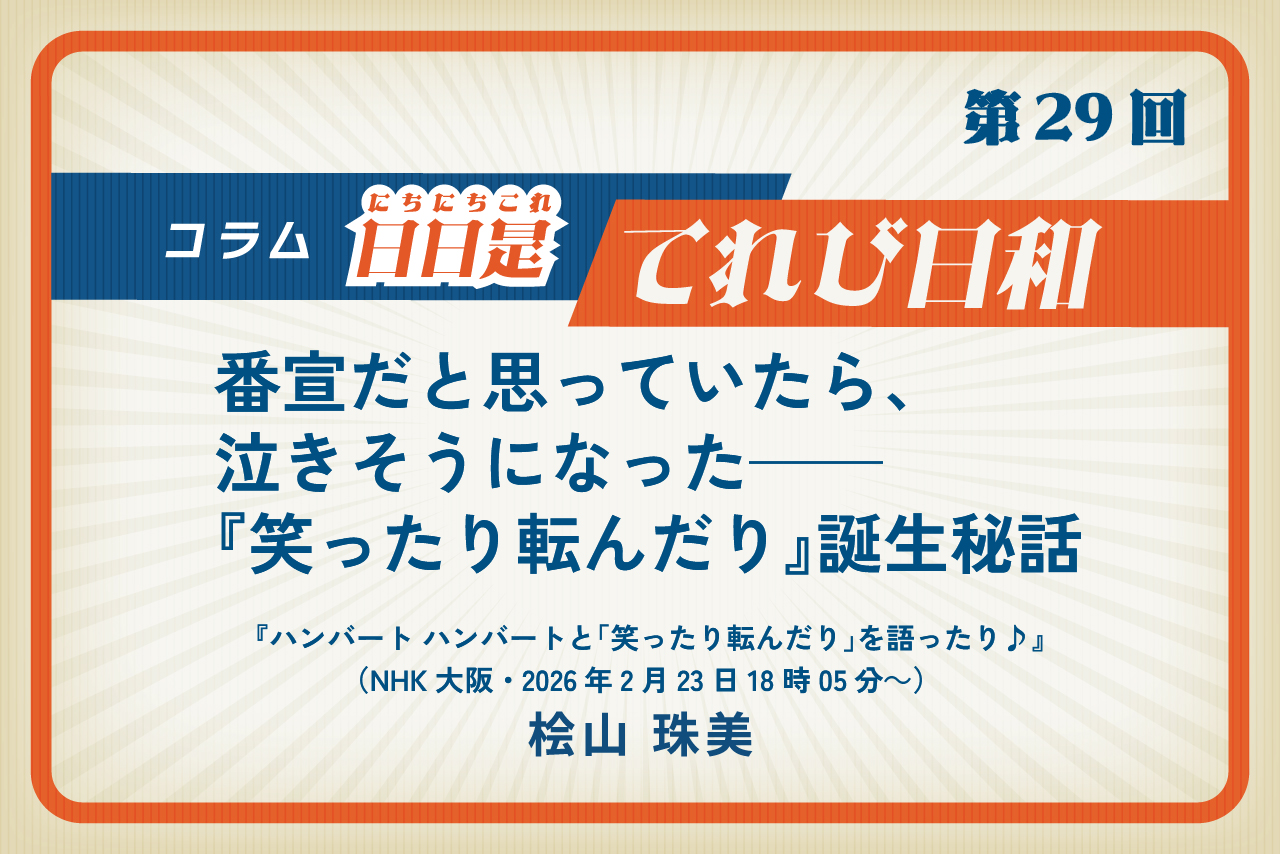HBF CROSS
写真と歌が紡ぐ、心地いい『ばけばけ』の朝
▶▶▶ 『日日是てれび日和』──気になる番組を読み解く週一コラム 桧山珠美
【第11回】連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK・2025年9月29日~ )

新しい朝ドラが始まって早1週間が過ぎた。世間の評判はさておき、少なくとも私の周りではおおむね好評だ。特に、オープニングがいい、との声多数。
前作『あんぱん』の主題歌、RADWIMPSの「賜物」はかなり挑戦的な楽曲で、正直、初めて聴いた時は、あまりの違和感に驚いたが、毎日、聴いているうちに馴染んできて、最終回にオーケストラバージョンが流れてきた時には感動で胸がいっぱいになったものだ。
が、それはあくまでも個人的な感想で、世間的には、朝ドラらしからぬ主題歌で歌詞も何を言っているかわからないという意見も多かった。特に高齢者にとってはなかなかの試練だったようだ。
対照的に、『ばけばけ』の主題歌ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」はその対局にあるような一曲。フォーク調のゆったりとしたメロディと、「野垂れ死ぬかもしれないね」というような聴き込むほどにはっとする歌詞、やわらかな温かみのあるハーモニーは、悲喜こもごもな人生をあらわしているかのようだ。ドラマのキャッチコピー、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」の世界観にマッチした素敵な主題歌である。まだ始まって1週間だが、気がつけば口ずさんでいるほど、耳に心地よい。夫婦デュオであることも小泉八雲とセツ夫婦をモデルとした物語にぴったりだ。
さらに、その歌の世界観と見事にマッチしているのが、川島小鳥の写真で綴るスライドショーのようなオープニングだ。映像ではなく写真を使ったところが斬新で、ヒロイン・松野トキとヘブン夫婦の何気ない日常を切り取ったような温かみのある写真も微笑ましい。これも前作『あんぱん』とは対照的だ。ヒロイン・のぶを演じる今田美桜が近未来的な映像の中を疾走したが、本編との違和感が拭えず、しかも、やなせたかし・暢夫婦の物語のはずなのに、夫は出てこないのか、と思ったものだ。それゆえ、『ばけばけ』の仲良さげな夫婦の2ショットにほっとするのかもしれない。
ひとつ難をいえば、キャストの文字が小さ過ぎることで、これについてはSNSでも騒がれていたが、今のところ変わる気配はないようだ。おそらく、写真と文字のもっとも美しいバランスや余白を考えてのことではないかと察するが、果たして、“みなさまのNHK”は視聴者の声にどう対応するのか、見ものだ。
特筆すべきは語り部となる「蛇」と「蛙」の存在だ。「蛇です」「蛙です」「2匹合わせて蛇と蛙です」と現れた時にはぶっ飛んだが、その声を演じるのが、阿佐ヶ谷姉妹という絶妙のキャスティングは可笑しみが醸し出され、実にいい塩梅。これから先もゆる~い笑いを提供してくれるに違いない。
ヒロイン・トキを演じる髙石あかりをはじめ、演技達者な俳優陣が揃っていて安心して見られる。貧しくとも明るく生きる松野家のひとびとに、見ているこちらも元気になる。
令和ホラーブームが盛り上がりを見せる今、日本の「怪談」を文学に昇華させ、世界に紹介した小泉八雲とセツ夫婦の物語が朝ドラで紡がれること。その僥倖に感謝しつつ、「蛇」と「蛙」とともに、半年間、見守りたいと思う。

▷▷▷この連載をもっと読む
【第1回】予測不能な生放送の魅力炸裂!『平野レミの早わざレシピ! 2025夏』
【第2回】2013年『R-1ぐらんぷり』の三浦マイルドの今に仰天! 『笑いと償い マイルド故郷に帰る ~認知症の母が教えてくれたこと~』
【第3回】音楽に込められた平和への願い 『MUSIC GIFT 2025 ~あなたに贈ろう 希望の歌~』
【第4回】欽ちゃんと浜木綿子、44年ぶりの再会が生んだ感動 『ボクらの時代』
【第5回】時空を超えて蘇る『サザエ万博へ行く』
【第6回】『トットの欠落青春記』-芦田愛菜が生きた“徹子の青春”
【第7回】『旅サラダ』― 佐々木蔵之介のルーマニア紀行
【第8回】終了目前 ― 『激レアさん』が映し出す多様性
【第9回】小雪が伝える発酵の魅力―富山「バタバタ茶」
【第10回】『エヴァンゲリオン30周年特別番組「残酷な天使のテーゼ」時代も国境も超えて』
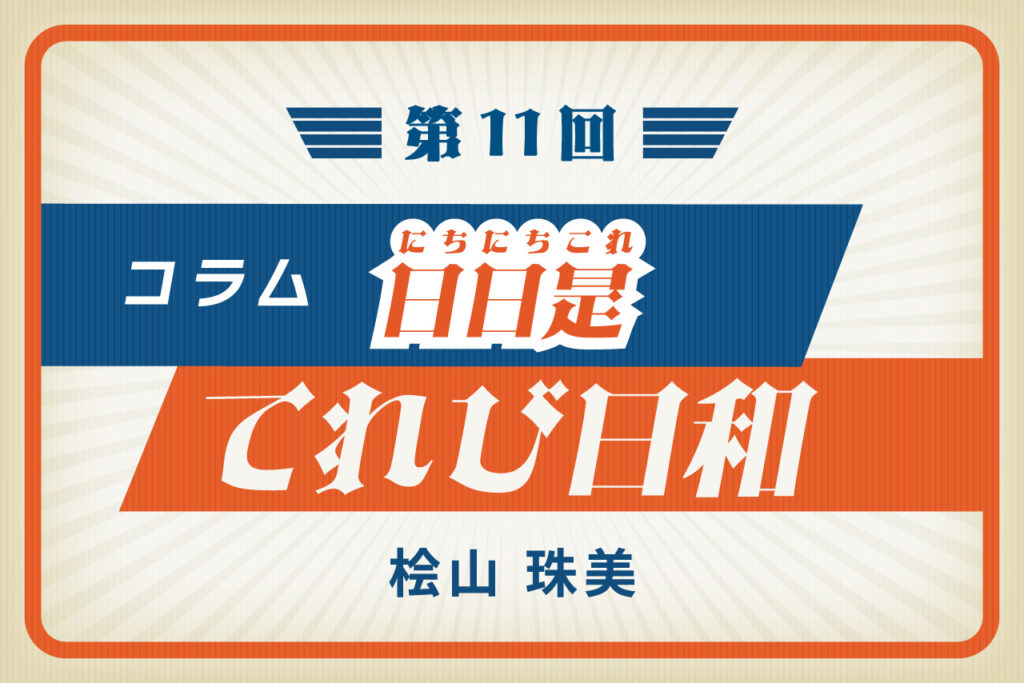
プロフィール

桧山珠美(ひやま たまみ)
HBF MAGAZINEでは、気になるテレビ番組を独自の視点で読み解く連載『日日是てれび日和』を執筆中。
編集プロダクション、出版社勤務を経て、フリーライターに。
新聞、週刊誌、WEBなどにテレビコラムを執筆。
日刊ゲンダイ「桧山珠美 あれもこれも言わせて」、読売新聞夕刊「エンタ月評」など。
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/xb894950/hbf.or.jp/public_html/wp-content/themes/theme/single-magazine.php on line 86
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る