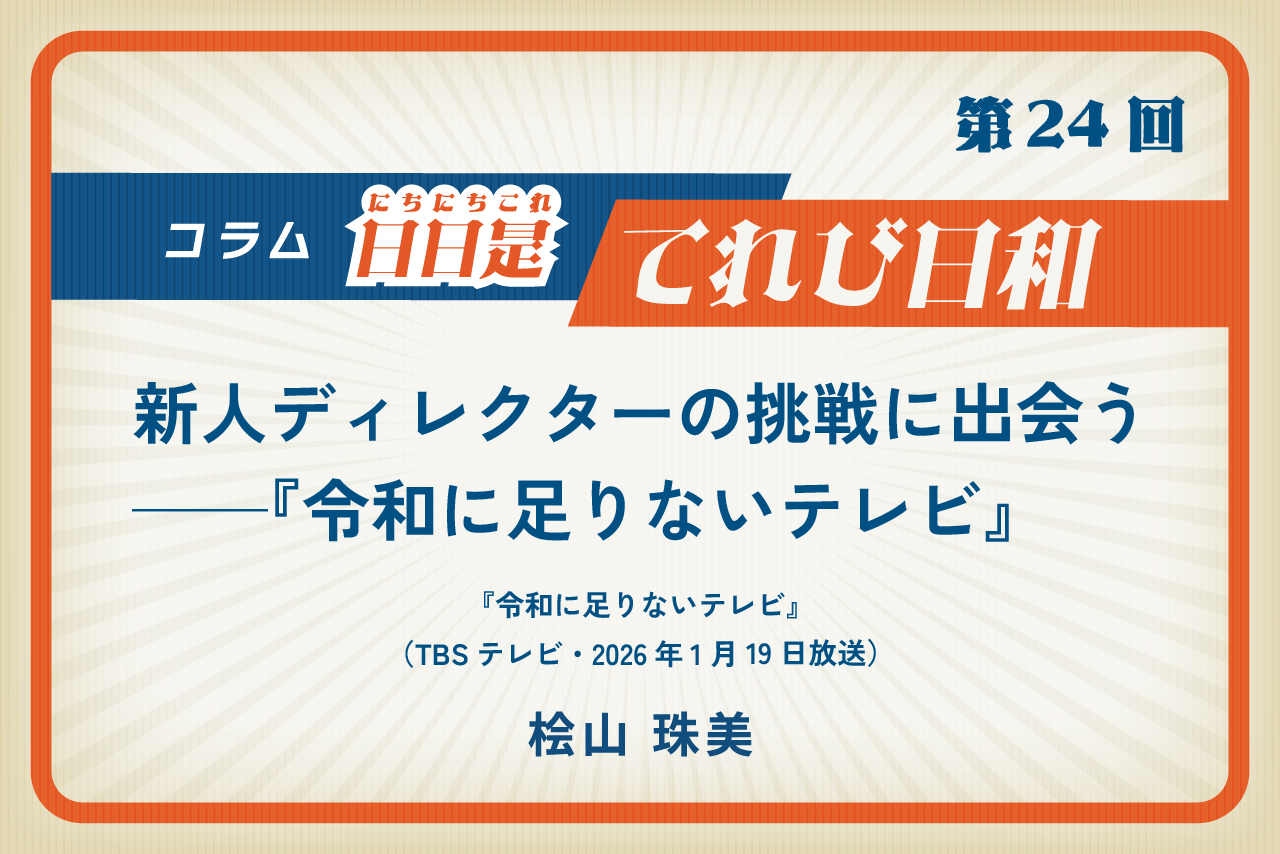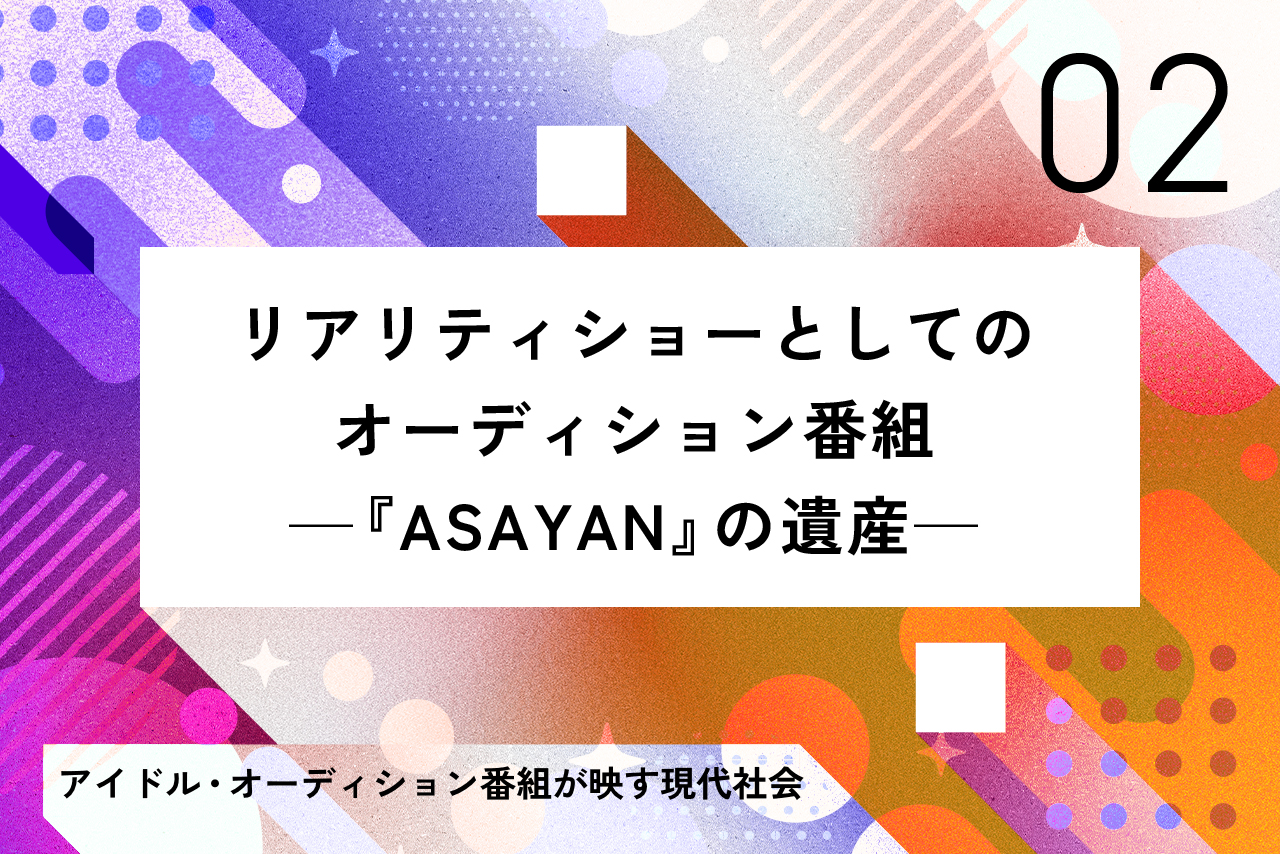HBF CROSS
斉加尚代さん「会社のためではなく社会のために」― 北海道ドキュメンタリーワークショップ第1回
未来へつなぐ灯 連載第1回
北海道放送 山﨑裕侍
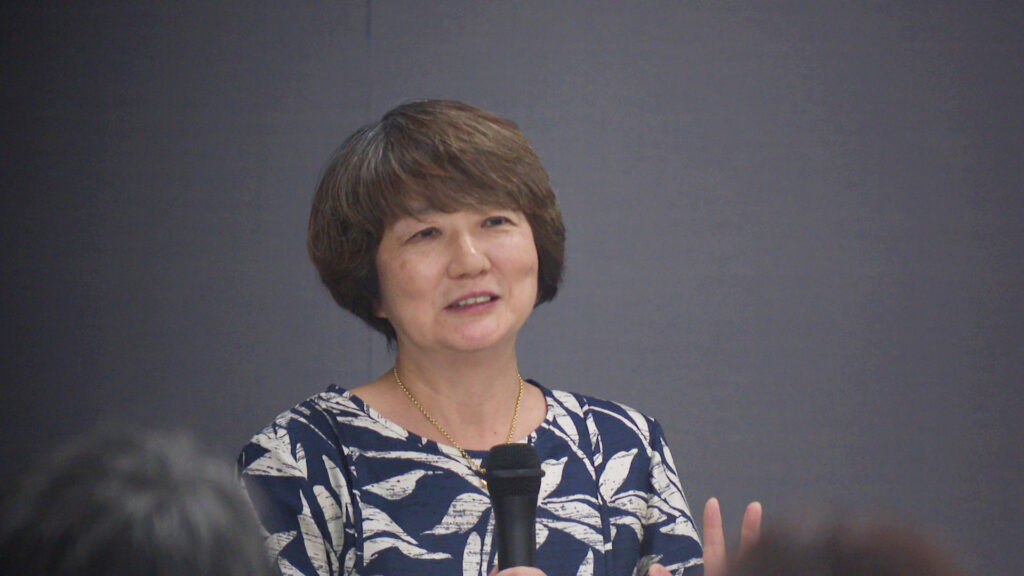
「30人でも集まればいいよね」「来てくれただけでも感謝だね」
私たちはそんな会話をして自らを励ましていた。
北海道ドキュメンタリーワークショップ。
道内の民放・NHKすべての局の有志で実行委員会をつくり、ドキュメンタリーの文化を若手に継承しようとワークショップを企画した。
ワークショップ開幕 ― 初回は73人が参加

第1回は2024年9月14日。北海道放送(以下HBC)の主催だった。ふたを開けてみたら参加者は会場の定員を超える73人。土曜日午前9時半から午後5時までの丸一日の開催にもかかわらず、予想を超え多くの人が集まった。職種も報道部の記者、制作部のディレクター、カメラマン、編集マンといった制作現場だけでなく、営業やデジタル部門と幅広い。
斉加尚代さんが語る映画『教育と愛国』誕生の裏側
ゲストは元毎日放送(以下MBS)のディレクター斉加尚代さん。ギャラクシー賞大賞を受賞し、大ヒットとなった映画『教育と愛国』を監督するなど、日本を代表するドキュメンタリーディレクターのひとりだ。テレビと映画の両方のドキュメンタリー制作の経験があり、局内で作り続けることの困難を乗り越えてきた実績は、座学としても非常に有益だと考え依頼した。

午前の第1部では映画の上映と斉加氏の講演が行われた。1990年代から教育現場を取材してきた斉加氏は、「教師らの苦悩の背後に政治介入があると考え映画の企画書を書いた」と明かした。しかし会社は当初映画化には消極的で「テレビ屋はテレビで勝負すべき」「地味なドキュメンタリーを映画にしても稼げない」と言われたという。それでも社外に協力者が現れるなどして、粘り強く社内を説得し1年あまりかけて映画化が実現した。
若手と議論 ― 相手に誠意を尽くすということ
午後の第2部はHBC入社3年目の貴田岡結衣記者を交えて「取材相手との距離感」「構成とナレーション」といった11のテーマを斉加氏と深掘りして議論した。このテーマは各局の若手に事前にヒアリングをして決めたものだ。


「ドキュメンタリー制作において重視していることは?」との質問に斉加氏の記者としての姿勢が凝縮されていた。
『教育と愛国』で斉加氏は保守色の強い教科書執筆者である歴史学者・伊藤隆氏に複数回にわたりインタビューを行い、「(歴史から)学ぶ必要はないんです」という本音を引き出した。
「取材をする上で重視していることは、どんな立場の人であろうと誠意を持って取材すること。全く思想の違う人でもネット右翼やレイシストでも、相手の意見には同意はしないが、あなたの言うことについては曲げたり歪めたりはしない。だけどこちらは自由に批判し報じますよと伝えることを大事にしている」
「中立を装うのは敗北」 制作者の覚悟
ドキュメンタリーや報道は中立でなければならないという意見に対しても明快だった。斉加氏は、学校で政治的中立性を言われすぎた若い社会科教師がベテランの教師に「私、選挙に行っていいんでしょうか」と相談したというエピソードを紹介し次のように語った。
「教育現場もメディアも中立病というか、議論の割れるテーマについては、一層多角的に深く取材しなければいけないのは当然だが、両論併記をして中立を装うのは制作者として敗北だと思う」
テレビも政治的なテーマを扱うことで政治家からのバッシングを恐れて委縮してしまってはいないだろうか。放送法で定める「政治的に公平であること」とは、テレビ局がどの政治勢力も中立的に扱うという意味ではなく、権力からの介入を防ぎ、放送の独立性とその表現の自由を確保することを意味する。
斉加氏がMBSのドキュメンタリー番組『映像』に携わることが叶ったのは入社20年目。だからこそ作れる喜びと魅力を誰よりも知っている。
「ドキュメンタリーというものは会社のためにあるというより、社会のために存在することがすごく魅力的。会社員という立場を超えて、1人の作り手、1人の記者としてドキュメンタリーに向き合える。そして表現したものを受け取ってくれる視聴者や観客が大勢いることを知れば、どんどん作りたくなると思う」
圧力にどう立ち向かうか ― 若手を支える力
報道と権力との関係も大切なテーマだ。記者からは、権力を批判したときに圧力がかかることがあり、どう向かっていけばいいか質問が上がった。斉加氏は自身の経験を交えて答えた。

「記者クラブに詰めている若い記者たちが、ネットの中で個人名を晒されて誹謗中傷されるのは怖いし嫌だと言う。記者や厳しい取材に臨んでいくディレクターをみんなが支える、守っていくという空気を、それぞれの職場でつくっていかなきゃいけない」
SNSや政治家から攻撃を受けたこともある斉加氏は、放送局が会社として記者を守ること、さらにメディアどうしの横のつながりの大切さを強調した。そして最後にベテランテレビマンに注文した。
「若い挑戦する記者やディレクターたちを支えて、励まして『何かあっても任せとけ』と言って声をかけ続けていただきたい」
ドキュメンタリーをつくる自由な気風を伝承するためには、ベテランが奮い立ち、若者たちを支えていかなければならない。そんなエールをもらった。
参加者の声に見えた“北海道の熱”
終了後、参加者からは「北海道にドキュメンタリーに関心を持ち続ける制作者がこんなに多く存在することに励まされた」「取材相手との向き合い方、心構えや準備の大切さ、日々の生活の中でなぜと思うことの大切さを弊社の若い社員たちにもぜひ聞いてほしいと思った」など好評が相次いだ。
SNSや動画配信サービスが隆盛を迎え、テレビがオールドメディアと言われるが、オールドならではの積み重ねてきた歴史と経験がある。テレビの存在意義、ドキュメンタリーの価値、ジャーナリズムの力を再発見できたワークショップとなった。
プロフィール

山﨑裕侍(やまざき ゆうじ)
北海道放送コンテンツ制作センター報道部スペシャルエキスパート
大学卒業後、制作会社入社。テレビ朝日「ニュースステーション」「報道ステーション」で犯罪被害者など取材。2006年HBC入社。警察・政治担当や統括編集長を経て現職。臓器移植などのドキュメンタリー制作、放送文化基金賞・民放連盟賞・ギャラクシー賞・芸術祭など受賞。第74回芸術選奨文部科学大臣賞。映画「ヤジと民主主義 劇場拡大版」監督。
2024年度北海道ドキュメンタリーワークショップ実行委員長。
「北海道ドキュメンタリーワークショップ」は、放送文化基金の助成を受けて2024年9月から各局が持ち回りで計6回開催。多彩なゲスト講師を招き、放送局の垣根を越えて切磋琢磨し交流を深めることを目的とし、局員に限らず制作会社など放送に携わる人なら誰でも参加できる場となりました。
本連載では、その全6回を月に一度のペースでレポートとしてお届けします。質疑応答のハイライトやゲスト講師が伝えたかったメッセージ・哲学を掘り下げながら、その熱気をお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。
👉この連載の他の記事を読む
🔗【連載第2回】森達也さん「SNS時代の今、映画『A』を振り返る」
🔗【連載第3回】“想定外”が導いたNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』
👉ワークショップの全体の概要や準備の経緯についての記事を読む
🔗 北海道で高まるドキュメンタリー熱(成果報告会2025)
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、事務局レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る