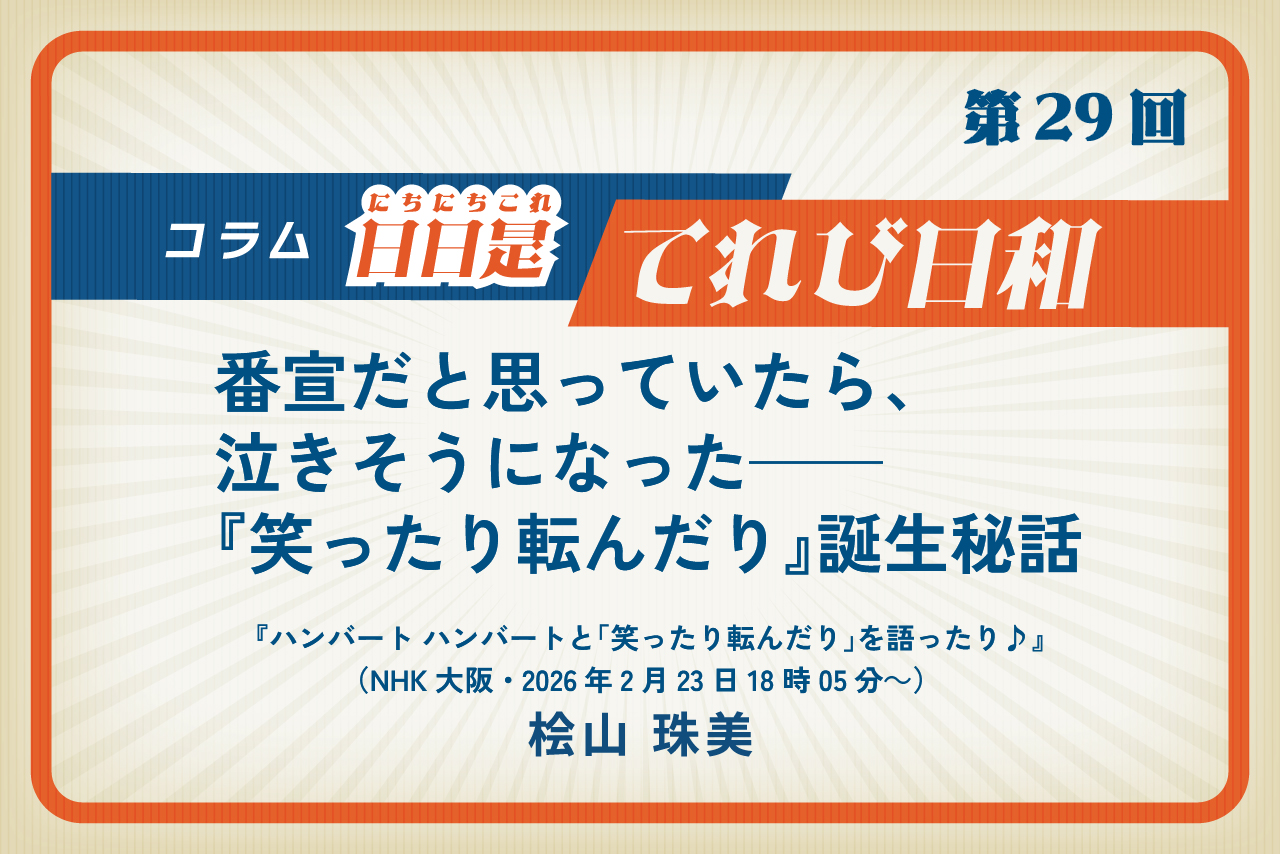放送文化基金賞
未来へつなぐ挑戦―『題名のない音楽会』
第51回放送文化基金賞 エンターテインメント部門
対談 鬼久保美帆×丹羽美之

半世紀以上にわたりクラシック音楽の魅力を伝えてきた『題名のない音楽会』。その60周年記念番組『題名のない音楽会~山田和樹が育む未来オーケストラの音楽会』(テレビ朝日)が第51回放送文化基金賞でエンターテインメント部門の最優秀賞を受賞しました。さらに、6代目司会者としてクラシック音楽の魅力をわかりやすく届ける石丸幹二さんに出演者賞が贈られました。今回、番組の総合演出を手がける鬼久保美帆さんに、審査委員長の丹羽美之さんがお話を伺いました。
一度限りの60周年記念企画の誕生
丹羽
エンターテインメント部門 最優秀賞受賞おめでとうございます。
鬼久保
ありがとうございます。
丹羽
まずは受賞の感想をお聞かせください。
鬼久保
まさか入賞するとも想像していなかったので、信じられませんでした。最優秀賞をいただけるなんて本当に嬉しいです。

丹羽
この番組は、放送60周年を記念して、世界的な指揮者・山田和樹さんと一緒に、18歳以下の子どもたちで一度限りのオーケストラを結成するという企画でした。最初は自分をうまく表現できなかったり、なかなか殻を破れなかった子どもたちが、山田さんの指導によって、少しずつ自分で考え、成長していく姿に魅了されました。音楽の力も強く感じましたし、何より、“一度限りの特別な場”を作り、その中で子どもたちの力を引き出していくテレビの力も感じられる、本当に素晴らしい番組だったと思います。
鬼久保
最初はこれがテレビ番組として成立するのか、ゴールが見えなかったんです。番組では、良い音楽を通して視聴者の皆さんに音楽の素晴らしさや楽しさを届けたい、そして放送を通じて社会に文化的な貢献をしたいと考えています。でも、基本的には一方通行なんですよね。そこで60周年記念の企画を考えるときに、「番組が視聴者となにか直接やり取りできないか」と思い、子どもたちに世界で最も注目される指揮者のレッスンを直接受けてもらおうという企画を立てました。

オーディションで104人全員が合格!想定外の展開
丹羽
オーケストラを結成するのは、この番組の長い歴史の中でも初めての試みで、かなり思い切った挑戦だったと思います。今回の企画の柱となっている山田和樹さんは、世界的に活躍されている指揮者ですが、お忙しい山田さんに、どのように企画を説明して出演してもらったのですか?
鬼久保
山田さんとは、もう15年以上のお付き合いがあります。番組開始25周年を記念して創設された「出光音楽賞」という、有望な若手で新進気鋭の音楽家を支援する賞があるのですが、山田さんは第20回(2010年度)の受賞者でした。それ以来、折に触れて番組に出演していただいています。その中で、山田さんがご自身の演奏活動だけでなく、いかに日本に音楽の文化を根付かせるかを常に考えていらっしゃることも知っていました。また山田さんご自身は、かなり大胆な挑戦を好むタイプなんです。ですので、最初からこの企画にとても前向きでしたが、むしろ大変だったのは山田さんのマネジメント側の方々で、かなり青ざめていらっしゃいました。
丹羽
練習はどれくらい行ったんですか?毎回、山田さんが指導されたんですか?
鬼久保
山田さんがすべての練習に参加するのは難しかったので、不在時はアシスタント・コンダクターに練習を見てもらっていました。練習は全部で4回ほど行い、そのうち2回が山田さんご本人の指導でした。

丹羽
オーディションで104人全員が合格になったのも驚きました。
鬼久保
書類選考は行っていたのですが、山田さんが「オーディションには立ち会いたい」というご希望をお持ちだったため、山田さんが時間的に立ち会える人数として104人に絞りました。その中から50人くらいを想定していたので、まさか全員が合格するとは思いませんでした。
山田和樹の魔法のような指導
丹羽
特に印象的だったのは、初めて集まった子どもたちを一つの集団にまとめていく過程で、山田さんが協調性を求めなかったことです。むしろ逆で、「キャンバスからはみ出せ!」と言うんですよね。揃えるのは後でいい、と。まずは、「自分だけの音を出す」「存在感を出してほしい」という指導には、音楽にとどまらないメッセージ性を感じました。
鬼久保
山田さんは「いかに個性を出すか」を大事にされていました。私たち日本人は文化的に、和を尊び協調性を優先するところがあります。山田さんは、子どもたちが日本から世界に出ていくために、そこから一歩踏み出すことを求めていたんだと思います。これは子どもたちや演奏家に限らず、普遍的なメッセージとして、私たちの心に響くものがあったと思います。
丹羽
そうした“山田イズム”は、他のところにも現れていましたか?
鬼久保
ええ、実は放送には入らなかった場面にも、山田さんの哲学が随所にありました。たとえば、子どもたちは山田さんにサインをもらいたくて、最初は遠慮しつつ様子をうかがっているんです。誰かが勇気を出してもらいに行くと、一気にみんなが集まってくる。でも、あるタイミングで山田さんはスッとそれを打ち切るんです。「みんなが並ぶから自分も」ではなく、「今このタイミングならいけるかも」と自分で判断して動く力。それを大事にされていたように思います。自分で相手を見て、考えて行動する。そうした“処世術”のようなものも、自然と子どもたちに伝えていた気がします。

丹羽
表には出ない場面にも、大切な学びが詰まっていたんですね。
鬼久保
そうなんです。そして、これも放送ではカットしたんですが、練習が始まる前に山田さんから参加者全員へお手紙が配られたんです。その中にユニークなルールが2つ書かれていて、1つは「あくびをしたら即中止」。もう1つは「楽譜は必ず紙で、書くのは鉛筆で」だったんです。
丹羽
最近はiPadを使う子も多いですもんね。
鬼久保
そうなんです。でも、iPadやボールペン、シャープペンシルも含めて全部NGでした。
丹羽
それはどういう意図だったんですか?
鬼久保
私も伺ったんですが、「理由はない」とおっしゃるんです。そもそもクラシックの演奏自体がアナログなので、紙の質感や鉛筆の手触り、そこに何かあると感じていらっしゃると思うのですが、山田さんは、意外と「こうしましょう」と言ったことに理由はないんですよ。“自分で考えてみること”—それが常に山田さんのテーマにあって、言葉では答えを教えないけれど、「きっと何かあるはずだ」と子どもたちに考えさせるんですね。
丹羽
確かに、印象的だったのは「答えを全部は言わない」という姿勢ですよね。たとえば、コントラバスの子どもたちに“ダウンで弾くかアップで弾くか”を選ばせる場面がありましたよね。一度は「ダウン・ダウンで弾いてみよう」と提案しながらも、最終的には「どっちでもいい」と。
鬼久保
「ダウン・ダウン」という運弓は「ダウン・アップ」に比べると大変なんですよ。でも音は強く出る。あえてそれを提示して、「あなたたちはどう考える?」と投げかけていたように思います。
丹羽
そういう一つ一つのやりとりの中で、子どもたちが自分の頭で考え、表現するようになっていく。山田さんの魔法のような指導を通して子どもたちが成長していく様子は、ドキュメントとして見応えがあって、思わず食い入るように観てしまいました。

はじまりは“深夜の一言”から
丹羽
“世界一長寿のクラシック音楽番組”としてギネスにも認定されている『題名のない音楽会』ですが、放送が始まったのは1964年ですよね?
鬼久保
はい、ただ歴史が少し複雑でして……。1964年に東京12チャンネルで、『ゴールデン・ポップス・コンサート 題名のない音楽会』というタイトルでスタートしました。その後、いろいろな事情があって、司会、スポンサー、東京交響楽団、制作スタッフごと、テレビ朝日の前身である日本教育テレビ(NET)に引っ越してきたんです。このときに、タイトルが『題名のない音楽会』に変わりました。
丹羽
その印象的な番組タイトルは、どなたがつけたんですか?
鬼久保
初代司会者だった作曲家・黛敏郎さんが名づけ親です。黛さんの著書によると、タイトル決めにはかなり時間がかかったようで、何度も会議を重ねた末、深夜まで及んだある打ち合わせで、もうみんな疲れ果てていたときに、半ば投げやりな感じで「いっそのこと『題名のない音楽会』というタイトルにしたら・・・」とおっしゃったのが、そのまま番組名になったそうです。
丹羽
偶然のようでいて、なんだか深い意味を感じるタイトルですね。
鬼久保
そうなんです。これはあくまで私の推測ですが、レナード・バーンスタインがハーバード大学で「答えのない質問」という講義をしていたんですね。そして『題名のない音楽会』のベースになったと言われているのが、レナード・バーンスタインとニューヨーク・フィルによる『ヤング・ピープルズ・コンサート』というクラシック番組なんです。黛さんがそれをニューヨークで観て、「日本でもこんな番組があったらいいな」と思われたそうで。そう考えると、『題名のない音楽会』というタイトルも、バーンスタインの「答えのない質問」からヒントを得ていた可能性があるのかな、と思っています。

大人気の公開収録はなかなか当たらない!?
丹羽
ホールでの公開収録の回を拝見するたび、毎回満席という印象があって、番組の人気の高さを感じます。
鬼久保
ホール収録では、前半・後半で異なるプログラムの2本撮りをしていて、毎回、旬の演奏家をお招きして、凝縮されたコンサートをお届けしています。そんな機会って、なかなかないと思うので、とても人気なんです。この公開収録も、スポンサーである出光興産様の「本物の音楽を身近に届ける」という理念に基づいていて、お客様は無料でご招待しています。最近は公開収録が少なくなっていますけど、そこはこだわって続けています。
丹羽
実は私も、何度か応募したことがあるんですけど、一度も当たったことがなくて(笑)。やっぱりすごい人気なんだなと実感しています。
鬼久保
それは申し訳ないです(笑)。
丹羽
いろいろな取り組みを続けていくうえで、一社提供というのは、やはり大きな存在ですよね。
鬼久保
そうですね。「文化的な貢献がしたい」という同じ想いが、いろいろなトライアルもあたたかく見守ってくださるんです。
本物の音楽がわかる耳を育てる
丹羽
鬼久保さんは、東京藝術大学音楽学部のご出身とのことですが、もともと『題名のない音楽会』をやりたくてテレビ朝日に入られたんですか?
鬼久保
入社試験のときはそう言いました(笑)。本当は演奏家を目指していたんですが挫折しまして、大学では音楽理論を学ぶ楽理科に進みました。学者になるのも違うなと思っていたとき、テレビが何せ大好きだったので、「テレビで音楽ができたら面白いんじゃないか」となんとなく思っていました。
丹羽
いまや世界で最も長く続いているクラシック音楽番組のプロデューサーであり、総合演出も手がけていらっしゃいますが、『題名のない音楽会』をつくる上で、一番大切にしていることは何でしょうか?
鬼久保
まず、“楽しくいること”ですね。出演者もスタッフも楽しんでいないと、観ている方にも伝わらないと思うんです。もう一つは、“本物を届けること”。本物の音楽って、知識がなくても「なんかいいな」って感じられるものなんですよね。だから私、『題名のない音楽会』を見続けてくだされば、「本物の耳」が育ちます、ってよく言っているんです。たとえば、贋作を見抜く鑑定士が本物を見続けて選別する力を養うように、いい音を聴き続けることで自然と違いがわかるようになると思うので、ちょっと“耳育”(みみいく)もしているんです。

丹羽
本物の音をテレビで届けるって、すごく難しいことですよね。
鬼久保
実は、番組づくりの中で一番注力しているのが、「音」なんです。演奏を収録したあと、細かくトラックダウン(音の調整・編集)を行います。たとえば、ミスがあった部分はリハーサル音源に差し替えたり、テレビで心地よく聴こえるように、音量やバランスを細かく地道に調整していくんです。時には指揮者、演奏家と一緒にチェックを重ねていくこともあります。
丹羽
そこはなかなか見えない部分ですね。
鬼久保
そうなんです。実は綿密にチューニングされた音なんです。特にホールの音って、そのままだと空気感が多くて、テレビだと意外に迫力がなく聴こえてしまうんです。
丹羽
マイクにも工夫があるんですか?
鬼久保
はい。ホール全体の響きは3点吊りマイクで収録していますが、各楽器につける個別のマイクは、楽器によって種類を変えたり、立てる位置を細かく調整したりします。それも奏者によって変わるので、音声スタッフが綿密に調整しています。
丹羽
まさに職人技の世界ですね。
鬼久保
本当に技術が必要で、もはやテレビの音声マンの仕事の範囲を超えています。それでも手探りで、本物の音を届けるために時間をかけながら仕上げています。
“わかりやすく伝える”力——石丸幹二の存在感
丹羽
出演者賞を受賞された石丸幹二さんの存在感も大きいですね。今回の受賞番組でも、山田さんの指導の意図などを的確に“翻訳”して視聴者にわかりやすく伝えていました。
鬼久保
石丸さんには、視聴者と番組をつなぐ「橋渡し」の役割をお願いしています。石丸さんの素晴らしいところは、難しいことをそのまま難しく話すのではなくて、音楽にあまり親しみがない方にも伝わるように、ちゃんと一般の言葉に置き換えて話してくださることです。加えて、本物の演奏家のすごさが理解できないといけません。石丸さんは東京音楽大学でサックスを専攻された後に、声楽へ転向して東京藝術大学の声楽科に入り直されているんです。幼い頃からさまざまな楽器を経験されていて、音楽への知識も深いですし、劇団四季ではトップスターとして長く活躍されてきた俳優としての表現力もあります。そうした総合力があるからこそ、番組がエンターテインメントとして成立している面も大きいと思っています。

丹羽
鬼久保さんたち制作スタッフの皆さんが作り上げた場の魅力を、しっかりと背負って、画面を通して視聴者に届けてくれる存在が石丸さんなんですね。もう一人の司会者、武内絵美さんの進行やナレーションもとても良いと思います。
鬼久保
武内アナは、スポーツからバラエティまで幅広く対応できるアナウンサーなので、武内アナが進行面を支えることで、石丸さんがより自分の言葉を引き出せるような環境を作ってくれていると思います。
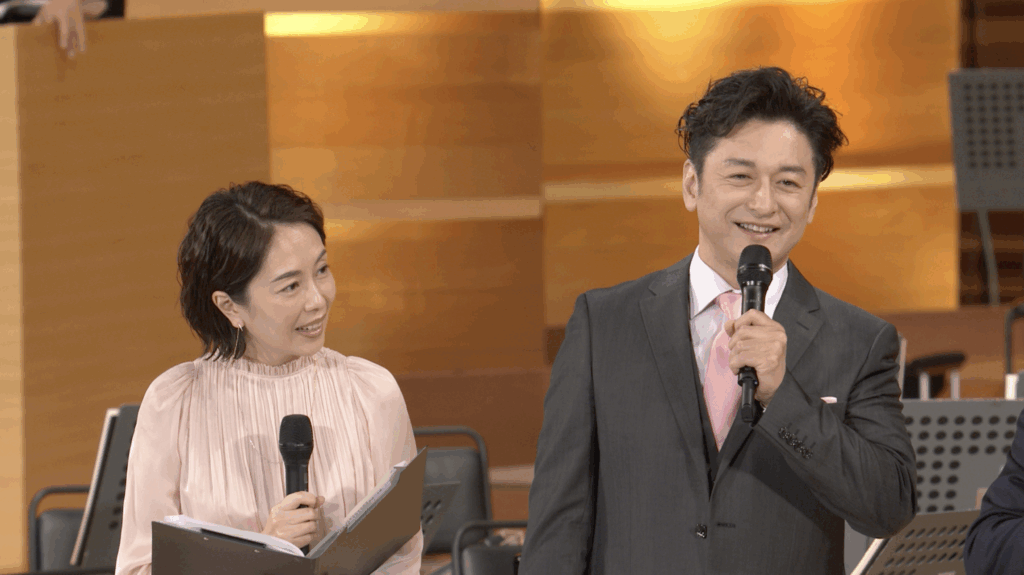
一人の音楽家と伴走できる喜び
丹羽
番組を長く続けていると、出演者との関わりも長くなりますよね。その中で特に嬉しい瞬間はありますか?
鬼久保
長くやっていて本当に良かったと思うのは、ひとりの音楽家の誕生から成長、大ブレイクまでを追えることです。たとえば、第18回ショパン国際ピアノ・コンクールで第2位に入賞したピアニストの反田恭平さん。反田さんは、12歳のときに視聴者参加型企画「振ってみまSHOW!」で、オーケストラの指揮を体験したんですね。そのときの体験をきっかけにピアノに本腰を入れ、世界的なコンクールで結果を残し、今は指揮活動にも取り組んでいます。こうして一人の音楽家の人生を伴走するように歩んでいけるのは、長く番組を続けてきたからこその大きな財産です。
丹羽
番組を拝見していると、次の世代を見いだし、後押しする姿勢も強く感じます。
鬼久保
はい。そこはとても大切にしています。『題名のない音楽会』を25年担当してきましたが、単なる企画づくりではなく、番組外でも人と人をつなげたり、若い才能を発掘・育成したりと、「文化をつくる」という使命感で取り組んでいます。
丹羽
番組をつくる上で、それ以外にも意識していることはありますか?
鬼久保
常に“挑戦し続ける”ことです。伝統や長く続いているものは、守ろうとする意識だけだと、小さくまとまってしまい、結果的に守ることすらできなくなると思うんです。だからこそ、新しい領域に踏み込み、はみ出すくらいの企画をつくらないと、テレビとしての魅力も失われてしまうと思っています。それと、「いかに未来へつなげるか」ということも、常に意識しています。
丹羽
今回受賞した未来オーケストラも、新しいことに挑戦し、未来へつなげる姿勢に貫かれていましたね。今のテレビは「番組として成立するかどうか」ばかりに目が向きがちですが、作り手が楽しみ、情熱を持って挑戦し続けることこそが、エンターテインメントとしての魅力を高める原点だと改めて感じました。今日はありがとうございました。

プロフィール
鬼久保美帆さん(おにくぼみほ)
東京都立小石川高等学校、東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。1995年テレビ朝日に入社し、バラエティ番組を経て2000年より『題名のない音楽会』を担当し現在プロデューサー&演出および『musicるTV』、『BREAK OUT』プロデューサー。『題名のない音楽会』では今までに放送文化基金賞エンターテインメント最優秀賞、ギャラクシー賞テレビ部門優秀賞、民放連賞特別表彰部門青少年向け番組優秀賞など受賞。音楽では「ピティナ・ピアノコンペティション特級ファイナル」、「童謡こどもの歌コンクール」などの審査員を務める。
丹羽美之さん(にわよしゆき)
エンターテインメント部門審査委員長
1974年生まれ。東京大学大学院情報学環教授。専門はメディア研究、ジャーナリズム研究、ポピュラー文化研究。番組アーカイブを用いてテレビの文化や歴史を研究している。主な著書に『日本のテレビ・ドキュメンタリー』、『NNNドキュメント・クロニクル:1970-2019』、『記録映画アーカイブ・シリーズ(全3巻)』(いずれも東京⼤学出版会)などがある。
【番組概要】
『題名のない音楽会~山田和樹が育む未来オーケストラの音楽会』
放送60周年を迎えた長寿番組『題名のない音楽会』が挑んだ特別企画。世界的指揮者・山田和樹と、18歳以下の子どもたちによる「未来オーケストラ」が誕生し、本番を迎えるまでの軌跡を4回にわたり描く。山田の一言で子どもたちが変わっていく瞬間、音楽が自信と個性を引き出していく過程が感動を呼ぶ。クラシック音楽と教育の力を伝える、まさに“未来”へ響く音楽会。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る