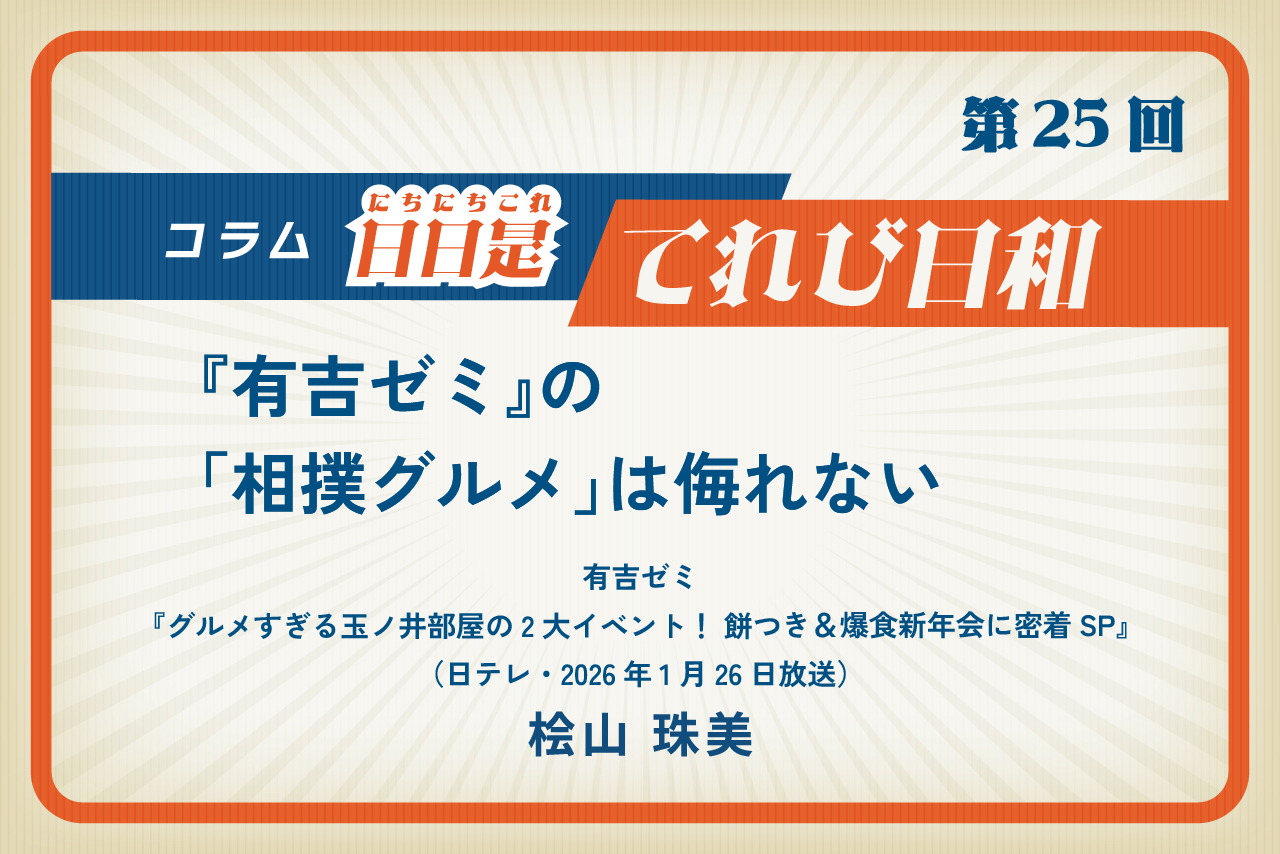HBF CROSS
『灯りのようなものが、たしかに』視聴者に返ってくる“問い”―ローカル局発WEBドキュメンタリーという表現【長谷川朋子】
連載コラム▶▶▶いま、気になるコンテンツ “その先”を読む #6

出所者と、偏見を超えて彼らを雇った人々。その関係をオムニバスで描くWEBドキュメンタリーシリーズ『灯りのようなものが、たしかに〜ある出所者と雇った人たちの七つの物語〜』がYouTube上で静かに広がっている。初回公開から2週間で10万再生に達した。ここで示されるのは正しさでも断罪でもない。現実の手触りのままに差し出された痛みと、それでも消えない小さな希望だ。プロデュースしたのはUHB北海道文化放送。日本財団と組み、「責めない」メディアの形に踏み込んでいる。
語りよりも雄弁に写真で「現在」を突きつける
第1話「大阪編」は、窃盗の罪で受刑後、犯罪当時働いていた焼肉店で再び働き始めた31歳男性が主人公だ。インタビューに答える彼の言葉は軽やかで、笑顔もある。「罪は隠したくない」と堂々と語る姿には好感を覚える。だが同時に、筆者自身が心のどこかで彼を疑う目を向けていたことにも気づかされる。「本当に立ち直っているのだろうか」という無意識の警戒心を呼び起こしていたのだと思う。

その気づきは、インタビューの言葉と交差するように挿し込まれる一枚の写真によって、揺さぶられた。そこに写っていたのは、いまこの瞬間を生きている彼の姿だった。語りよりも雄弁に、「現在」を突きつけられた感覚があった。信じているつもりで、実は信じきれていなかったのは、こちらの側だったのかもしれない。

一方、第2話「福岡編」では、また別の揺さぶられ方をする。障害を抱え、身寄りもなく、生活に行き詰まる中で、特殊詐欺に関わった経験を持つ女性が主人公だ。か細い声ながらも正直に話す女性の言葉に対し、写真はどこか張りつめ、苦しさをはらんでいる。ズボンを握る手、ふとした視線。その一瞬に、言葉にならなかった感情が押し込められているように見えた。
それでも不思議と、そこに絶望だけは残らない。むしろ、人が生きる強さが、静かに立ち上がってくる。救いは、過剰な演出や説明ではなく、映像と写真の“ずれ”のあいだに、そっと置かれていた。
善悪を裁く語りに違和感を覚える
なぜ、こんなにも見方が揺さぶられるのか。その理由は、監督・プロデュースを務めた後藤一也氏が選んだ「作り方」にある。後藤氏はこれまで、所属するUHB北海道文化放送で、出所者が関わった事件の背景に向き合うドキュメンタリーなどを手がけてきた。その経験を積み重ねる中で、善悪を裁く語りや、作り手の正義を前面に出すテレビ的な取り上げ方に、違和感を覚えるようになったという。
ナレーションを置かず、出所者と雇い主の語りを淡々と積み重ねる。さらに、映像の流れの中に写真家・岡田敦氏の静止画を挿し込むことで、物語は一方向に収束しない。説明されない“間”が生まれ、見る側は、理解したつもりになる手前で立ち止まらされる。

その結果、視聴者は登場人物を評価する立場ではなく、いつのまにか「自分はどう見ているのか」を問われる側に立たされる。大阪編や福岡編で筆者が覚えた揺らぎは、まさにそのために設計されたものだろう。今後、更新される岡山や熊本などを舞台にしたエピソードでも、その方向性は共有されていくはずだ。
出所者を取り巻く現実の重さも背景にある。日本の再犯率は、令和6年版『犯罪白書』によれば2023年時点で47%と高い水準だ。その約7割が無職者であり、多くが社会とのつながりを失ったまま、孤立の中で再び罪に手を染めてしまうという構造がある。
本作は、日本財団の「職親プロジェクト」の協力を受けて制作された。だが、このシリーズが真正面から扱っているのは、制度や数値ではない。情報を前面に押し出すのではなく、出所後に人はどれほど脆くなるのかという現実を、関係性の中で見せている。
また、本シリーズは「立ち直り」を成し遂げた成功例として扱っていない。他者との関係を取り戻そうとする過程そのものに、かすかな光が宿る瞬間をすくい取ろうとしている。そのために必要だったのが、評価や断罪を前提としない、あの距離感だったのだろう。
手応えは「10万回の再生数」だけじゃない
後藤氏が強調したのは、作り手としての立ち位置だ。物語を“描く”のではなく、あくまで当事者の存在を“通す”こと。その姿勢が、本作の出発点になっている。
「僕から見た相手のストーリーを描くだけでは、それは自分の正義に過ぎない。だから、自分は“媒介者”に徹したいと思ったんです。相手の痛みや存在を、そのまま捉えて伝えたいと」
その思想を、具体的な表現へと落とし込む存在として、後藤氏は写真家・岡田敦氏の仕事を挙げる。それは、言葉による説明とは異なるアプローチだ。
「岡田さんは、30分くらいカメラを向けたまま、ほとんど何も喋らない。でも、その場にいる相手の純度の高さを待って撮るんです。なのに、結果として強い作家性が立ち上がる。その現場を見て、テレビマンとして反省させられました」

そんな撮影現場を経て、12月1日に第1話を配信開始すると、YouTube上の再生数は2週間で10万回を超えた。後藤氏自身も、この反応は想定外だったという。ただ、手応えとして語られたのは数字そのものではない。
「偏見を崩したり、人に何かを感じさせたりするという意味では、今回のやり方は有効だったと思います」
WEBという選択は、単なる伝える手段の話にとどまらない。後藤氏は、ローカル局が社会的テーマにどう向き合うかという問いにも、視線を向けている。
「社会的なものが、きちんと利益を生み、持続的に作れるのは理想です。でもそうでなければ、結局は“お金のあるものだけが作れる”世界になってしまう。ローカル局がパブリシティだけをやる場所になるのは違う。とにかく、いいものを作らないといけないと改めて思っています」
『灯りのようなものが、たしかに』は、社会問題をわかりやすく整理する作品ではない。だがその代わりに、見る側の視線や判断の癖を、静かに問い返してくる。信じているつもりで、どこかで疑ってはいなかったか。理解したと思った瞬間に、何かを見落としてはいなかったか。
分断が深まるいま、答えを急がず、誰かを裁かず、関係の中に生まれるかすかな光に目を向ける。そんな表現のあり方が、確かにここにある。その灯りは決して強くはないが、目を凝らせば、いまを生きる私たちの足元を、静かに照らしている。

▷▷▷この連載をもっと読む
【#1】SFドラマ『ブラック・ミラー』がNetflixのカルト的人気番組になった理由
【#2】是枝監督が語る「今、残したいテレビドラマ」、短編映画『ラストシーン』にあるヒント
【#3】アニメ『映画 えんとつ町のプペル』復活のカギは「カナリア諸島」との協業にあり?
【#4】坂元裕二が生み出した『Woman』アラビア語版の成功の秘密
【#5】米ドラマ『Boston Blue』に見るテレビの再構築──続けることの力、変わることの勇気
連載コラム▶▶▶いま、気になるコンテンツ “その先”を読む
多様化する映像コンテンツの世界で、いま本当に注目すべき作品とは?本連載コラムでは、国内外の番組制作やコンテンツの動向に精通するジャーナリスト・長谷川朋子さんが、テレビ・配信を問わず心を動かす作品を取り上げ、その背景にある社会の変化や制作の現場から見えるトレンドを読み解いていきます。単なる作品紹介にとどまらない、深い洞察に満ちたコンテンツガイドです。
著者・プロフィール

長谷川朋子 (はせがわともこ)
ジャーナリスト/コラムニスト。国内外のドラマ、バラエティー、ドキュメンタリー番組制作事情をテーマに独自の視点で解説した執筆記事多数。「朝日新聞」「東洋経済オンライン」などで連載中。フランス・カンヌで開催される世界最大規模の映像コンテンツ見本市MIP現地取材を約15年にわたって重ね、日本人ジャーナリストとしてはコンテンツ・ビジネス分野のオーソリティとして活動中。著書に「Netflix戦略と流儀」(中公新書ラクレ)など。
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る