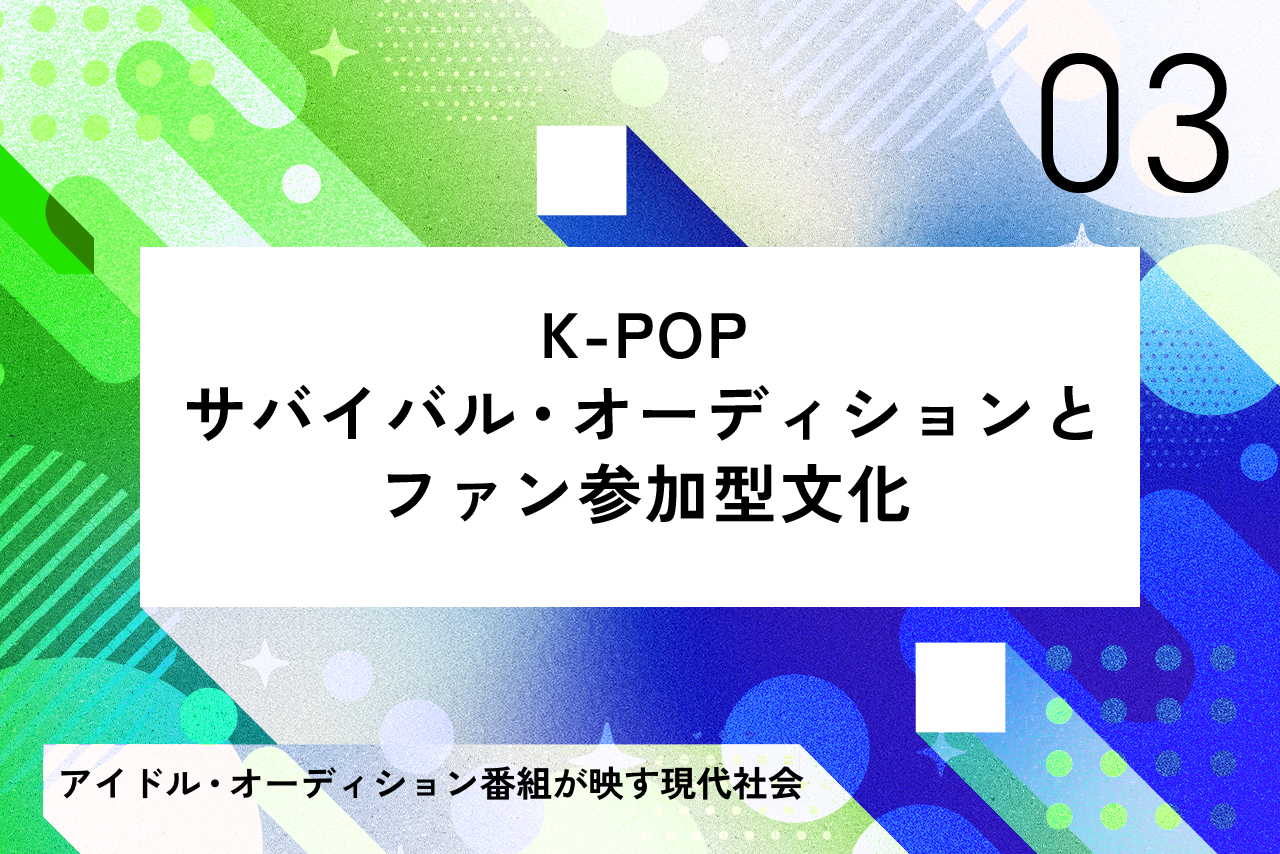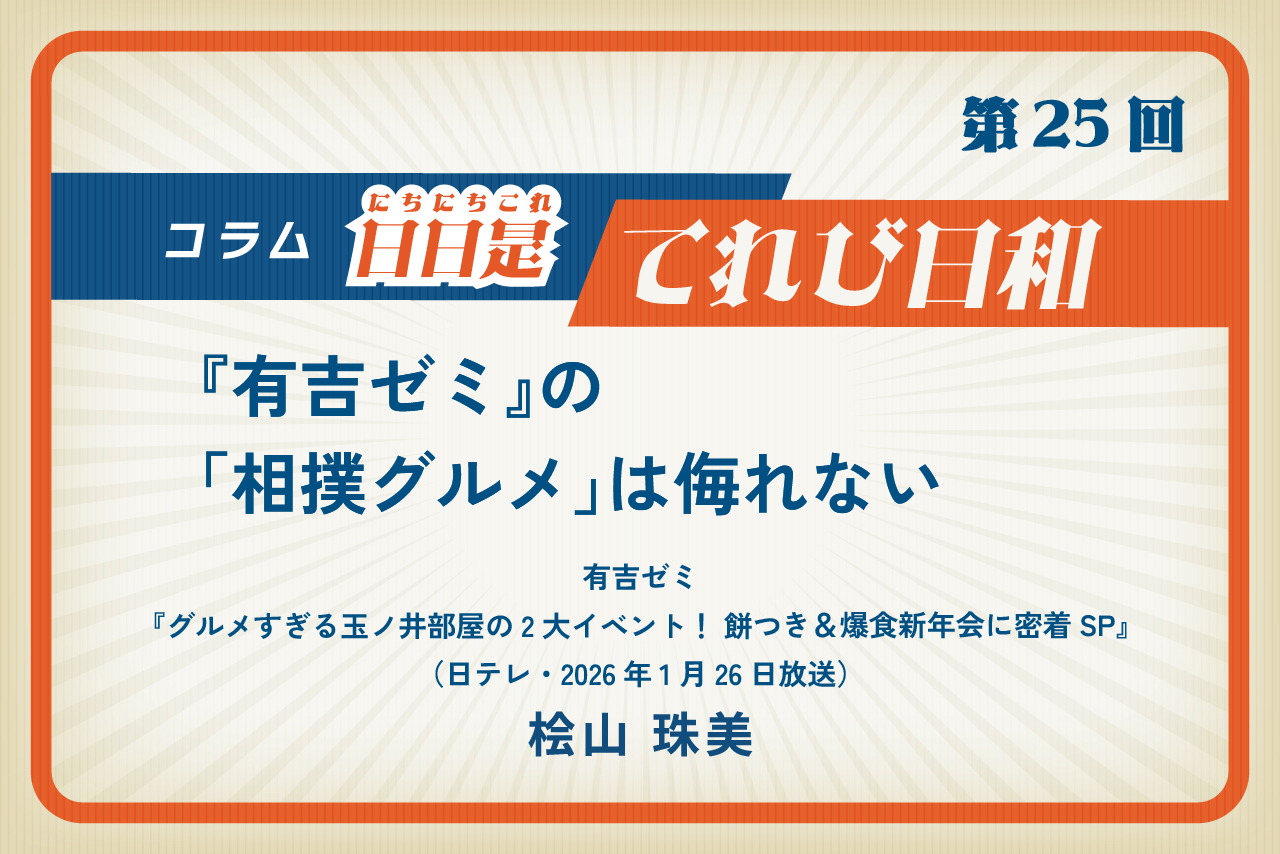放送文化基金賞
【第51回放送文化基金賞】エンターテインメント部門 選考記
未来を感じる至福の時間
丹羽美之
1964年から続く長寿番組『題名のない音楽会』が最優秀賞に輝いた。60周年を記念して、番組史上初の18歳以下からなる「未来オーケストラ」を結成。世界的指揮者・山田和樹の魔法のような指導によって、子供たちがどんどん自分の殻を破っていく姿に魅了された。音楽の力とともに、子供たちの未来を感じさせる至福の時間だった。
優秀賞には、様々なタブーに挑み、日本の障害者像を更新し続けた『バリバラ』が選ばれた。マイノリティの当事者が声を上げ、孤立せずにつながることの大切さを最後まで愉快に訴え続けた。番組は終了したが、その歴史的使命は決してまだ終わっていないと痛感する。
能登半島地震から立ち上がろうとする寿司店の親子を追った『オモウマい店』も傑作だった。「オモウマ」が磨いてきた密着取材のノウハウと、ユーモアに満ちた人物描写を通して、ニュースや報道では伝わらない被災地の日常の風景や思いを描いた。
トランプの壁を越えようとする人々の素顔に迫った『国境デスロード』は、エンタメ部門としては配信作で初の受賞となった。体当たりの取材で、移民たちの懐に入り込み、その希望と絶望の実態や、政治的・社会的背景に迫った意欲作だった。
選考会では、配信作、特にリアリティショーの評価をめぐって激論が交わされた。放送文化とは何かをめぐって、しばらくは模索が続きそうだ。
「ならでは」
澤本嘉光
「エンターテイメント部門」と文字面からすんなり想像すると、バラエティー番組を始めとする『理屈なく楽しい』『くだらない!と言いつつつい見てしまった』ようなザッツ・エンターテイメントな番組を浮かべてしまうのだが、今年の審査で目にしたものはジャンルの広さを物語るように「そうではない番組」が多かった。特に、長年継続してきた番組の特別版や、総集編的なものが。という中で「題名のない音楽会」は歴史と未来を共存させた内容で、この番組にしかできない「ならでは」な説得力を持ち合わせた内容で見ていてドキドキすらする秀作だった。また配信の番組が地上波にはそこまで行けない感のある「ならでは」な番組を提示してくれて結果としてさらに「そうでない番組」の幅を広げてくれたことは嬉しかった。実際にある世代に話題になっていた番組には配信の番組が多かった印象もある。
という中での個人的な希望はこの審査後記に「こんな番組に投票してしまってごめんなさい!でもどうしてもなんです」と謝罪を書けるような「ならでは」なバラエティー番組を来年はもっと目撃したいな、投票するかどうかで葛藤したいな、と。今回は特別編を出品していた番組でも実は平常時の番組コーナー自体が魅力的な番組もあったので、その辺り見れなくて残念と思ったものもありました。推測していただければなあと。
明日のテレビとは何か?今そのことを真剣に考えなくてはテレビは消滅する
土屋敏男
明日のテレビとは何なのか?今その事を考えて実行しなくてはテレビ(地上波)は長い栄華の時を終えるだけではなく消滅してしまう、という思いで審査をした。
言うまでもなくテレビは大きな転換期の中にいる。
YouTube、Netflixなどの配信プラットフォームの出現だけでなくコンプライアンスの問題またHUT低下の問題さらには経営体制の問題まで。その中でテレビが長年果たしてきたエンターテインメントの未来とは何か?残念だったのは多数のテレビ局から「街ブラ」番組が応募されていたことだった。各局の応募番組を選考した人に問いたい。この番組が貴局のエンタメ番組の未来を指し示しているのですか?何の挑戦もしないで未来が築けるのですか?
そんな中でテレビ朝日『題名のない音楽会〜山田和樹が育む未来オーケストラの音楽会』はテレビの未来を指し示すと思った。企画立案、そして撮影対象を丁寧に見つめてそれを何週にも渡って放送していく形式。演出。地上波テレビならではの大秀作だった。
そして3年前から門戸を開いた配信プラットフォームからついに受賞作が現れた。ABEMA『国境デスロード』。このことも今回の審査結果で特筆すべきことだ。これは逆に“地上波テレビ局では今できないもの”という視点で選んだ。そしてこの番組のP、Dがテレビ局出身であることをポジティブに捉えたい。
もうネットがなくなることはない、当たり前だが。その中で地上波テレビがエンターテインメントとして何を作り送り出していくのか?地上波テレビの人たちに改めて切実に問いたい。
「たるや!」
豊﨑由美
長寿番組が終わってしまうのは淋しい。15年間も続いてきた『バリバラ』の終了も残念でならない。マイノリティーが抱えている問題を、当事者の目線から泣き笑いしながら届けてきてくれた功績たるや!最後に優秀賞を授与できる光栄たるや!
……もっと続けては?
『題名のない音楽会』も、子どもの頃から親と一緒に見てきた息の長い番組だ。その放送60周年を飾る4回シリーズでは、オーディションに参加した104名のティーンエイジャーらと指揮者・山田和樹氏が「未来オーケストラ」を結成。山田さんの明朗愉快な指導力の素晴らしさたるや!指導に応える子どもたちの目の輝きたるや!司会・石丸幹二氏のコメントの的確さたるや!今年も最優秀賞にふさわしい番組に出会えて幸せです。
テレビ・エンタテインメントの行方
水島久光
かつて「楽しくなければテレビじゃない」と豪語していた局の危機は、単に一企業の組織問題に止まらず、テレビ・エンタテイメント全体に再考を迫るインパクトを与えた。巨大組織や大物タレントの退場は、どうもその前哨にすぎなかったようだ。
だから今回の最優秀賞が、長寿音楽番組に輝いたのも偶然ではない。オーケストラという時代を超えてきた表現形式と、若き演奏者たちのパッションのぶつかり合い。そこに我々は、心揺さぶられる普遍的な何かを覚えたのだ。
優秀賞の『バリバラ最終回』も、ただ積年の実績を評価したわけではない。むしろこの15年で変われなかった社会が目に浮かんだ。だからこそ粘り強く放送枠に踏み止まった関係諸氏の存在を、確かな記録に残すべきだと考えた。
奇しくも放送 100年である。既に接触時間はスマートフォンに奪われ、映像チャネルとしては配信サービスに主役を明け渡しつつある。今回の応募にも周年番組が目立った。それがイノベーション産出力の乏しさを映す鏡だとしたら、寂しいとしか言いようがない。
奨励賞の二作の題材である『能登の親子』も『トランプの壁』もギリギリの現実を映し出したものである。確かにエンタメ的エッセンスに優れてはいる。でもそれは我々がこれまで放送文化として期待してきたものとは少し違うような気もする。
テレビ・エンタテインメントの未来は、いったいどこにあるのだろうか。
家にテレビがない子どもたちが増えても
三宅香帆
家にテレビがない、という同世代の声をしばしば聞く。見たいテレビ番組があればスマホでTVerやPrimeVideoをひらけばいいわけだし、話題作は大抵Netflixやhuluで配信される。テレビ番組が勝手についていて、お茶の間の話題の中心になる、なんて時代はいつのまにか通り過ぎた。そんな流れに追い打ちをかけるかのように、昨年から今年は、テレビ業界に不信感を募らせる報道も多かった。
──しかしこのような時代にあって、放送文化基金賞の審査委員にありがたくもお誘いいただいた時に感じたことと言えば、「いまの時代に放送文化にしかつくりだせないエンターテインメントとは何だ」という問いに興味を持ったのだった。
今回大賞を受賞した『題名のない音楽会』は、まさにテレビ番組にしかつくりだせない良質なエンターテインメントだった。演奏とドキュメンタリーと解説がうまくかみ合った映像に、シンプルに感動した。なんて簡単な感想なんだと笑われてしまいそうだけど、見ているとき心が動いた。子どもたちにとっても、音楽業界にとっても、この番組が続いてきてよかったなあとしみじみ思った。テレビの企画でもないと集まり得ない子どもたちだったかもしれないのだ。
長く続く番組が、新しい演者を出したり、新しい企画に挑戦したりして、新鮮な風をテレビに吹かせる。これこそが誠実な仕事そのものだと思う。家にテレビがない子どもたちが増えても、テレビにかかわる大人が真摯に誠実に挑戦を続けていれば、番組というエンターテインメントはひとびとを楽しませ続けるのだろう。今回そのことを信じさせてくれた作品たちに出会えたことが、とても嬉しかった。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る