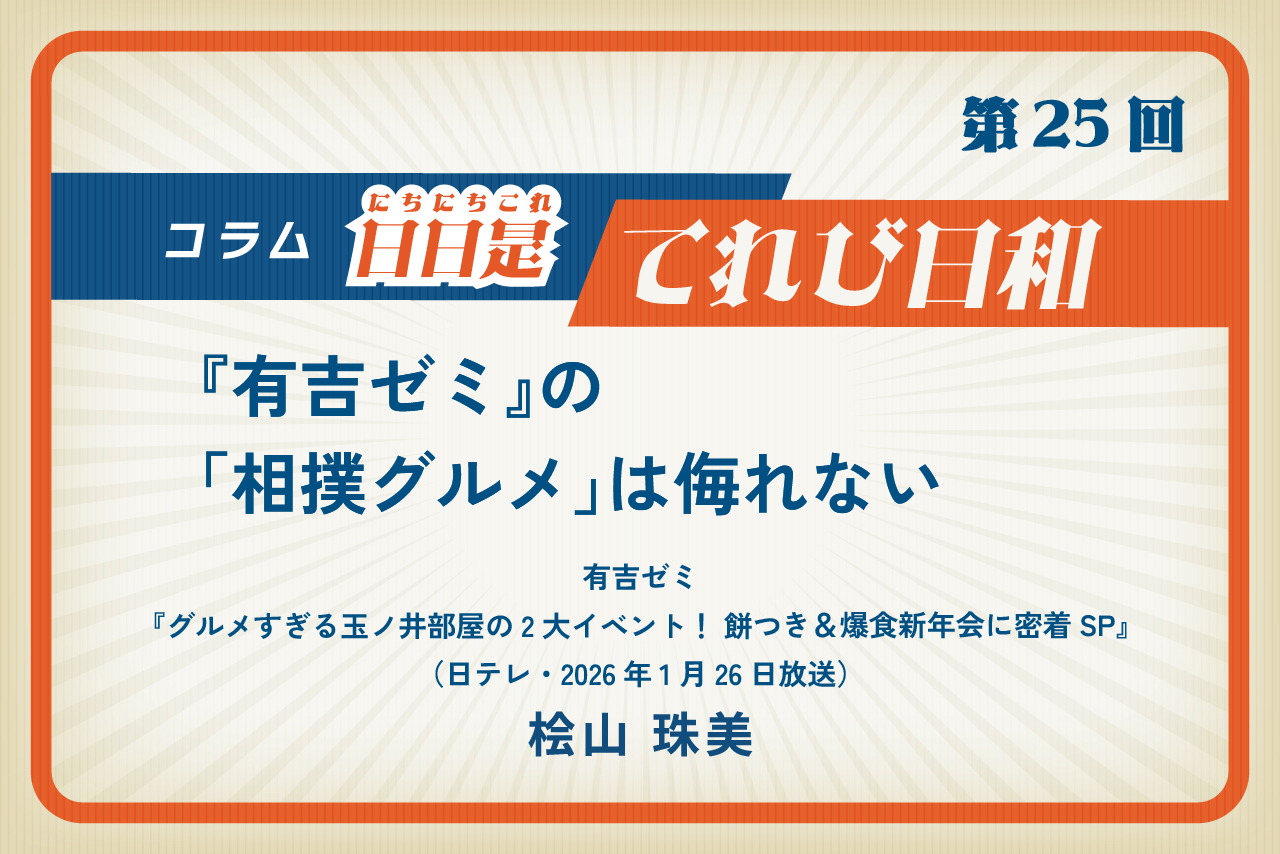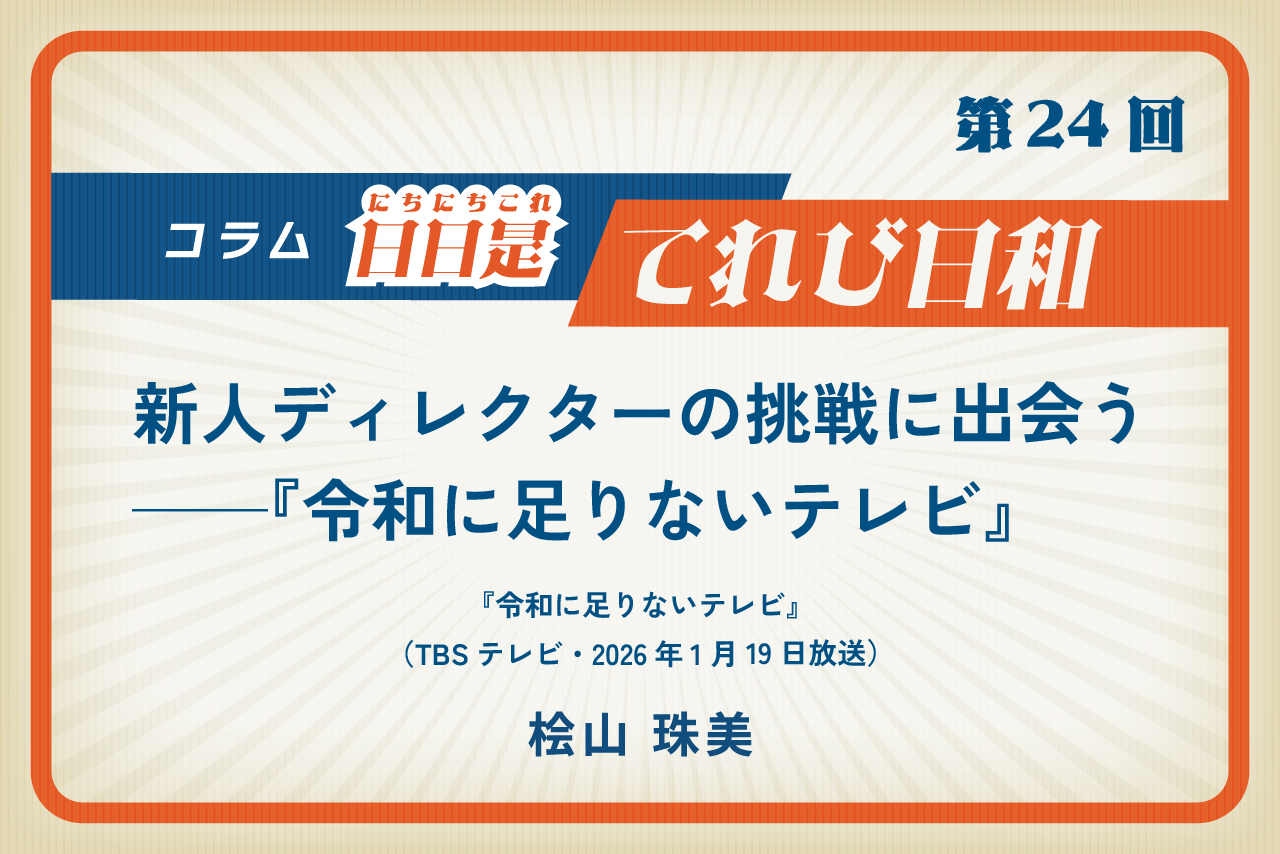放送文化基金賞
【第51回放送文化基金賞】ドキュメンタリー部門 選考記
「女性と子ども」という視点
桐野夏生
最優秀賞の『調査報道・新世紀 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』、奨励賞の『“法”の下の沈黙〜優生保護法の罪〜』、同じく奨励賞の『いのち つないで』の三作品は、いずれも「女性と子ども」という共通のテーマを持つ。今やジェンダーだけでなく、小児性犯罪・児童ポルノなどの子どもの性被害、そして生殖を巡るSRHR(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)、つまり個人の性と生殖に関する健康と権利へと、問題は包括的に広がりつつある。
子どもの盗撮動画や児童ポルノが、商品となって売り買いされている現実がある。『子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』は、その温床となっているアプリのプラットフォームの解明と告発の過程を追った優れたドキュメンタリーである。盗撮された動画や、子どもの自撮り性的画像がいったんネット空間に上げられれば、どこまでも拡散して、被害者の苦しみは想像を絶する。取材班は、民間のネットパトロール「ひいらぎネット」と、民間の調査機関Tansaと協力して盗撮動画をチェックし、アプリのプラットフォームを告発する。民間の調査機関との連携も、新しい調査報道の手法であると評価された。
優秀賞の『海獣のいる海』は、北の島でトドを撃つ漁師の生涯を追った作品である。淡々としたストイックな漁師の姿と、北の厳しい自然を美しく撮った映像が素晴らしい。奨励賞の『封じられた“第四の被曝”—なぜ夫は死んだのか—』は、埋もれていた事件を丹念な取材で掘り起こし、個人は国家に優先されない、という強烈なメッセージと、スクープ性が高く評価された。
なぜ変わらない!なぜ変えられない!
伊藤 守
高い水準の作品が多いなか、二作品のみの紹介となる。『子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』は独立系メディアTansaと市民ネットそしてNHKとの連携による調査報道の画期となる作品であった。多角的で粘り強い取材(市民ネットの地道な調査とTansaによる「闇」に切り込む圧倒的な取材力、そしてNHKの高度なデータ収集と編集力)で、この深刻な問題が野放し状態のまま、なぜ放置され続けているのかに迫る内容だ。たしかにこうした映像を拡散するコミュニティ運営者やアプリ管理者の法的規制の難しさやGAFAに代表される巨大なプラットホーム企業の利益優先など多くの問題が山積する。だがこの作品がもっとも注視するのは「子どもを守る意識が弱い」日本社会の姿、いまだに続く「子どもや女性を性的に搾取してよい」とするような環境を是正しない文化や制度の歪みである。『“法”の下の沈黙』は1948年国会で満場一致で可決され、その後50年代以降、難聴者やろう者や軽犯罪者や精神疾患患者に対しても同意なく不妊手術を施した「優生保護法」が、なぜ2024年の違憲判決に至るまで存続してきたのかを問う骨太の作品である。ここでも問われているのは、遺伝性や感染の因果性に疑問を呈する主張が存在したにもかかわらず、なぜこの法が存続してきたのかである。
今日まで続く障がい者への差別や排除、女性や子どもへの性的搾取と虐待、こうした問題を黙認させてしまう「悪しき根っこ」が綿々と社会と文化の内部に存続していることを自覚させてくれる熱量に溢れた作品であった。
ドキュメンタリーの訴求力
井上佳子
作品は力作揃いで「選ばない」理由を見つけ自分を納得させるのに苦労した。受賞した五作品はひときわ険しい高峰を征したという思いを強くしている。
選考でしばしば考えたのは番組の訴求力についてだ。同じテーマを扱っていても番組によって訴求力は異なる。何が違いを生むのか。ひとつはテーマを普遍化できているかどうかだろう。『“法”の下の沈黙』は、優生保護法の下、誰もが思考停止に陥り自分の役割を積極的に果たそうとしたことで被害が再生産を続けた事実を浮き彫りにした。組織の中で人間は自分の顔を失くす。自分もその歯車になるかもしれないという戦慄を観る者に抱かせる。
もう一点、訴求力において大切なのは、取材者と取材対象者との緊張関係ではないか。賛否が分かれるテーマの場合、取材対象者はSNSなどで攻撃される可能性がある。それでも顔を出して語るのは両者に信頼関係があるからだろう。『言えない心のうちがわを』では、女性たちがカメラの前で家族からの性被害のすさまじさを語った。『法医学者たちの告白』は、法医学に関わる医師たちが、都合よく利用され続ける法医学の現状を実名で告白した。
同性婚の法制化を目指す臼井崇来人氏は、妻と共に長年誹謗中傷に苦しんできた。彼の闘いの記録『望まれない性を生きて』は次のような問いかけで番組が終わる。「私たちの社会は彼らの勇気を受けとめられるだろうか」。番組の緊張感は、観る側の背筋も伸ばすのだ。
協働と表現の力で切り開くドキュメンタリーの新たな地平
金川雄策
今年も素晴らしい作品の数々に出会うことができました。メディア業界が激変するなか、制作者が視聴者のために知恵を絞り、人生を懸けて番組作りに取り組まれている姿勢が、ひしひしと伝わってきました。
最優秀賞を受賞した『調査報道・新世紀 File3 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』は、NHKがTansaなど外部団体と連携しながら調査報道に挑むという、これまでにない試みであり、大きな希望を感じさせるものでした。こうしたコラボレーションの成果によって、番組内ではスリリングな展開とともに、驚くべき事実が次々と明らかにされていきます。知見を持ち寄り、互いに協力し合う姿勢こそが、これからの放送文化を発展させる鍵であると強く感じさせられました。
優秀賞に選ばれた『海獣のいる海』は、動物の命を奪ってきた主人公が、自らの命とどう向き合うのかを、美しくこだわり抜かれた映像と音で描き出しました。俯瞰のドローン映像によって、小さな町に生きる人間とトドが、同じ大きさの粒のように並列され、隣合って生きる姿を視覚的に印象づける構成は見事でした。
これら2作品は、今後のドキュメンタリー番組が進むべき方向を示唆しているように思います。リソースや予算の違いから、NHKの作品がどうしても上位を占める傾向にはありますが、美しい映像と音で語る手法は、どの作り手にも開かれた表現で、もっと取り入れていけるのではないかと感じました。
未来が明るいとは思われない
関川夏央
『子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』(NHK)は衝撃だった。と同時に、ネットの先端技術が犯罪の温床となる事実にやりきれなさを体感した。
小児性愛、女子中高生の盗撮といった病気を抱えた人々が、SNSで集団化するとさらに病症は深まる。しかしもっとも不快なのは、カネのためにそのような犯罪行為にも目をつぶる巨大プラットフォーム企業だ。彼らは責任を問われるべきだし、罰せられるべきだと思う。NHKとNPOの協力というあらたなスタイルで調査・報告したこの作品は深刻な説得力を持つが、技術の進歩も革新も不快な未来をもたらすだけではないかと茫然たらざるを得ない。
『海獣のいる海 あるトド撃ちの生涯』(NHK札幌 / NHK旭川)は一人の漁師の最晩年をえがいた。
北海道礼文本島のすぐ北に、トドが越冬地とする小島がある。かつては数家族が住んでトドを冬場の食料としていたが、いまは無人だ。そこから本島に移り住んだ射撃の名人である主人公は、漁網を食い破るトドのみを「眠るごとく命をとりたい」と、揺れる船上からほとんど一発で仕留める。この八十八歳の名人が病死したのは夏祭りの直後であったが、そのことを視聴者は、映像ではなく、淡々とした島内放送で知らされるのである。
最果てに生きた人の人生が、作り手の周到な観察眼と、むしろ言葉の少なさがもたらす明瞭な輪郭で表現されたこの作品は、まぎれもなく傑作と思う。
「余韻」と共に「共感」を生むドキュメンタリーの数々
林 典子
現代社会における若者の孤立、アイヌや在日コリアンの人々への民族差別の源流と未来への課題、戦後80年を迎え新しい手法で「戦争の記憶」を伝える番組の数々、可視化が難しい性暴力を扱った作品など、受賞作以外にも多くの秀作に出会えた。他者の感情を繊細に紡ぎ出す優れた映像作品は、観ている者の思考を刺激し、新たな視点と共感を生み、社会に対する行動を促すことにも繋がる、というドキュメンタリーの潜在的な可能性を改めて実感した選考だった。
最優秀賞の『調査報道・新世紀 File3 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』は、児童ポルノが取引されるビジネスの実態や、SNS上のコミュニティーが悪質な性犯罪を駆り立て、やがては責任の所在が見えなくなっていく複雑な構図を、独立メディアTansaとの丹念な共同取材により浮き彫りにし、強い衝撃と共に現代社会に鋭い問題提起を投げかけている。『海獣のいる海 あるトド撃ちの生涯』は、漁師俵静夫さんが厳しくも美しい自然との関わりの中で、向き合ってきた「命の重さ、儚さ」という普遍的なテーマを圧倒的な映像美と、静寂の中で掬い取られる音などを丁寧に紡いで表現し、見る者に豊かな余韻を残す素晴らしい作品だった。『いのち つないで』は内密出産の当事者の女性の切実な声が、今も苦しみに直面する女性たちの痛みを想像させ、その先にある乳児遺棄問題や支援を拒む行政の存在など差し迫った現状に対して社会がとるべき対応を問うている。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る