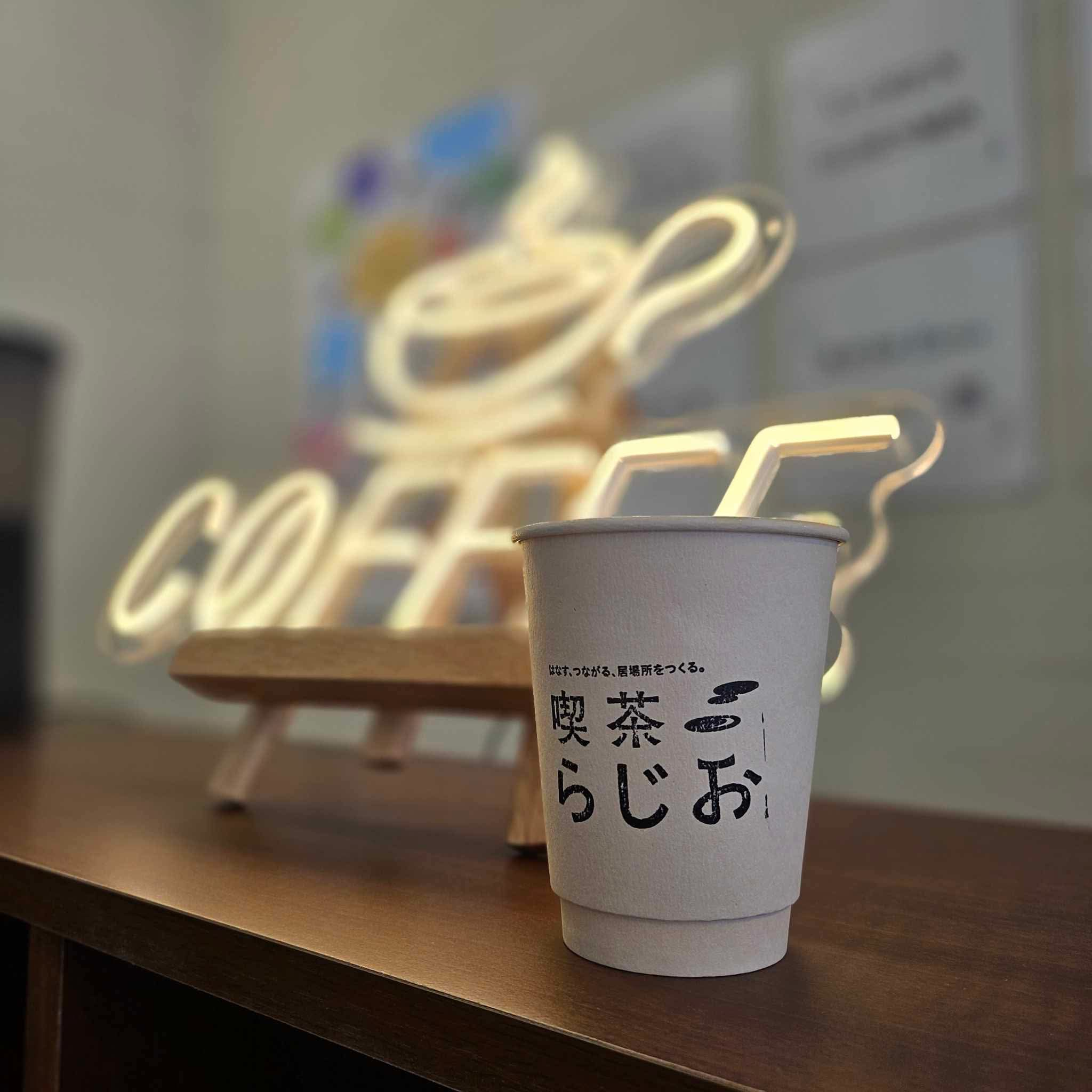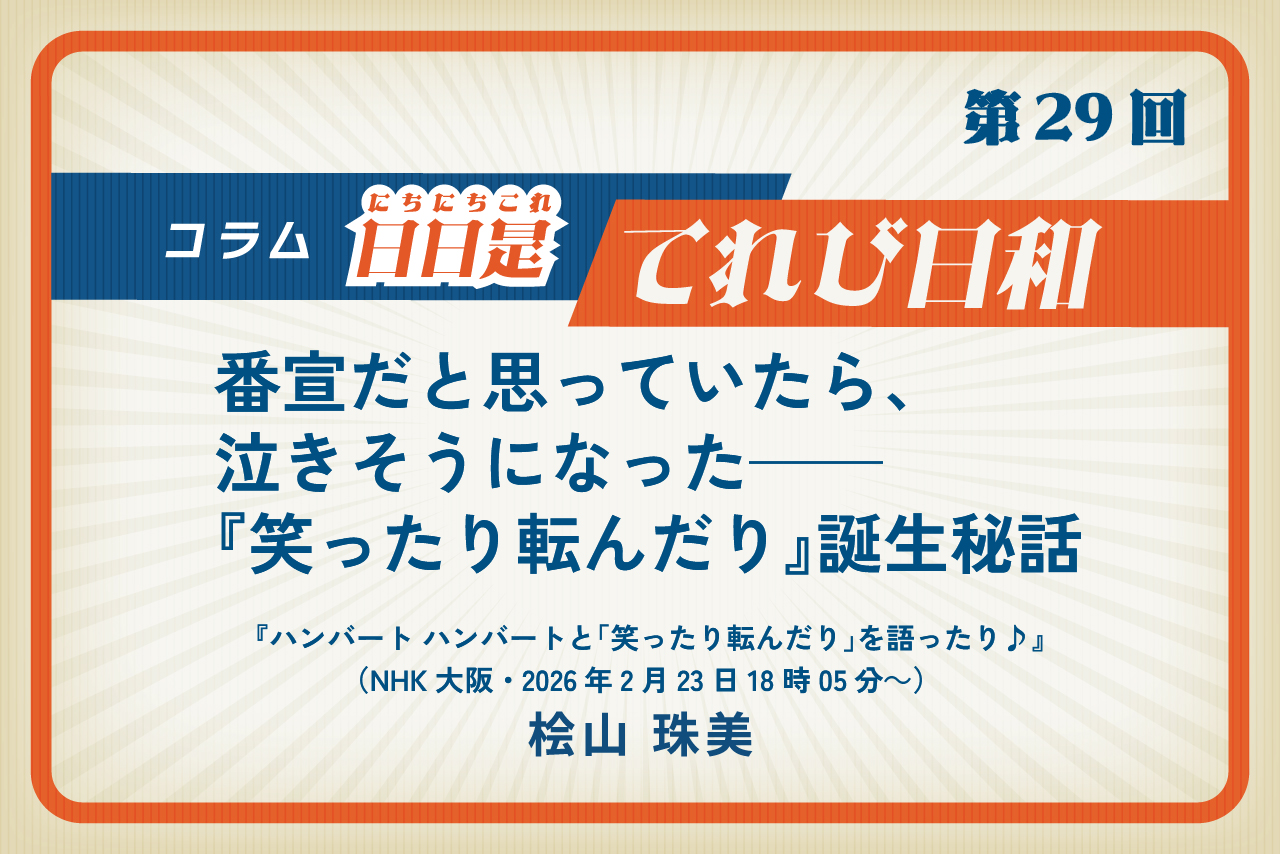HBF CROSS
マイクのあるカフェ〈喫茶らじお〉で 【伊藤守】
2025年6月18日、新潟県阿賀町津川で第6回となる〈喫茶らじお〉が開催されました。放送文化基金ではこの〈喫茶らじお〉のプロジェクトに助成し、プロジェクトを立ち上げから応援してきました。今回は審査を行った伊藤守委員長が現地に行って取材しました。

新潟も梅雨に入った6月中旬、小さな街の中心部にある住吉神社で“9時開店”と印刷されたパンフレットを手に、「喫茶らじお」を訪れた。会場に着く前は、てっきり神社の中でやるものと予想していた。ところが、なんと本殿の前の境内にテントを張って、昨夜から降り続く強い雨のなかでの開店である。開店と同時に年配の男性と女性が木箱の椅子に腰かけると、マスターの伊勢みずほさんは明るく「いらっしゃいませ~」と声をかけてコーヒーをふるまった。2人はテーブルに置かれたマイクを前に自然に話し始める。第6回「喫茶らじお」のスタートである。
喫茶らじおのスタート
読者はここまで読んで、どんな喫茶なの?と疑問を持たれたのではないだろうか。「喫茶らじお」がスタートした経緯をスタッフの高橋紘子さんから聞いた。新潟放送が地域放送局から地域メディア、地域の課題解決型企業に成長を遂げる中で、エリアプロデュース部という新部署が立ち上がった。地域の課題について議論を重ねるなかで、思いをともにする新潟博報堂、DERTAの3社が集まり、「BSN×DERTA×新潟博報堂 地域課題解決プロジェクト」が始動したという。目的は、その地域の⼈、関わる⼈の内から湧き上がる「他にない何か」を見つけて、持続可能な取り組みを行うこと。ゴールは地域の人の笑顔と幸せである。つまりトップダウンではなく、あくまでボトムアップによるコミュニティの再生・維持ということだ。ところで、「喫茶らじお」とは素敵なネーミングだと思っていたが、彼女の話を聞いて、現地を訪れ、そのネーミングの理由がわかった。

津川町は昔から会津と越後を結ぶ阿賀野川と街道で物資を運ぶ交通の要所として栄え、1960年には9102人の人口を抱えていた。だが近隣町村と合併する前の2004年には5228人に減少し、2020年には3441人となった。現在65歳以上の人が占める割合は5割を超える。こうした人口減少と高齢化は、全国の市町村でも同じ状況にあるが、津川地区のような山間部ではなおさらである。若者が少なく、この街の県道14号線沿いの商店街には有名なパン屋さんはあるが、喫茶店はない。つまり、町の人たちが日常的に集い、自由に話せる場所や機会がない。
高橋さんはそこに目を付けた。テーブルにマイクを置き、町の人たちが気軽に出入りして自由に話したいことを話せる居場所をつくる。収録した声をポッドキャストで配信し、津川地区の人たちはもとより、県内の、あるいは県外の多くの人にも聞いてもらうことで、地域の生活の良さや豊かさを、手触り感覚で伝えようと考えた。街の人たちのつながりも生まれるのではと期待して、遊休施設を利用して具体化したのが「喫茶らじお」である。
語り合いの場
さて、前置きが長くなったが、最初にマイクの前に座った2人の話しに戻ろう。年配の男性は長年勤められた国鉄を退職後、新潟のさまざまなイベントに参加してきた。今回も、勤務していたときに何度も訪れた津川で「喫茶らじお」があると聞き、新潟市内からやって来たという。男性は県内各地のことや、山菜取り、釣りにも詳しく、あっという間に話が盛り上がった。女性の方はポッドキャストでこの番組を知って来られたという。
開店から11時頃まで雨が続き、どのくらい人が来るのかと気になったが、心配は無用だった。20キロほど離れた五泉市から結婚を機に津川に移り住んだという近所の女性や、ずっと津川で暮らしてきた女性、津川の観光ガイドを務めている方、農家の方など、地元の人々が次々と訪れた。お孫さんを連れた家族の姿もあり、木箱の椅子が足りず、数十分も立ったまま話を聞く人もいるほどだった。

マスターの伊勢さん(実は新潟放送のアナウンサーを長年務め、ファンも多い)が、「津川の良いところは?」と話を振ると、先の女性が「雪解けの春の景色が一番」と答えれば、男性は「なんと言っても麒麟山をバックにした阿賀野川の風景」だと言う。何十年も地元で暮らし続けてきたからこその実感がこもった発言だ。
明治の中期に建てられた住吉神社の近くの家で暮らす男性の言葉も印象に残った。ちょうどこの日は先に述べたように前日から雨が降り続け、切り立った幾つもの山並みの麓や阿賀野川には霧が立ち込めて、幻想的な雰囲気が漂っていたのだが、この男性は悩みごとなど物事を考えこんでいるとき、この深い霧に包まれると「気持ちがすっきり晴れて、悩みなどすっと消えていく」と語ってくれた。深い霧に触れると人の心に微妙な変化が生まれるのだろう。綿々と続く自然と人とのかかわりあいの中に神秘的な何かを感じさせてくれる言葉だった。
集う人々の物語
高橋さんから話を聞くと、毎回、印象に残る話に出会ったという。第1回の御神楽温泉の食事館では、1回目ながら15名ほどが参加。なかにはビールを持ち込んだ方もいて、いまは食することが少ない郷土料理の話も出て盛り上がった。2月に予定していた第2回は大雪で中止となり、3月の阿賀の里の道の駅で開かれた第3回は10人ほどの参加。阿賀野川の船運を担う船長は、「東京から津川に移住し27年。最初は馴染めなかったが、街の飲み会に誘われ、いまではすっかり地元に馴染んだ」という。商店街の一角にあるフリースペース・カネクを会場にした第4回では、80歳のおばあちゃんが参加、「津川は宝の山」と話し始めた。その理由は「ここではトリュフがたくさん採れるから」。80歳女性のトリュフハンターである。第5回は旧鹿瀬小学校で開催。すでに廃校となった校舎で、卒業生を含めて約20名が参加、ここでも昔の思い出話で盛り上がり、全員で校歌を合唱する楽しい会となった。

この日来られた方々からも窺われるように、「喫茶らじお」の参加者は、地元の人たち、旅行で津川に来て偶然立ち寄った人たち、そしてラジオのリスナーやテレビの紹介番組、新聞記事でこの企画を知って来られた人たちである。2回目という方もいたが、ほとんどがはじめてテーブルを囲んだ一期一会の出会いだった。趣味やこれまでの人生、新潟や津川の郷土の話を自然体で語り、互いに話のキャッチボールを楽しみながら、笑顔で別れていく。地元の人にとっては他の地域から来た人の話が刺激となり、地元のよさを再発見できる機会にもなっていた。さまざまな人たちが交錯するなかで生まれる会話。そこから育まれるボトムアップの地域再生である。
メディアの古くて新しい姿
この取り組みに筆者が関心を抱いたのは、NHKのテレビで放送されている『病院ラジオ』と「喫茶らじお」との間に共通性を感じたからだ。ご存じの方も多いだろう。サンドイッチマンが司会を務め、入院中の患者やその家族が、病気のことや医師や看護師とのかかわりなど、入院生活上の喜怒哀楽を、人肌に触れるような静かな語り口で話す。ラジオから流れる声を、病室にいる他の患者や家族が耳を澄まして聞く。話す人も聞く人も、そして視聴者も「ほんのりと、共感し合い、互いに思いやる心が呼び起こされる」番組である。そこにはラジオから流れる声だからこそ作り出せる独自の空間がある。
「喫茶らじお」も、市井の人びとの日常のなにげない話ではあるけれど、含蓄のある会話が交錯し、飛び交う独自の色合いを帯びた声の空間を作り出している。
ラジオやテレビといったマスメディアが厳しい環境に直面し、オールドメディアと言われる中、ニュースや娯楽の提供だけでなく、「何かと何かを媒介(media/medium)する」というメディアの本来の意味に立ち戻って考えるなら、「喫茶らじお」のように、地域に根付いたかたちで、住民と行政との間をつなぎ、そして企業の参加も呼び掛けて、コミュニティを支える役割をメディアが担うこともできるはずだ。「喫茶らじお」はそうしたメディアの古くて新しい姿を示唆しているのではないだろうか。
今回で「喫茶らじお」はひとまず終了となるという。とても残念だ。年に2回か3回の開催でも良いから、行政と企業も巻き込んで、ぜひ再開に向けて走り出してほしい。
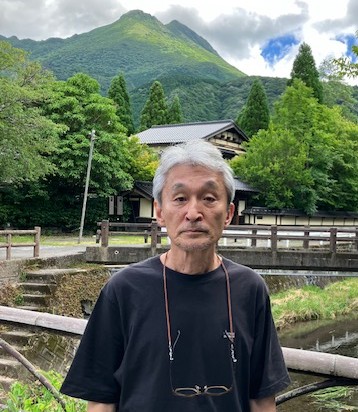
伊藤守 プロフィール
早稲田大学名誉教授。社会学、メディア文化研究が専門。趣味は写真と旅。
著書
『フェリックス・ガタリの思想:生の内在性の哲学』(青土社、2024年)
『メディア論の冒険者たち』(東京大学出版会、2023年)
『コミュニケーション資本主義と<コモン>の探求』(東京大学出版会、2019年など)
喫茶らじお実行委員・高橋紘子さんの寄稿はこちらから▼
「喫茶らじお」は各種Podcastで配信中です!
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──寄稿、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの面白さをお届けします。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る