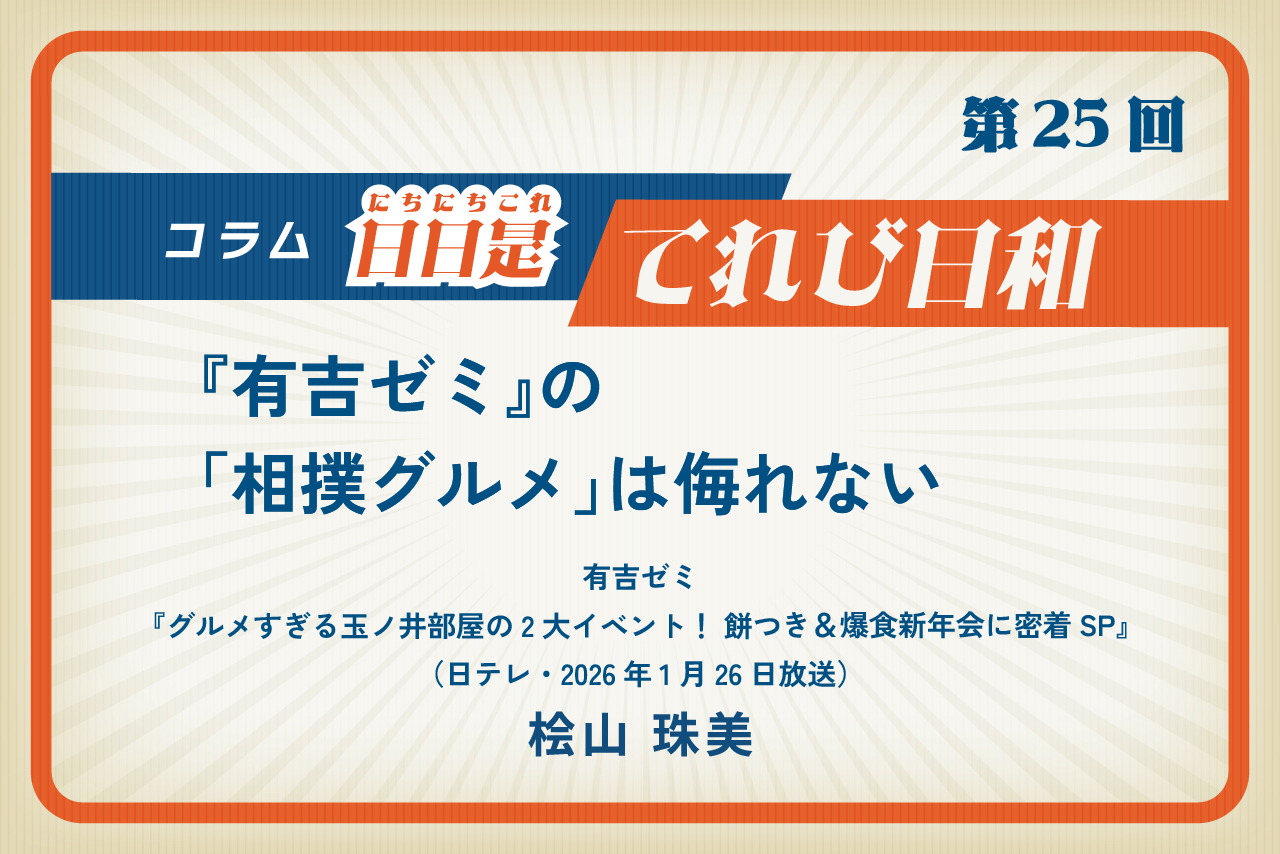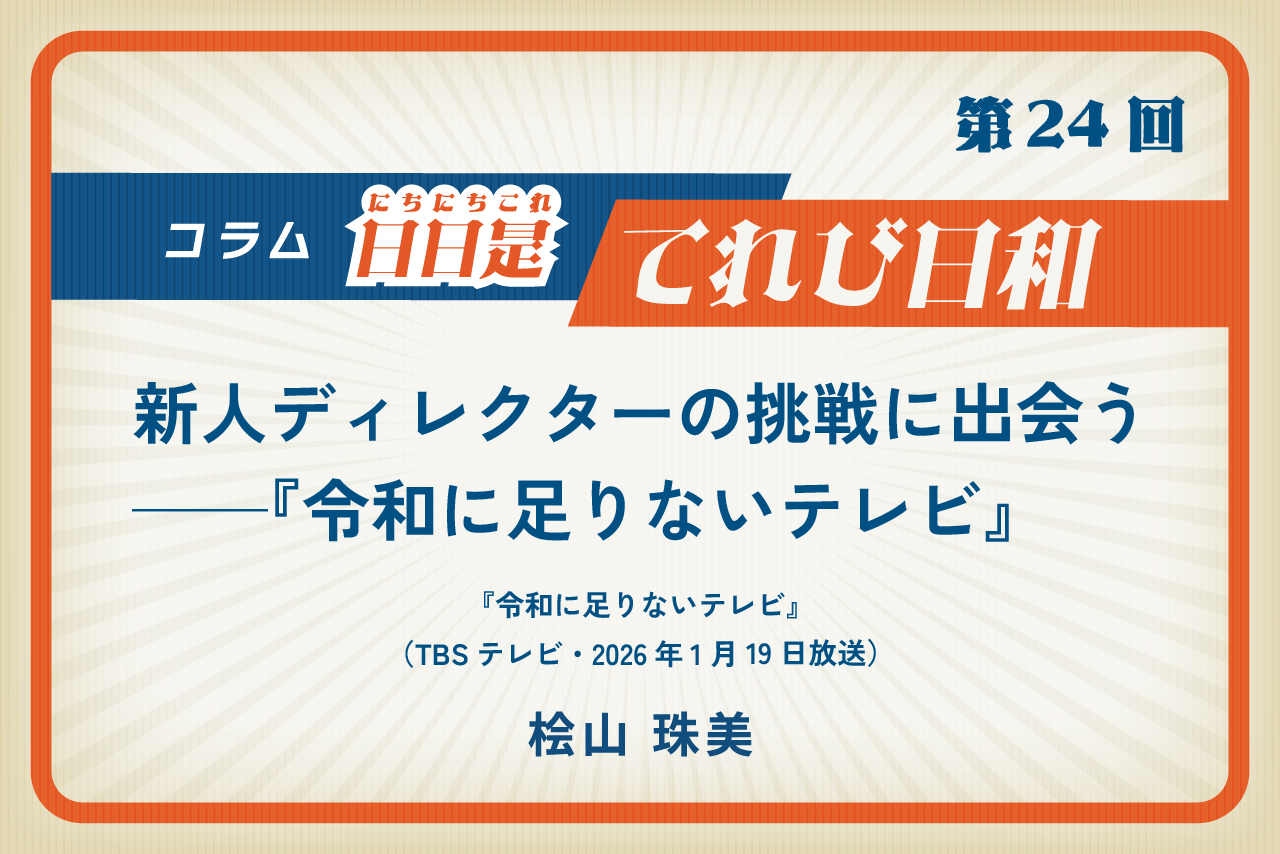助成
助成がつなぐ、放送の未来へ
成果報告会2025/助成金贈呈式
放送文化基金の2024年度の助成対象が決まり、2025年3月7日、ホテルルポール麹町(東京都千代田区)にて成果報告会2025と2024年度助成金贈呈式を開催しました。
当日は研究者の方、放送現場に携わる方、若手の方からベテランの方、文系、理系問わず様々な分野で放送・メディアに関わる方々にご参加いただきました。今回は、その様子をレポートします。
HBF編集部 根橋智美


第1部 成果報告会
成果報告会では、技術開発部門と人文社会部門から、1年の助成期間を経て評価が高かった方々の成果の報告がありました。2024年度に新設したイベント事業部門からは途中経過が報告されました。
最初に、技術開発部門から福井工業高等専門学校電気電子工学科教授の濱住啓之さんが発表を行いました。研究には高等専門学校の生徒さんも参加していることや高等専門学校についてのお話があり、マイクロ波帯FPU用SC-FDE無線伝送方式の開発についてはデータを示しながら成果をご説明いただきました。
人文社会部門からは、京都産業大学国際関係学部 准教授 千葉 悠志さんが、カタールに拠点を置く放送局アルジャジーラに注目し、国際放送局として発展を遂げた背景を分析した結果が共有されました。
休憩をはさんで、イベント事業部門から2件の報告がありました。
「北海道ドキュメンタリーワークショップ」実行委員会委員長の山﨑 裕侍さんに北海道ドキュメンタリーワークショップを立ち上げた経緯を中心に、参加者の声などが紹介され、手ごたえが語られました。
喫茶らじお実行委員会ディレクターの高橋紘子さんからは、自身の取材経験から過疎地域の人たちにも自分たちの住む町に魅力を感じてもらえるにはどうしたらよいだろう?と喫茶らじおを思いついた経緯と開催の様子をお話しいただき、実際の音声を交えて途中経過が紹介されました。
成果報告会には約60名が参加し、質疑応答の時間には活発な意見交換が行われました。
▶︎成果報告の詳細はこちらから
【技術開発】濱住啓之氏「マイクロ波帯FPU用SC-FDE無線伝送方式」
【人文社会】千葉悠志氏「国際放送とコスモポリタンな文化・都市―カタールの事例から」
【イベント事業】山﨑裕侍氏「北海道ドキュメンタリーワークショップが生まれた理由、必要な理由」
【イベント事業】高橋紘子氏「喫茶らじお~おしゃべりがつなぐ、まちとひと~」
第2部 助成金贈呈式
続いて行われた贈呈式では、各部門の審査委員長が審査の概要と所感を述べたのち、濱田理事長から採択された41件の代表者一人ひとりに目録が手渡されました。
今回の助成では、技術開発部門8件、人文社会部門15件、イベント事業部門18件が採択され、総額は6,905万円。採択されたプロジェクトは、これから1年間にわたって研究・開発・事業等を行い、成果報告へとつなげていきます。
また、各部門を代表して1名ずつが今後の展望について語りました。
〇技術開発部門代表・片岡龍峰さん(国立極地研究所)
「オーロラ計測システムの小型化に取り組んでおり、将来的には火星探査機に搭載し、火星でのオーロラ計測を実現したい。」
〇人文社会部門代表・Tse Yu-Keiさん(国際基督教大学)
「NHKとBBCの比較を通じて、ネット配信時代の公共放送の役割や理念、NHKの課題を考察し、新たな視点を提示したい。」
〇イベント事業部門代表・森内真人さん(地方の映像クリエーター育成実行委員会・青森放送)
「地方局の制作者と青森の高校生が交流し、映像制作を学ぶワークショップを開催し、現役の制作者のレベル向上とともに、高校生たちに地方から映像発信をする魅力を伝えたい。」
いずれもプロジェクトに対する意欲・目標が語られ、1年後にどんな成果が出てくるのか期待が高まりました。
また、申請の多かったテーマや注目すべき傾向を読み解くコーナーが設けられ、助成対象者とともに紹介されました。2024年度の傾向としては若手研究者、特に博士後期課程の方々の採択が目立ちました。さらに、放送開始100年の節目を反映し、ラジオ放送や音声配信に関するテーマも多く寄せられました。加えて、ジェンダー課題の解消を目指す取り組みや、災害報道・防災に関するプロジェクトなど、時代の関心を反映した多様なテーマが採択されました。
第3部 懇親会
懇親会では、部門や所属を越えて、審査委員も交えた活発な意見交換が行われ、閉会の時間まで多くの参加者が交流を深めました。この場をきっかけに、助成プロジェクト同士の連携が生まれたり、新たなプロジェクトの構想が進展したりと、人的ネットワークの広がりが実際の成果へと結びつく機会となっています。

一年に一度、助成対象者が一堂に会するこの日。この日をきっかけに放送に携わる多くの方にご参加いただき、 ここでの交流が今後の研究や実践を前進させるきっかけとなること、またそれらの取り組みを支援できることを願っております。
放送文化基金の助成は、放送業界をより良くしていきたいと考える方どなたでも門戸を開いています。新しい取り組みのアイデアや研究対象を見つけた方はぜひ申請ください。一緒に放送文化・メディア文化の芽を育てられる日を心待ちにしています。
関連記事を見る
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/xb894950/hbf.or.jp/public_html/wp-content/themes/theme/single-magazine.php on line 86
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る