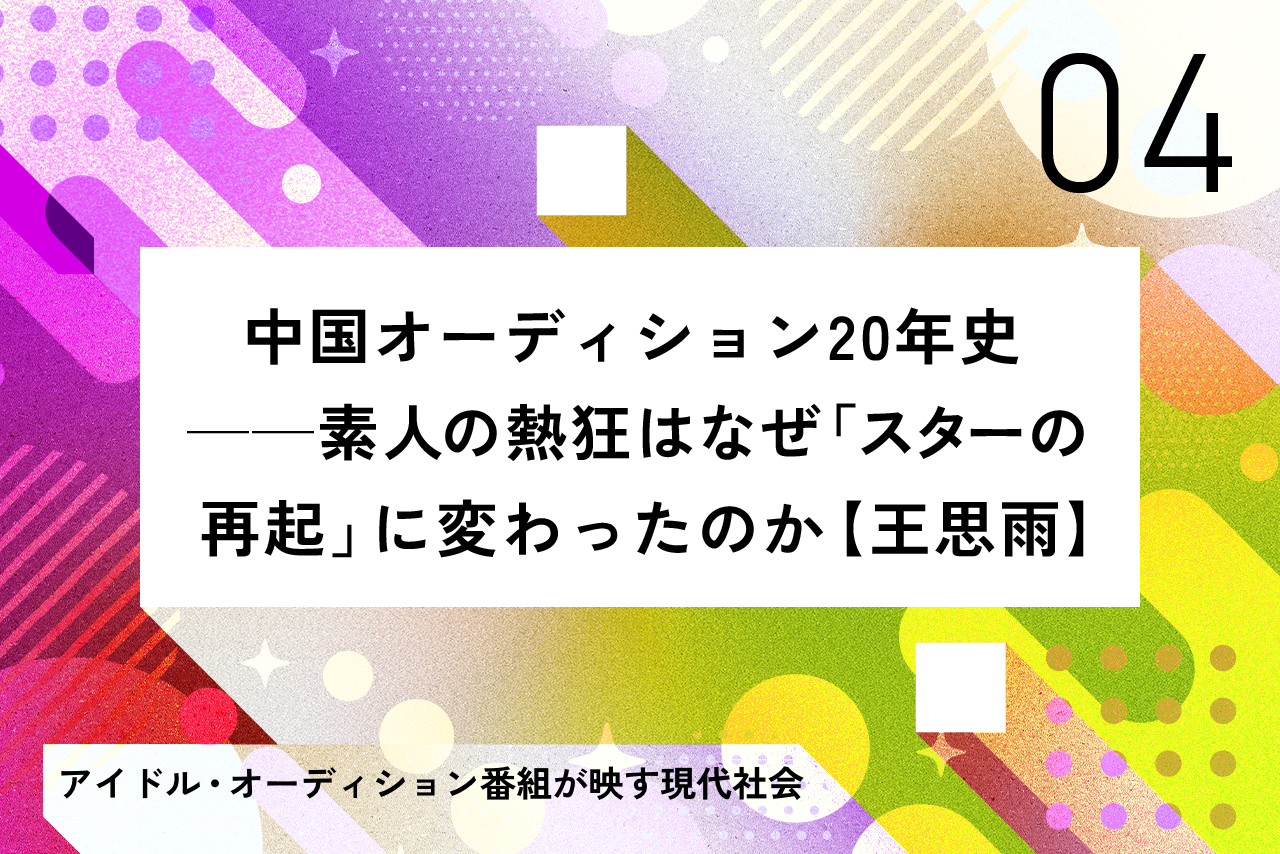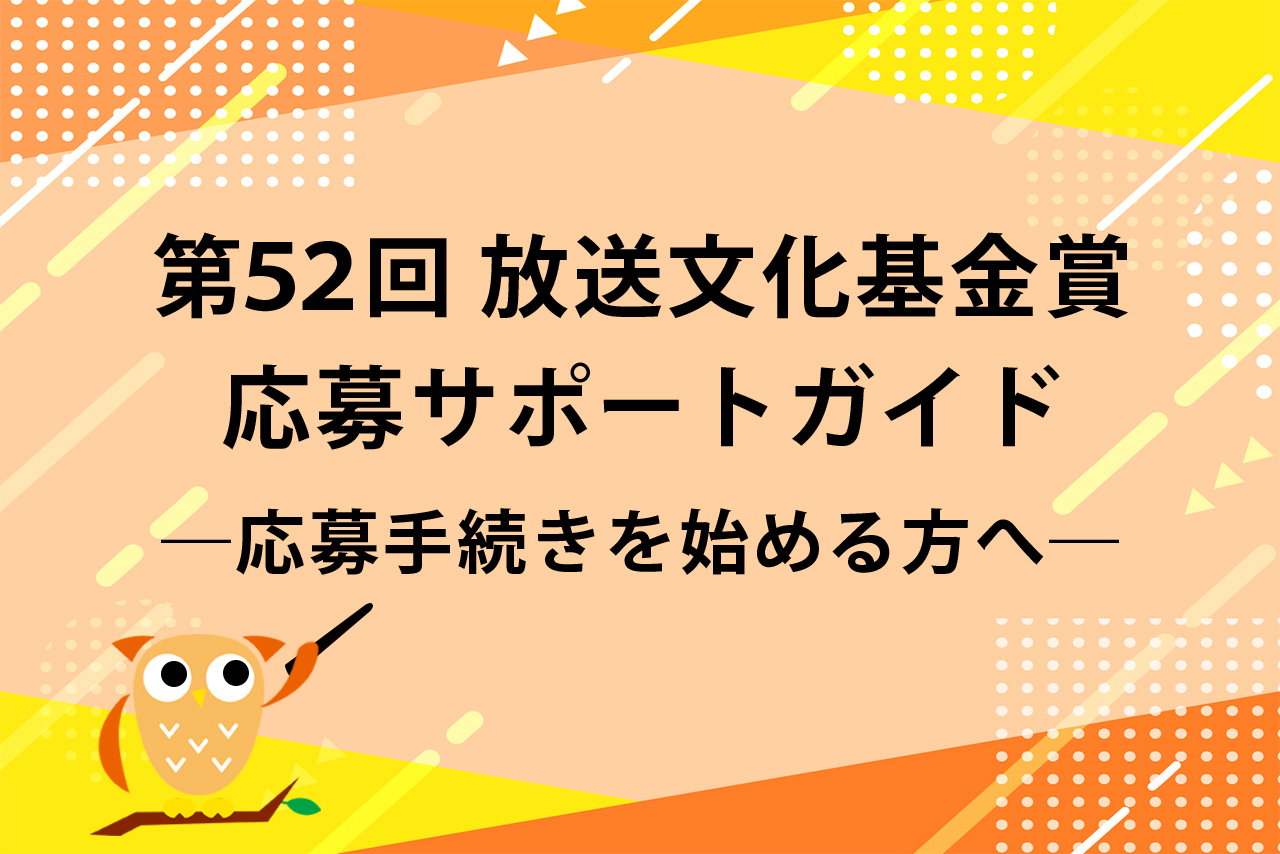HBF CROSS
“言葉のスナイパー”田代裕さんが語るポスプロの現場――北海道ドキュメンタリーワークショップ第6回
未来へつなぐ灯 連載第7回
メディアプロデューサー 山谷博

2025年6月29日、6回目となる北海道ドキュメンタリーワークショップが札幌のSTVホールで開催された。今回のゲストは『情熱大陸』や『ザ・ノンフィクション』の構成とナレーションを手がける構成作家の田代裕さん。ドキュメンタリーの取材後の作業である、いわゆる「ポスプロ」をテーマに選んだ。会場には放送関係者を中心に100人近い人が集まった。
実は北海道のローカルでの制作現場で「作家」に仕事をお願いすることはそう多くない。ドキュメンタリー番組の多くは構成も、そしてナレーションの原稿もディレクターが手掛けることが多いからだ。ただ、私自身はこう考えている。「構成」は視聴者に向けて番組の「体調」を整える作業であり、MAでナレーションや音効、BGMを入れることで、番組は「命」が吹き込まれると。
だからこそ、構成作家の中でも、とりわけナレーションを書くことにおいて、「言葉のスナイパー」でもある(これは私が勝手に田代さんをそう呼んでいるのだが)田代裕さんに力を貸してもらうことが多く、そんなつながりもあって今回のドキュメンタリーワークショップにお呼びした。
ディレクターと構成作家のファーストアプローチ

まず『情熱大陸』では、およそ24分ほどの本編のナレーションを、ディレクターによる仮のナレーションをベースにして、田代さんがまずは10時間ほどで書きあげるという。ディレクターとの徹底したやり取りを経て、わかりにくい部分も含めて構成をブラッシュアップし、「命」を吹き込む準備を進める。この制作とのキャッチボールが「田代流」の一つだ。
ここでほしいのは制作側の「解釈」だという。すなわち「意図」とも言うべきか。「意図」のない番組は、それがドキュメンタリーであれ、バラエティであれ、「命」の入りようがない。
また田代さんは「かしこまった言葉をいくら聞いても面白くない」とも言う。確かに「ポロっと出た言葉」を大事にすることは、実はドキュメンタリー制作の鍵である。
さらに「どうしたら簡潔に物事が伝わるか」ということを考えるという田代さん。やはり「スナイパー」だ。「短い言葉」で視聴者の琴線を仕留めるのだ。そのためにどのように言葉を捻り出していくか、という過程についても赤裸々にしてくれた。
限られた秒数の中で「何が正しく、どの言葉が琴線にふれるのか」をあぶり出すこと、それが構成作家という、ディレクター以外のポジション、別の道からの番組へのアプローチなのだ。このもうひと手間の作業、この道筋が番組自体の幅を広げていく。
構成作家ならではのアプローチ

構成作家の立場から、ディレクターとはまた違うアプローチで、番組の「テーマ」をどう立ち上げるかという戦いがある。田代さんは「映像の中に埋もれていたテーマを強く押し出す」というのが構成作家の仕事であるという。
そして「ナレーションは文章ではない」ともいう。ここが作家らしいというべきか、「耳に届く時のリズム感を大事にする」というのだ。
具体例はこうだ。語尾を「る」なのか、「か」なのか、「た」なのか意図的に変えるそうだ。「くだらないかもしれない」と笑う田代さんだが、「番組を見ている人に、気持ちよく内容を蓄積させたい」という、作家ならではの視点と言える。
さらにこんな具体例も挙げる。「そして」「そんななか」「その」「やってきたのは」「ただ」と言う言葉には気を付けると。これはディレクターとして自分がナレーションを書いても「あるある」である。確かに使いがちな言葉なのだ。特に「その」はなくても大丈夫なことが多いのでやってみてほしい、と言う。「そして」は番組の中で1回しか使わないそうだ。それは、「そして」を使う重要な場面は60分に1回しかないからだと。なるほど。
さらに「このあとは」というのはやめましょう、とも。「そんなことはわかっているから」。田代さんの言葉に対するストイックさと、哲学が垣間見えて面白い。「この日」と「その日」の違いとかにも触れる。確かに違う。意味合いも意図も何もかも違うのだ。
ナレーターと構成作家のスタンスは
第2部は具体的に、ディレクターが登壇し、田代さんが構成作家として関わった作品をもとに、制作過程を掘り下げた。

この中では、ナレーターの立ち位置について議論になった。レポーターにもなり得るし、「旅人」でもあれば、視聴者とともに発見のできる立場にもなりえるからだ。だからこそ「一人称」にすることの意味、客観と主観など、ナレーションの中に含まれる様々な側面をこの第2部ではあぶり出す形となった。
登壇したSTVの水谷プロデューサーは、10年ほど前にディレクターとして田代さんに構成作家に入ってもらってドキュメンタリーを制作したが、その時に教えてもらったことの一つが臨場感であり、リアル感だという。「ドキュメンタリーは事前に収録しているけど、その時にあるリアル感を大事にしなさいと教えられ、今もそれをインタビューの際にも常に気にかけている」と。極めて大事なことが議論の中で浮かび上がったのだ。
また、ディレクター陣との議論の中で、田代さんは、ディレクターとの雑談も大事だと語った。ディレクターが取材現場で感じたものを構成やナレーションにしっかりと繋げたいからだ。だからこそコロナの時のリモートでの打ち合わせは厳しかったという。それはそうだ。
「ディレクターが最初の視聴者であり、構成作家はその後、視聴者のために書き、ディレクターのために書き、最後に自分のために書いている」というスタンスもまた、心強いとしか言いようがない。
部活を扱ったドキュメンタリー制作で田代さんに構成をお願いした畑野ディレクターは、ナレーションを通して感じる「普遍的なメッセージを作り手の主観に戻させるようなスキル」について尋ねた。田代さんの答えは明快だ。「それはテクニックではなく、みなさん見てくださいね、という気持ちがそういう言葉になる」。これこそディレクターが仕上げの段階でほしいものの一つであろう。
もう一つ、視点としておもしろかった話がある。「背中」を撮っておくとナレーション的にはいろいろなことが言えるのだそうだ。「最近はなかなか背中を撮ってくれない」と嘆く田代さん。意図的ではなく、いい背中を撮ってほしいそうだ。いい加減な背中を撮ってもダメで、できれば三脚でゆっくり撮るとか、こだわってほしいという。
「背中が好きなんですよ」というのには笑ったが、制作の一つの大きなヒントのような気がしてならない。
こうしてみると、田代さんは、構成作家であり、ナレーションの作家でもあるが、その独自の「ディレクターとしての目線」が入り込むことが「田代流」でもある。
ドキュメンタリー制作への別の「角度」はまだまだある
ナレーションに限らず、もっと音楽・音効のことなどにもワークショップとしては触れたかったが、そこまで辿り着けなかったのが残念だ。今度またこのような機会があれば、そこまで踏み込んでみたい。
なかなか聞けない貴重な機会だったので、これもまたヒントか、と感じたものを羅列してみる。
*「出来事はシーンになかなかならないんですよ」
*「シーンというのは仕掛けている人に何か腑に落ちることがおきること」
*「漫然とその場面をカメラを回しているだけでは番組にはならない」
*「撮れなくても、考えることこそが大事。それが次につながるから」
あらためて、ドキュメンタリーの制作には様々なアプローチがあることを実感するワークショップだった。取材のきっかけや取材対象との向き合いなど、制作の前半の作業はもちろん最重要である。だが、その後のいわゆるポスプロも、取材を番組という形に昇華するための重要なアプローチであることは間違いない。そのタイミングでこそ、多くの「頭脳」、言い方を変えれば多くの「角度」が必要であり、その一つの方法論として構成作家の役割は大きいと思っている。
会場のディレクターからの質問の中で「何気ないやりとり、というのはどういうものなのか」というのがあった。ダイレクトな質問だったが、田代さんは「その人の手触り、その人の個性がちょっとみえるような、そのようなもの」と迷いなく答えていた。これはおそらくドキュメンタリーという番組と視聴者の距離を縮める、まさに田代流の根源であると思う。

最後に田代さんが会場のディレクターに言ったのは、
「ディレクターは素材をちゃんと全部しっかりとみて、しっかりと把握すること」
そんなことは当たり前だよね、と思ったが、もしかすると、それもあえて言わなければならないという時代になってしまったのか…と、ちょっと不安を覚えた6回目のワークショップでした。
最後に、6回にわたる北海道ドキュメンタリーワークショップで蒔いた種がこれから、若い世代のディレクターやクリエイターたちの中で健やかに伸びることを期待したい。6回で全てを網羅できたわけではないが、ある一定のインスピレーションやスキルの源みたいなものを感じ取れていたら大きな成果だと思う。
メディアが作るものに正解はないのだ。正解がないからこそ色々なクリエイトがあっていい。これまでのドキュメンタリーがこうだったからこうしよう、ではなく、これはこれ、そして自分は自分、という意気込みみたいなものがこのワークショップで芽生えることこそ、実は本望だったりすると思う。今度は実戦で生かしていってほしい。
プロフィール
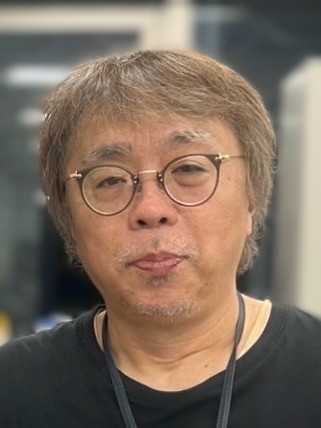
山谷博(やまやひろし)
メディアプロデューサー
1965年生まれ、札幌市出身
1990年に札幌テレビ放送(STV)入社
ラジオ局(現STVラジオ)、報道記者・報道デスク、日本テレビ出向を経て2011年からはテレビ制作で番組プロデューサーとしてバラエティ番組やドキュメンタリー番組をてがける。2025年にSTVを退職して、現在は独立してプロデューサー、ディレクターとして活動。
「北海道ドキュメンタリーワークショップ」は、放送文化基金の助成を受けて2024年9月から各局が持ち回りで計6回開催されました。多彩なゲスト講師を招き、放送局の垣根を越えて切磋琢磨し交流を深めることを目的とし、局員に限らず制作会社など放送に携わる人なら誰でも参加できる場です。本連載は、その全6回を月に一度のペースでレポートとしてお届けし、質疑応答のハイライトやゲスト講師が伝えたかったメッセージ・哲学を掘り下げながら、その熱気をお伝えしてきました。今回が最終回。ワークショップは引き続き助成を受け、新しい形で展開しています。
👉この連載の他の記事を読む
🔗【連載第1回】斉加尚代さん「会社のためではなく社会のために」
🔗【連載第2回】森達也さん「SNS時代の今、映画『A』を振り返る」
🔗【連載第3回】“想定外”が導いたNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』
🔗【連載第4回】元メンバーのインタビューが全てを変えた――『安全地帯・零ZERO-旭川の奇跡-』
🔗【連載第5回】「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く
🔗【連載第6回】「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ
👉ワークショップの全体の概要や準備の経緯についての記事を読む
🔗 北海道で高まるドキュメンタリー熱(成果報告会2025)
“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、事務局レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る