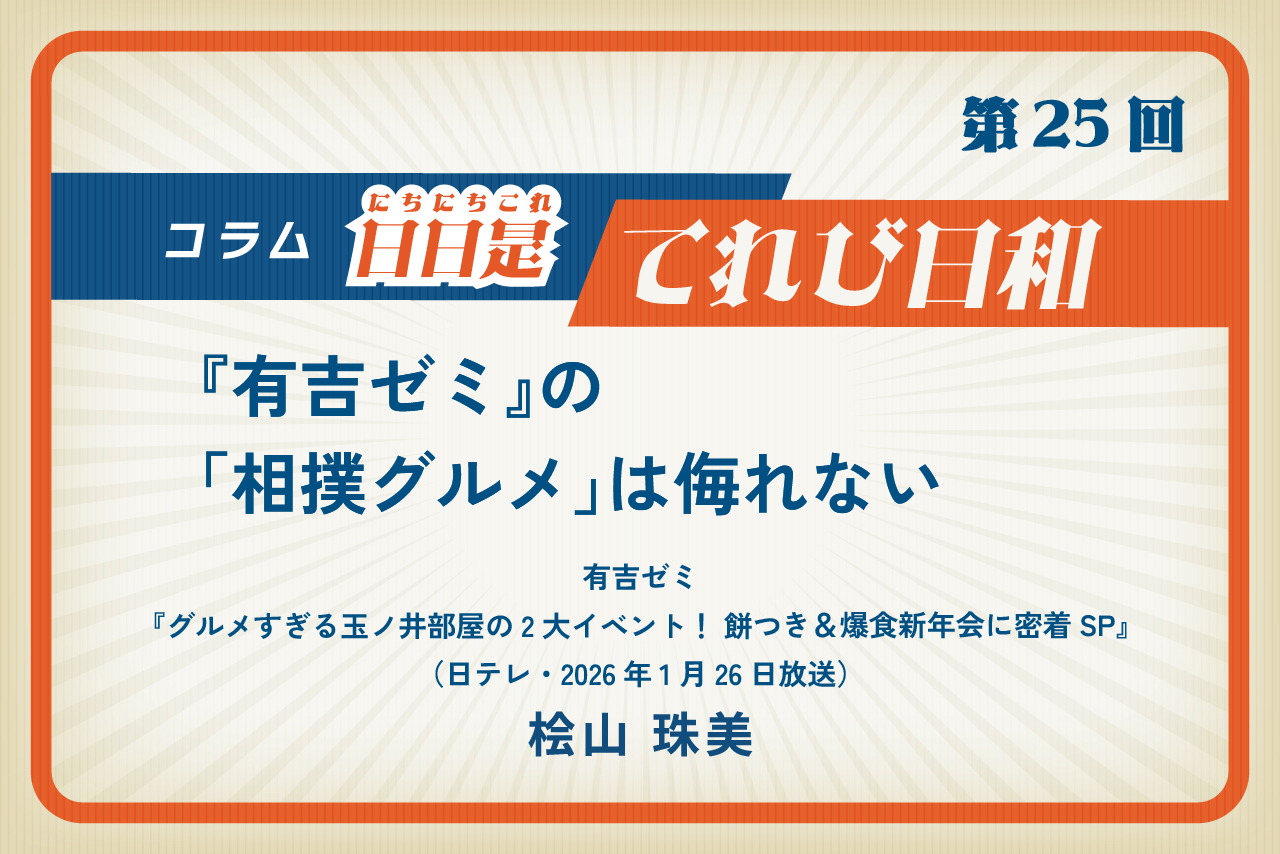制作者フォーラム
「クリエイティブって何?」―「北日本制作者フォーラムinふくしま」を開催
HBF編集部

2025年11月14日(金)、「北日本制作者フォーラムinふくしま」が、郡山市立中央公民館で開催されました。ミニ番組コンテストとトークセッションの2部構成で開催されたフォーラムには、東北6県と北海道の全民放とNHKの制作者を中心に約45名が参加しました。
フォーラム当日の模様をお伝えします。
ミニ番組コンテスト
子どもたちに伝える“命の授業”
ミニ番組コンテストでは、各局1本ずつ夕方ニュースなどの1コーナーの番組(ミニ番組)が出品され、全21作品から大賞1本、優秀賞2本、審査員特別賞3本、放送文化基金特別賞1本が選ばれました。審査員長の千野克彦さん(フリーディレクター)、稲田豊史さん(ライター、編集者)、辻愛沙子さん(株式会社arca CEO、クリエイティブディレクター)が番組ごとに講評・審査を行いました。

ミニ番組コンテスト 審査結果
| 賞 | 受賞者 | 番組名 |
|---|---|---|
| 大賞 | 土川怜音 (テレビユー山形) | 『東日本大震災から14年~あの日を境に変わった女性~』 |
| 優秀賞 | 井坂桃花 (北海道文化放送) | 『特集 重い障がい“18トリソミー”医療的ケア児と家族の1年』 |
| 優秀賞 | 水谷悠真 (NHK山形放送局) | 『父の心の傷を背負って 元日本兵のPTSD』 |
| 審査員特別賞 (千野賞) | 工藤勇生 (テレビユー福島) | 『カメラめせん 毎朝出迎えてくれる校長先生』 |
| 審査員特別賞 (稲田賞) | 佐藤大輔 (NHK青森放送局) | 『自由すぎる書道教室』 |
| 審査員特別賞 (辻賞) | 中嶌修平 (青森朝日放送) | 『第二の人生は“医師”の道~86歳の現在伝えたいこと~』 |
| 放送文化基金特別賞 (梅岡賞) | 角田翔太 (仙台放送) | 『東日本大震災で子供3人亡くした夫妻 家族5人揃った絵を依頼』 |

大賞に選ばれた『震災から14年~あの日を境に変わった女性~』は、小学生のときに東日本大震災で被災し、恩師に命を救われた女性が、その後小学校教師となり、“命の授業”を通して子どもたちに命の大切さとその守り方を伝え続ける姿に密着した番組。「構成力の高さや、取材者と取材対象者の先生との間にしっかりとした信頼関係があるからこそ、自然なコメントを引き出せており、その関係性が映像からも伝わってくる」点が高く評価されました。

優秀賞1本目、『特集 重い障がい“18トリソミー”医療的ケア児と家族の1年』は、“平均寿命1歳未満”と言われる難病を抱え、生まれつき重い障がいがある5歳の男の子に、1年間密着取材したドキュメンタリー。取材に長期的に向き合ってきた覚悟が伝わってくる作品であると評価されました。

優秀賞2本目には、これまで見過ごされてきた元兵士とその家族の心の傷に向き合った『父の心の傷を背負って 元日本兵のPTSD』が選ばれました。「映像として残す意義のあるテーマで、数十年先にも意義が色あせないような骨太な作品である」と評価されました。

ミニ番組コンテスト総評として、審査員長の千野さんからは、「どの作品からも、取材する作り手と、取材を受ける方々との距離感の良さが伝わってきました。そこには確かな信頼関係があり、その上で作品がつくられていることを感じました。皆さんがそれぞれの地域に根差し、丁寧に取材を重ねてきたからこそ築かれた信頼関係であり、それが作品の大きなストロングポイントだと思います。この点をぜひ大切にしてほしいと思います」との講評がありました。

大賞、優秀賞に選ばれた上位3作品は、2026年2月14日(土)に東京で開催される「全国制作者フォーラム」に出品されます。
トークセッション
続いて、参加者から事前に寄せられた質問をもとに、「クリエイティブって何?」という問いを軸に、ゲストの千野克彦さん、稲田豊史さん、辻愛沙子さんを迎えたトークセッションが行われました。

制作に生かせる“気づき”とは?
記者2年目の制作者から、「普段、何気ない日常の中から取材対象を見つけ出すことは、意外と難しいと感じることが多いです。皆さんは、ご自身の制作活動に生かすために、日常生活の中でどのように“気づき”を得ているのでしょうか」という質問がありました。
これに対し稲田さんは、「僕は何冊か本を書いていますが、ジャンルはまったくバラバラです。ポテトチップスの本を書いたり、離婚についての本を書いたりしています。“気づき”というのは、待っていても来ないし、追いかけても来ないものだと思っています。ではどうやって気づくのかというと、自分が面白いと感じるテーマを掘り続ける中で生まれるものだ」と述べました。
「ポテトチップスならポテトチップス、離婚なら離婚と掘り続けていると、そのジャンルに対する自分の“受容体”がどんどん大きくなり、常にスタンバイ状態になるんです。そうすると、何か起きたときに、自分の中のどれかのチャンネルに引っかかる。それが“気づき”だと思っています」と話しました。

辻さんは、“気づき”を得る方法として「自己開示を始めること」だと語りました。「実は私、右耳難聴で、周りからそのことが気づかれづらい。だから、見た目では分からない背景を持つ人や、目に見えない誰かの痛みに気づきやすいと思っているんです」。
一方で、「右耳難聴を打ち明けると、周囲からは『大変ですね』と言われることがありますが、私自身前向きに日常を送っているので、病気や障害のある人を必ずしも『かわいそうな存在』として描く必要はないという視点も持ち合わせている」と話しました。
さらに、「打ち明けることで、自分がどのような人間で、何に関心があるのかをあらかじめ示せるので、取材や企画につながる情報が自然と集まってくる」と改めて自己開示の重要性を訴えました。

千野さんは、「ドキュメンタリーのテーマをどうやって見つけようかと、あくせく考えなくてもいいと思います。普段の取材を続けていく中で、日々人と接しているうちに、『これ、ちょっと面白そうだな』というものには、必ず出会えるんです。そのときに、『これは何を伝えられるのか』と、もう一歩奥を考えることが、テレビのディレクターの仕事なんだと思います」。
「上司から『事件が起きたぞ』と言われて、日常の取材に向き合いながらも、どこかで『自分は本当は何をやりたいんだろう』『今やるべきテーマは何なんだろう』という問いが出てくる。そのときに、その先に何を伝えられるのか、という視点を持っていることで、気づきにつながるのかもしれません」と語りました。
今の時代、ドキュメンタリーは求められている?
葛藤を抱える制作者から、次のような質問も寄せられました。
「今の時代、ドキュメンタリーは求められていると思いますか。必要だとは感じているものの、自分が作る意味を考えあぐねる毎日です。何かヒントをいただけないでしょうか」。
質問した制作者は、自身の悩みをこう続けました。「番組を作りながら、『これは本当に見てもらえるんだろうか』という思いが、ずっと頭にあります。素材の良さを生かそうとして余韻を大切にしたり、ナレーションで説明せず、きちんと映像を見てほしいと思ってつないでいくと、今度は『絶対に見てもらえない番組になっているな』と感じてしまう。どんどん分かりづらくなっていくんです」。
「一方で、分かりやすさを重視すると、今度はどこか、しらけた番組になってしまう。今のテレビにドキュメンタリーは本当に求められているのか、いつも自問しています」。
これに対し、千野さんはまず、「実際に放送して、誰にも見てもらえなかったというケースはありましたか?」と問いかけ、「米印になっていたことはあります」との答えに対し、「米印でも、ゼロではない。見ている人は必ずいるんです」と語りました。

さらに、「今の時代、1.5倍速で見られて、最後まで見られないこともあるかもしれない。テレビの中でドキュメンタリーの本数は減ってきています。でも、それをもって『求められていない』と作り手が思ってしまったら、そこで本当に終わってしまう」。
「ネットやスマホで多様なものが見られる時代だからこそ、テレビのドキュメンタリーには、まだまだ役割があると僕は思っています。1.5倍速でも、見てくれればいい。テーマに興味を持ってくれたなら、それでいいんです」と述べました。
若手制作者の不安に正面から向き合いながら、千野さんは視聴環境の変化を前提に話を進めました。
「もし途中で離脱されたとしたら、それは次の工夫を考える材料になる。どうシーンをつなぐか、どう伝えるかを考え続けることが大切だ」と語り、「今日見た作品は、どれも取材者との信頼関係がしっかりあって、その信頼感が画面から伝わってきました。そこには、もっと自信を持っていい」と制作者を励ましました。
最後に、「僕はドキュメンタリーの可能性を一度も諦めたことはありません。確かに数字が悪いと、へこみますよね。でも、家族が『面白かったよ』と連絡をくれただけで、それだけでうれしい。見てくれる人は、少なくても必ずいる。わずかでも届けたいと思い続けないと、僕らは作り続けられないと思うんです」と、思いを語りました。
千野さんの言葉を受け、別の角度からの発言もありました。
稲田さんは、「『ドキュメンタリーが見たい人?』と聞いても、堅い印象があるので、なかなか手は挙がらないかもしれない」としながらも、「世の中の人は、ドキュメンタリー的なものに慣れている」と語りました。

「たとえば『水曜日のダウンタウン』も、ある種のドキュメンタリーだと思っています」と述べ、声が出せない芸人と、目が見えない芸人を同じ空間に置き、どのようにコミュニケーションが生まれるのかを記録した企画を例に挙げました。
「制作側の仕掛けはあるものの、そこで起こる人間同士の関わりや、そこから生まれる気づきや驚きは、まさにドキュメンタリー的なもの。ドキュメンタリーという名前が付いていなくても、人と人がどう関わるのかを見ることに、人は強い興味を持っている。決して見る人がいないジャンルではないと思います」と述べました。
一方、辻さんは視聴者の立場から、ドキュメンタリーの意義について語りました。「自分に近いテーマの作品に出会ったとき、自分では言葉にしづらい思いを、誰かが代弁してくれることに大きな価値を感じる」といいます。

「映像に残ることで、悩んだときに誰かが検索してたどり着き、他者に伝えるための『ツール』になることも、ドキュメンタリーの重要な役割です」と話しました。
また、「SNSにあふれる個人のリアルな声も、ドキュメンタリー的なものだとし、人は誰しも、自分以外の誰かの人生に触れたいと思っているからこそ、物語や他者の生き方に惹かれるのだ」と述べ、「視聴者として、もっとドキュメンタリーが作られてほしいと思っています」と、制作者たちにエールを送りました。
制作者からは「まだまだ頑張ってみようと思いました。ありがとうございました」との言葉がありました。
また司会者からも、「いちテレビ局員として、数字に落ち込んだり葛藤したりする場面は私自身にもありましたが、そこにとらわれすぎるのではなく、自分が信じるものを信じて進んでいこうと、改めて勇気をいただきました」とのコメントがあり、トークセッションは締めくくられました。
トークセッション後には、表彰式と懇親会が行われました。懇親会では、放送局の垣根を越えて同世代の制作者同士が悩みを共有したり、審査員に積極的に番組の評価を求めたりする若手制作者の姿が見られ、活発な交流の場となりました。

審査委員の稲田豊史さん(ライター、編集者)からフォーラムの感想を頂きました!
「評価」に飢える若き制作者たち―「2025北日本制作者フォーラムinふくしま」に参加して【稲田豊史】
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る