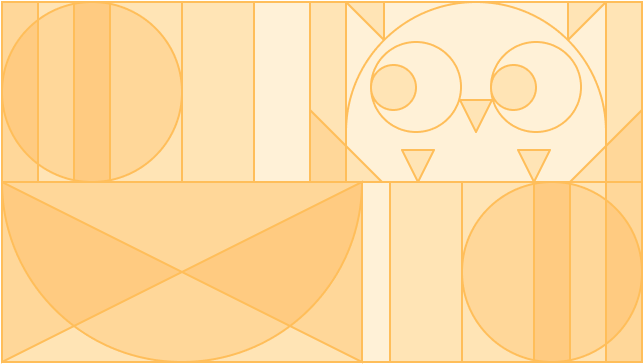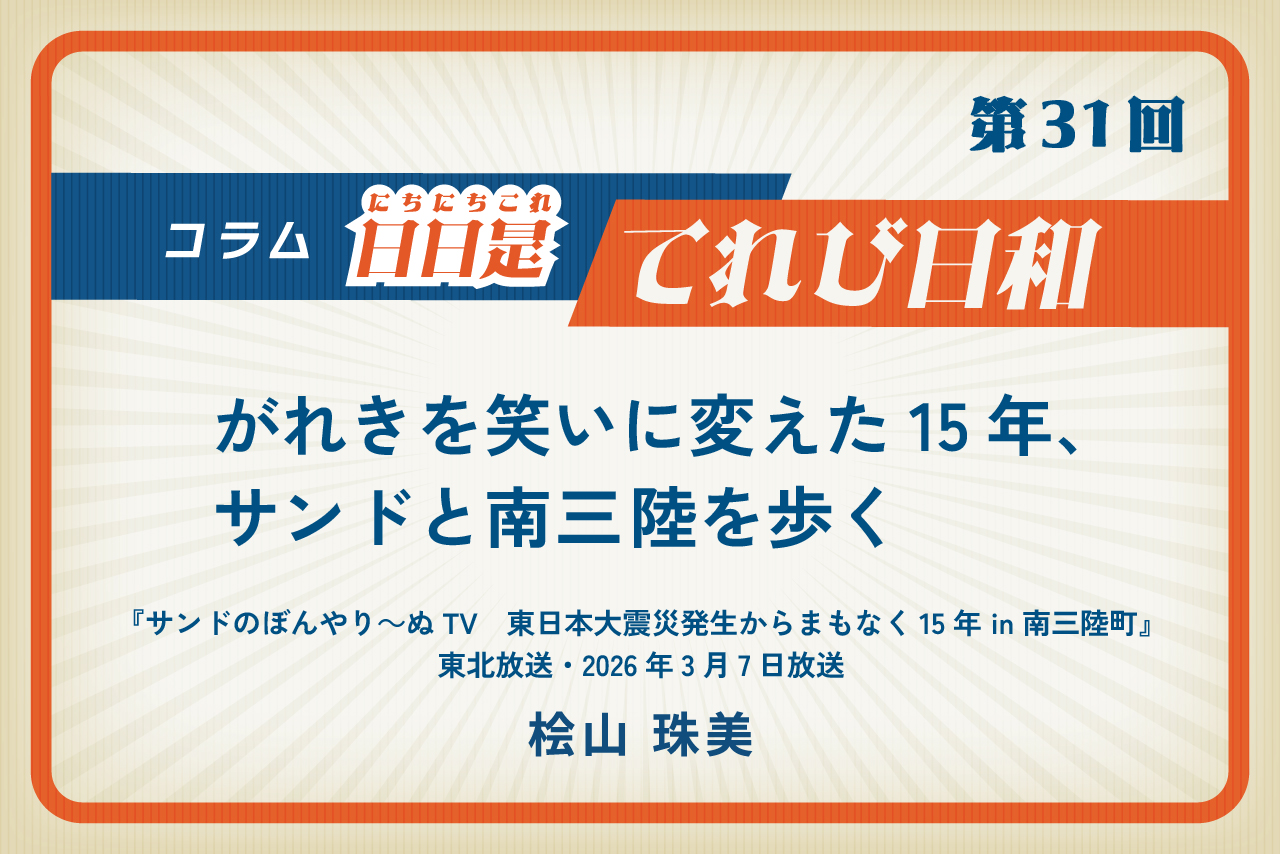助成
研究報告会2023【日根恭子、四方由美、北出真紀恵】
放送文化基金は、これまでに助成したプロジェクトの成果を発表する場として、助成金贈呈式とあわせて研究報告会を開催しています。
放送文化基金の2022年度の助成対象が決まり、2023年3月3日、ホテルルポール麹町(東京都千代田区)で助成金贈呈式が開催されました。贈呈式は第一部として研究報告会、第二部に助成金目録の贈呈、そして懇親会という構成で行なわれました。第一部の研究報告会では、技術開発部門で2019度に助成した豊橋技術科学大学 情報・知能工学系助教の日根恭子さんが、『人間中心社会のための放送技術開発』のテーマで発表を行い、人文社会・文化部門からは、2018、2019年度に助成した、宮崎公立大学人文学部教授でGCN(ジェンダーとコミュニケーションネットワーク)共同代表の四方由美氏に代わって、共同研究者で東海学園大学人文学部教授の北出真紀恵さんが、『番組製作会社から見る放送産業の変容に関する研究』というテーマで発表を行いました。報告会には約40名が参加し、質疑応答の時間にも活発な意見交換が行われました。
報告① 技術開発部門(2019年度助成)
『人間中心社会のための放送技術開発』
豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 助教 日根 恭子 氏

近年、テレビなどの従来メディアによる視聴に加え、新たな放送技術であるVR映像などの視聴機会が増加している。VR映像は高い没入感や臨場感を生むため、その映像コンテンツの記憶を向上させることなどが期待されているが、科学的根拠には乏しい。実際、VR映像は教育現場などでも使用されつつあるが、視聴者の認知負荷が高まり、記憶がむしろ低下する可能性が指摘されている(Makransky et al., 2019)。さらに、研究代表者らが行った実験より、製作側の意図とは反し、VR映像よりも従来メディアによる映像の方が、記憶が向上する場面さえあることが分かってきた(Hine & Tasaki, 2019)。こうしたことから、高い没入感や臨場感を維持しつつ記憶を向上させるためには、認知科学・心理学に基づいた、新たなVR映像コンテンツの提示方法を考案することが必要であるといえる。そこで本研究の目的は、記憶を向上させるVR映像の新たな提示方法を提案することとした。この目標を達成するため、心理物理実験に使用する映像提示プログラムの作成、および新たな提示方法の効果を検証するための心理物理実験を実施した。
研究代表者らのこれまでの研究(Hine & Tasaki, 2019)より、VR映像の特徴である自由な視点で映像空間内を視聴できることが記憶低下につながる可能性が明らかとなっている。一方で、この視点自由度が高いことが、高臨場感をもたらしているため、VR視聴の特徴である高臨場感を保ちながら、記憶促進を向上させるためには、記憶させたい対象が提示されている場合とそうでない場合で、視点自由度を変更できることが必要である。そのため、VR映像のコンテンツ提示について、視点自由度を調節することができる映像提示プログラムを作成した。
次に、作成した映像提示プログラムにより記憶成績が向上するか評価するため、心理物理実験を実施した。実験では、記憶成績と関連のある知覚弁別閾を調べ、視点自由度により知覚弁別閾がどのように変わるかを検証した。実験参加者はヘッドマウンテッドディスプレイを装着し、VR中に提示される対象が大きいか小さいかの判断が求められた。視点自由度条件として、実空間より不自由(低自由度)、実空間と同様(同自由度)、実空間より自由(高自由度)に視聴する、3条件が設定され分析対象となった。実際に提示された物体の大きさの種類は5種類であった。各被験者について、視点自由度条件ごとに心理物理関数を求め、丁度可知差異(JND:Just Noticeable Difference)を算出した。JNDは大きさの違いを見分けることのできる最小単位で、この値が小さいほど大きさの違いの弁別感度が良いことを表す。JNDについて多重比較検定を行ったところ、高自由度よりも低自由度の方が有意に小さくなることが明らかとなった。これは、視点自由度が低くなるほど、大きさを見分ける感度が良くなることを示している。このことは、不自由度な体験を提供したほうが、記憶が向上する可能性を示唆している。
本研究により、VR映像の視点自由度を変えることで記憶が向上する可能性を示され、記憶を向上させるVR映像の新たな提示方法が提案することができた。また、本研究を通して、単に映像技術の向上というだけでなく、ヒトの生理、心理に基づく、映像提示技術の研究開発の必要性が示された。
・2019年度助成「記憶を向上させる新しいVR映像提示の研究」
報告② 人文社会・文化部門(2018、2019年度助成)
『番組製作会社から見る放送産業の変容に関する研究』
GCN(ジェンダーとコミュニケーションネットワーク)共同代表 四方 由美 氏(宮崎公立大学 人文学部 教授)

※四方由美氏が報告の予定でしたが、急遽、GCN共同研究者で東海学園大学人文学部教授の北出真紀恵氏が発表を行いました。
本研究は、女性とメディアをめぐる現状と問題点を調査・分析し、解決のために発信を行うGCN(ジェンダーとコミュニケーションネットワーク:共同代表 林香里・四方由美)による共同研究である。私たちは、2010年度に放送文化基金の助成を受けた研究成果を『テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランスー13局男女30人の聞き取り調査から』(大月書店 2013)として刊行したのを始め、「放送で働く男女に関する実態調査」(2014)を実施するなど、GCNが90年代から担ってきた「メディアで働く男女に関する実態調査」(1994)、「放送ウーマン調査」(1999、2004)を継承し、本研究の「番組製作会社」の実態調査研究へとバトンをつないできている。
本研究では、これまで不可視化されてきた「番組製作会社」に光をあてている。研究の背景として「製作会社」には2000年代に入ってからネガティブな文脈で注目が集まるようになり、「テレビ制作という職場はブラックである」という認識が広がってきたことがある。2003年、「下請法改正」で番組製作取引が問題視され、追いかけるように2008年、総務省が下請け取引のガイドラインを策定した。現在のテレビ制作の現場では、外部発注や派遣労働が著しく増加し、現場ではその内部に幾重もの階層が作り上げられているのだ。
私たちは「番組製作会社」で働く制作者たちの証言を集めることによって、日本の放送産業の制度変容と現在のテレビ番組制作現場のリアリティを探ろうと試みている。インタビュー調査は2019年10月から2021年1月にかけて制作会社所属の制作者20名を対象に実施し、質的データの分析には質的分析ソフトMAXQDAを使用した。
調査の結果からは、テレビ局と製作会社には根深い「タテ型序列構造」が存在することや、デジタル技術革新によってテレビ産業界はアウトプットの多様化とコンテンツビジネスの変容のさなかにいることが確認された。また、業務のデジタル化によって作業量の増加や制作の細分業化など、制作者たちの仕事の仕方や労働環境、組織への帰属意識などに変化が生じていることなどが見て取れ、放送現場において最下位の職位であるアシスタント・ディレクター職に女性が多く配置されていることが明らかになった。若い制作者たちにとって、“工場”のような作業現場で、細分化された業務しか経験できないことが日常化しつつあるのがリアリティであるとするならば、彼ら・彼女らはどのようにして制作者としての未来を描くことができるだろうか。そして、テレビ制作の現場がどのように若い制作者を育てていくかは、テレビ業界全体として考えるべき課題であるだろう。
本研究の成果は、林香里・四方由美・北出真紀恵編『テレビ番組制作会社のリアリティ つくり手たちの声と放送の現在』(大月書店 2022)として上梓した。
・2018、2019年度助成「番組製作会社から見る放送産業の変容に関する研究」
北出真紀恵 プロフィール
東海学園大学人文学部教授。関西学院大学文学部在学中からフリーアナウンサー(放送メディアおよびCMナレーション)として活動。大阪大学大学院人間科学研究科に社会人入学、前期博士課程を経て後期博士課程単位修得退学後、転職。GCNに参加。著書に『「声」とメディアの社会学―ラジオにおける女性アナウンサーの「声」をめぐって』(2019晃洋書房)、『ジェンダーで学ぶメディア論』(2023世界思想社)など。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る