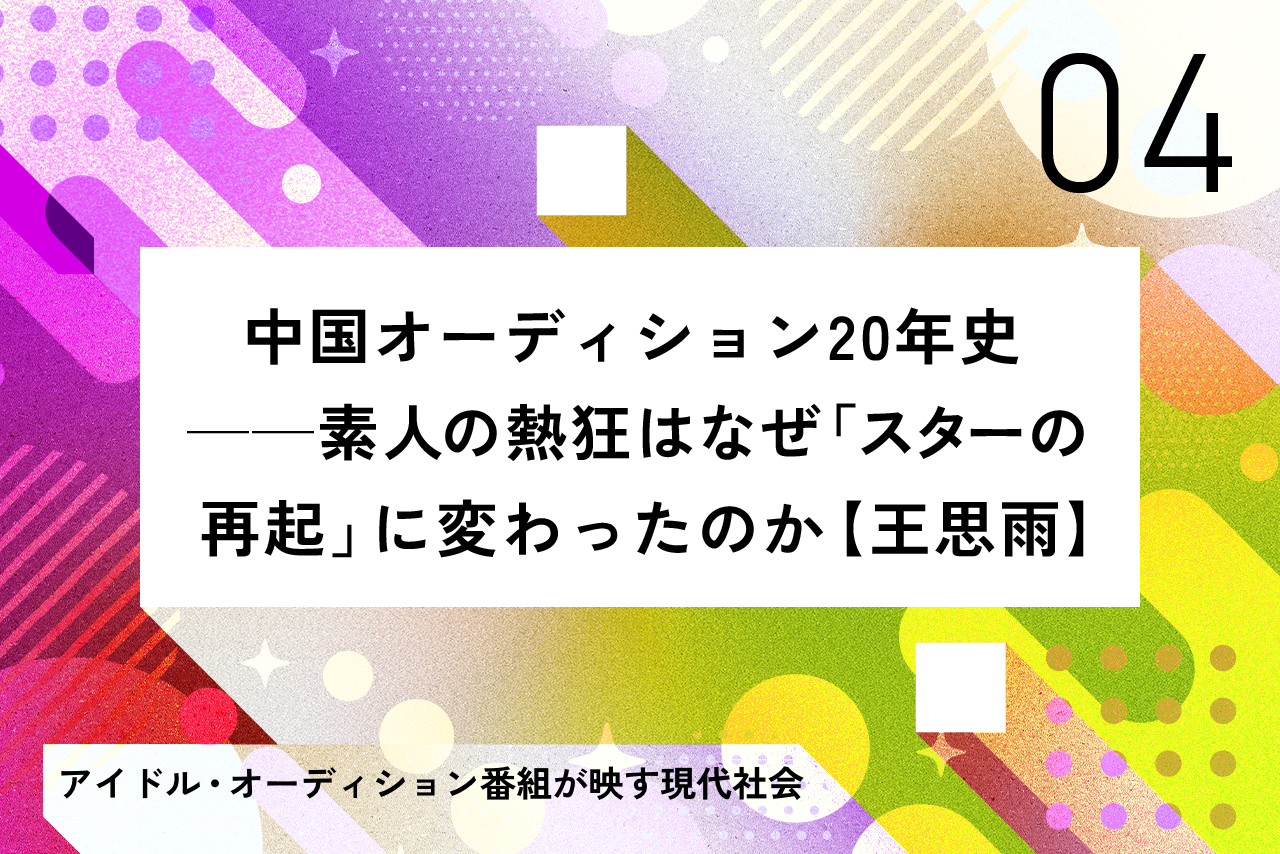放送文化基金賞
第40回放送文化基金賞 各部門の講評
テレビドキュメンタリー番組部門の講評
吉田 喜重 委員長
テレビドキュメンタリー作品のそれが宿命なのだろうが、これまで高く評価されてきた太平洋戦争、あるいは広島、長崎の被爆、そして現在では東日本大震災の記録は、いずれにしても悲しみの表現であった。
しかし本年度の最優秀賞、NHK福岡・熊本放送局制作『三池を抱きしめる女たち〜戦後最大の炭鉱事故から50年〜』は、依然として悲しみを伝えながら、かえって心が癒され、歓喜の気持ちすら抱かせる作品であった。
50年前三池炭鉱で起きた炭塵爆発、死者458人、一酸化炭素中毒患者839人、当時は治療の方法もなく生きることを強いられた患者たちとその家族の、その後の半世紀を追跡したものだが、不治の患者である夫に寄り添って生きてきた妻たちに焦点を当て、理不尽な生を強いられた女性たちのありようを描く映像には、誰しもが人間の尊厳の偉大さ、美しさといったものに思い至り、魂を揺さぶられるに違いない。
優秀賞のBS-TBS制作、『ドキュメンタリースペシャル フェンス』は、これまで幾度となく問われてきた沖縄の基地をめぐる、沖縄と本土の対立の構図に、フェンスの向こうの駐留アメリカ軍への取材を加え、基地問題の深層を改めて直視させるものである。
奨励賞の南日本放送制作『千年後の森が見える 屋久島・山師の物語』は、孤島に生きる木こりの記録だが、地域に深く根ざす民放局の思いやりのありように魅せられる。
同じく奨励賞、NHK制作『日本人は何をめざしてきたのか 第5回福島浜通り 原発と生きた町』は、福島原発の崩壊により故郷を去ることを強いられた双葉町の、過疎化ゆえに原発を誘致せざるを得なかった苦悩の歴史を追い、報道取材のあるべき姿に貫かれている。
同じく奨励賞、NHK広島放送局制作『終わりなき被爆との闘い〜被爆者と医師の68年〜』は、放射線を浴びた後遺症がDNAまでも傷つけ、いまもなお被爆者を苦しめている現状を告発するものだが、それは被爆ドキュメンタリーの歴史に新たな年輪を加えることを意味している。
テレビドラマ番組部門の講評
河合祥一郎 委員長
2013年という年を象徴するテレビドラマとして、テレビドラマの枠を飛び越えて社会現象ともなった連続テレビ小説『あまちゃん』と、「倍返しだ」の名ゼリフで日本中を湧かせた『半沢直樹』の存在は大きかった。「がんばれ」とエールを送る時代から、自分に何ができるのかを考える時代に変わったと言うべきか。震災後を描いて最優秀賞をとった『時は立ちどまらない』は、被災しなかった者が被災者のそばで何ができるかと苦悩する姿を描くものであり、震災後3年たった今だからこそ描けるドラマだという評が多かった。山田太一脚本のヒューマニズムを、すばらしいキャストを得て堀川とんこう監督がきっちりと美しいドラマに仕立て上げた。
『あまちゃん』は、ドラマの虚構性を脱構築し、あえてドラマであることを露呈するようなメタ・ドラマの手法が新鮮で、宮藤官九郎の才能を感じさせた。さまざまなキャラクターがそれぞれの存在感を強烈に感じさせる設定もおもしろく、多くの視聴者に元気を与えてくれた。大友良英の音楽は、そんな作品の力を象徴している。
『半沢直樹』は、審査対象となった第一回に、その後展開するドラマのあらゆる要素が詰め込まれていることを改めて確認して、その完成度の高さに舌を巻いた。高視聴率をとったのには、それだけの理由があったのである。主演の堺雅人の演技力も重要であり、堺あっての『半沢直樹』であった。
満島ひかりが主演した『Woman』は、2010年のドラマ『Mother』のスタッフによる作品であるが、坂本裕二の脚本は今回のほうが優れていた。シングルマザーを演じる満島の演技が光っており、圧倒的な魅力をみせた。ほかにも惜しくも選に漏れた優れた作品はあったが、有意義な議論をじゅうぶん尽くした結果の選考である。
テレビエンターテインメント番組部門の講評
堀川とんこう 委員長
受賞作3本は、いずれも制作意図のはっきりした優れた番組だが、うち2本は他のコンクールではドキュメンタリー部門に出品されたものだ。それが良くないというのではない。出品する側にとっても選ぶ側にとっても、この部門の捉え方が難しいということである。
放送文化基金にエンターテインメント部門があることの意味は大きい。番組表の真中でひしめき合っているお笑い番組、バラエティやクイズに、賞の門戸を閉じるのではなく、そこに光を当てることで娯楽番組の質について、少しでも意識的であろうとしているのである。
バラエティ番組と総称されるものが私たちに提供している「くつろぎ」は決して意味の小さいものではない。「くつろぎ」ながら、休息しリフレッシュしている。しかし同時に私たちは番組から何らかの予期しない影響を受けているに違いない。もしかすると日本人の民度に大きく関わるのは、実は膨大な数のバラエティ番組かもしれないと思う。そこにエンターテインメント番組の質を考える契機があるように思う。
入賞には至らなかったが、テレビ東京の『YOUは何しに日本へ』という番組があった。空港でカメラが待ち構えていて入国してくる外国人に、「YOUは何しに日本へ」と問いかけ、さらに「じゃ、ついて行っていいか」と密着取材するという番組である。有名タレントの出てこない、いかにも低予算の番組のようだが、アイディアが見事に成功していておもしろい。一様に観光客と見える外国人だが、来日の理由は驚くほど多様で、彼らの関心の在りようから日本という国を再発見する趣がある。ただの突撃インタビュー番組のようでいて、こちらの常識が覆される快感がある。出品作にはコスプレの世界大会というタイトルとは意味の違うものが挿入されていて内容を薄めてしまったのが残念だが、いわゆるマイナー・メジャーのエンタメ番組を考えるヒントを含んでいるのではないか。
ラジオ番組部門の講評
金田一秀穂 委員長
例年思うことだが、私たちが普通にラジオを聴くのは、車の中や何かをしながらであって、審査室でスピーカーとにらみ合って熱心に聴くのは、かなり不自然ではあると思う。しかし、そのような形態でも聴くに値する充実したものが選ばれる。いつもの番組の中身に加えて「審査会受け」する要素が必要になる。
ひとつ気になったのは、不必要に長いものがあることだ。放送時間の枠に合わせることが必要なのだろうが、聴いていてだらけてしまうものがあって、残念だった。
今年の最優秀賞と優秀賞は、同じ北日本放送の作品二つが選ばれた。重複を避けるという配慮を越えて、二作品の質の高さが、応募作品中群を抜いており、審査員全員が納得するところとなった。
『In My Life』は、ビートルズの曲を心に染み入るように英語で歌う、介護福祉士を天職とする川手照子さんという女性の物語である。夫を亡くし、今の仕事にたどり着くまでの人生を、自ら歌うビートルズの曲が美しく繋げていく。録音もきれいである。
『立山に想ふ』は、西村雅彦氏が故郷に帰って、素人集団と一緒に作りあげたラジオドラマである。最初は学芸会に付き合わされているようなぎこちなさを感じるのだが、聞いているうちにいつのまにか演者たちと一体になって、そのストーリーを楽しんでいる。聴取者参加型のラジオドラマの一つの新形態であるかもしれない。
『金魚の恋』は、手だれのプロの仕事である。筋立てに不自然さがあるものの、それを補う効果音の使い方が巧みだった。
撰にはもれたが、琉球放送の『アバヨイ 島唄で紡ぐ十五の春』は、南国の昔から変わらぬ故郷の空気と光をスピーカーを通して快く伝えてくれて、聴いていてとても心地よかった。ここに日本の原風景の一つがしっかりと守られていることを感じさせた。
放送文化部門の講評
河野 尚行 委員長
個人・グループ部門の応募数は、今年は13件で、この中から3点を選ぶ。その一つが南海放送のドキュメンタリー映画「X年後」制作・自主上映グループである。60年前のビキニ環礁水爆実験による被爆については、これまで「第五福龍丸」を中心に語られてきた。だが、この海域には当時1,000隻もの日本のマグロ漁船が操業しており、様々な放射能被害を受けていた。この事実を南海放送は9年前から追跡調査し、地域放送番組とNNNドキュメントなど10本の番組を制作、長い年月を経て顕在化する放射能被爆の恐ろしさを描き、更にアメリカの資料から、ビキニ環礁での度重なる核実験で、当時、日本の空を含む太平洋沿岸の国々の大気も広く汚染されていた事実も突きつける。それを集大成する形で映画を制作、全国で自主上映を続けている。
次にNHK盛岡放送局と「失われた街」模型復元プロジェクトが共同で行った、「ふるさとの記憶」プロジェクト。全国の建築学科の学生がプロジェクトを組んで、津波に襲われた地域の元の姿を立体模型で再現する。そこに住民が参加、住民の手で彩色し、一部修正して完成させる。災害前のふるさとの日常、街並みや海辺の仕事、祭りの様子を思い出して言葉を紡ぐ住民の表情が深く胸を打つ。ふるさとは記憶の中に生きている。この記録は人々の共同記憶の集積であり、貴重なアーカイブスだ。
個人で推薦されたのは「ワーキングプア」、「無縁社会」、「老人漂流社会」などの番組制作に携わったNHKプロデューサーの板垣淑子さん。戦後の高度経済成長期に大都市に集中した生産年齢層が、老人世代に突入し始め、無縁社会、老人漂流社会が他人ごとではなくなった。日本の社会問題として益々大きな比重を占める高齢化問題を、更に追及してほしいという期待も込めて選出した。
その他に議論が集まったのは、毎日放送の「情熱大陸」AR取材班の多視点放送。それにNHKの「福島をずっと見ているTV」のユニークな視点などが注目された。
放送技術部門の講評
長谷川豊明 委員長
今年の応募件数はNHK4件、民放7件、民放連1件、合計12件と、近年では多くの件数となった。このうち、地域局から2件あった。分野別では、送信機関係が3件、中継番組支援ツール3件、ファイルベースシステム2件、バーチャル映像関係2件、音声関係1件、ニュース番組支援ツール1件であった。応募件数が多かったこともあり、選考は難しいものになった。また、入選には至らなかったが、地域局からの応募のものは、地域局に相応しい内容であり、その技術開発意欲を称賛したい。
TBSテレビの「オメガファインダー」の開発は、スマートフォンを用いて、中継現場の送信予定場所から伝送路上の遮蔽物などの所見が簡単に得られ、中継準備作業の利便性や迅速性を大いに高めることができた業績を評価した。
フジテレビジョンの「ロケーションサポーター」の開発は、取材クルーの連絡手段としての電話が大災害発生時には輻輳して機能しないことが多いことから、電話にかえてインターネットとし、スマートフォンを利用することにした。災害時においても複数の取材陣の位置情報を本社デスクはもとより、お互いに確認できる仕組みを構築した業績を評価した。
NHKの「スカイマップ」の開発により、ヘリコプターから届く空撮映像でも地名を特定することができるようになり、とくに夜間には有効な手段となった。撮影対象をリアルタイムに特定でき、撮影場所や被災状況の迅速な把握・取材時間の短縮に寄与した業績を評価した。
日本のテレビ放送におけるラウドネス管理の導入は、「番組によって音声レベルが違う」「NHKと民放と音量が違う」など視聴者からの声に応え、民放連、NHK、電波産業会が一体となり、テレビ放送のチャンネル間や、番組間の音量感のバラツキを解消させた。放送事業者をあげてのこの取り組みは、個々の放送事業者の個別的な技術開発とは趣が異なるものであるが、放送事業への貢献は格別であり、特別賞を贈ることとなった。
関連記事を見る
新着記事を見る
私たちについて
詳しく見る財団情報
詳しく見る