 �i�ʃE�B���h�E�ŊJ���܂��j
�i�ʃE�B���h�E�ŊJ���܂��j |
| �����̐\���A�e�폑�ނ̒�o�͂����炩��B |
|
|
���a49�N(1974�N)�x���猻�݂܂œ���������{���������̑ΏۑS�Ă������ł��܂��B

 |
|
|
 |

| �@������������̕����Q�S�N�x�̏����Ώۂ����܂�R���W���A�����E���͒��̊C�^�N���u�ŏ��������掮���J�Â���܂����B���掮�͑O�N�x�Ɠ��l�A��P��������A��Q�������ژ^����A�����č��e���3���\���ōs�Ȃ��܂����B |
|
|
��1���@������
|
�@��P���̌����ł́A����23�N�ɏ����A���������v���W�F�N�g�̂����A�Z�p�J�����傩��A�c��`�m��w���w�� �y���� �씨�G�����A�w�]�͔����ǂ������邩�`�A�[�g�̔]�Ȋw�x�Ƒ肵�āA�]���ǂ̂悤�ɔ���������̂����A����|�p�ɑ��ĉ�������]�̓�����\�����������ʂƂƂ��ɔ��\�B���f�B�A����[���̕��y�ɂ��A��i�����R�Ɏ����^�сA�l�X�Ȓm���邱�Ƃ��ł��A�|�p��i�ɐڂ��邱�Ƃ݂̍�����̂��ω����Ă��錻��Љ�ł̎��p�I�ȑ��ʂƂ��Ĕ��������邱�Ƃ�|�p�ɐڂ��邱�Ƃ��ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɖ𗧂̂��Ƃ������ɂ��Ă��������ʂ���܂����B
�@�l���Љ凌������傩��́AGCN�iGender and Communication Network�j������\�@�J����������i���C��w���w���@�y�����j���A�w�u��ƃW���[�i���X�g�v�̃��C�t�R�[�X�x�̌������ʂ�B���G�E���l����������Љ�ɂ����ĕɑ���j�[�Y������ɂ킽�邪�A�ʂ����ĕ̒S����ł���l�ނɑ��l���͌����邾�낤���\�\�\�A��ł́A30����ΏۂɃ����O�C���^�r���[���s�����Ƃ��������̊T�v�A�����ĕ��͂̌��ʁA���炩�ɂȂ��Ă����u��ƃW���[�i���X�g�v�̃��C�t�R�[�X�ɂ��āA�W�F���_�[���A���㍷�A�L�[�ǂƒn���ǂ̍��ٓ��𒆐S�ɕ��܂����B |
| �@�@�Z�p�J������i����22�N�x�����j |
�w�]�͔����ǂ������邩�`�A�[�g�̔]�Ȋw�x
�c��`�m��w���w��
�y�����@�씨�G�� ��
�@���Ƃ͉����A�|�p�Ƃ͉����A����܂ŗ��j�ɖ����c���Ă����|�p�Ƃ��Ȃ��̑�Ȃ̂��A�n���͂̌���͂ǂ��ɂ���̂����������̔���|�p�Ɋւ�����ɂ��āA�ߔN�ł͔]��S�̊w�₩��̐ڋ߂����݂��Ă���B�{�ł͕҂̋ߔN�̌��������ƂɁA3�̎��_����A����|�p�Ɣ]�̊W�ɂ��Ă܂Ƃ߂��B... ⇒�Â���ǂ� |


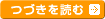 |
 |
| �A�@�l���Љ�E��������i����22�N�x�����j |
�w�u��ƃW���[�i���X�g�v�̃��C�t�R�[�X�x
GCN�iGender and Communication Network�j
������\�E���C��w�y�����@�J������ ��
�@2009�NGCN�́A���ۏ������f�B�A���c��Ấu���f�B�A�ɂ����鏗���̒n�ʍ��ے����v�i���E��60�J���Q���j�ɓ��{�S���Ƃ��Ē����ɂ��������B�ǂ̃��f�B�A��Ƃɂ����Ă��l���ӔC�҂́A�j���̑ҋ��͕����ł���Ɠ����Ă���B����ɂ��ւ�炸���{�̃}�X���f�B�A�g�D�ł͏����̊�����2���~�܂�ł���A�����̎Q�旦�͐��E�ʼn��ʃN���X�ł���B���G���l����������Љ�ɂ����āA�̐l�ނɂ����l�������߂��Ă���̂ł͂Ȃ����B... ⇒�Â���ǂ� |


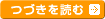 |
��Q���@���掮
|
�@��Q���̏����ژ^�̑���ł́A�͂��߂ɉ��엝�������A�u���N�́A���{�Ńe���r�������n�܂��Ă���60�N�Ƃ����ߖځB�����āA�e���r���������S�Ƀf�W�^�������ꂽ���A���߂ĕ����̉ʂ����ׂ��������l���鎞�����Ă��܂��B�e���r�A���W�I���͂��߂Ƃ��郁�f�B�A�̖����⑶�݈Ӌ`���l���A�Z�p�J���A�����A�����A���Ƃ�i�߂邱�Ƃ́A���Ȃ킿���������̔��W���e����Ŏx���čs���Ӗ�������A���҂���Ƃ���͑傫���B���ꂼ��̕���Ő���A�D�ꂽ���ʂ������Ă������������v�ƈ��A�B���������A�u�Z�p�J���v�̉H�����r�R���ψ����Ɓu�l���Љ�E�����v�̍��萭�j�R���ψ����獡��̐R���ɂ��ĊT��������܂����B |
�@�����Q�S�N�x�́A�Z�p�J���Q�V���A�l���Љ�E�����V�Q���̍��킹�ĂX�X���̐\��������A�R���̌��ʁA�Z�p�J���P�P���A�l���Љ�E�����R�P���̍��킹�ĂS�Q���A���z�T�C�T�O�O���~���̑�����܂����B�����ΏۂɑI�ꂽ1�l1�l�ɉ��엝��������ژ^����n����A������āA������w��w�@��H�w�n�����ȁ@�u�t�@���R�p������ƌc��`�m��w�@�@�w���@���u�t�@�������q����̓�l����v�X�A������\���Ĉ��A������܂����B
�@����̏��������掮�́A��P���A��Q���ʂ��Ă̂�130�l�̕��ɏo�Ȃ��Ē����܂����B |

�Z�p�J������̑�\
���R�p������ |

�l���Љ�E��������̑�\
�������q���� |
|
|
�����N�x�̑����ꂽ�����E���Ƃ̓���
���Z�p�J��
�@�Z�p�J���̐R���́A�P���P�P���ɐ��ψ���A�P���P�W���ɐR���ψ���J����A�P�P�����̑����܂����B
�@�̑𗦂́A�\�������Q�V���ɑ��ĂS�O�D�V���B
�@�������͑O�N���z�̂Q,�Q�O�O���~�ŁA�P��������P�Q�O���~����Q�U�O���~�A���ςQ�O�O���~�ɂȂ�܂����B�O�N�x�ɔ�א\������������A�̑����������������Ƃ���P��������̕��Ϗ����z�͂T�O���~�������Ȃ�܂����B
�@���e�I�ɂ́A�C���^�[�l�b�g�̔��B��f�W�^�����̐i�W�ɂ��R���e���c�̑��l�����i�ޒ��ŁA�ԑg�̎�������Ɋւ��錤���E�J���u�e���r�ԑg�̐��E�E�Z�p�Ɋւ��錤���v�A���ɂ��a�V�Ȍ����ƕ]�����ꂽ�u�f���R���e���c�̃^�[�Q�b�g�����ґw�̎�������Ɋւ��錤���v�ȂǁB
�@�܂��A�Q���������摜���^����u���̊��v�̗v�����A�S���I�A�����I�ɉ𖾂��悤�Ƃ��鎎�݂����ʂ����҂���Ă��܂��B
|
���l���Љ�E����
�@�l���Љ�E�����̐R���́A�P���P�U���ɐR���ψ���J����A�R�P�����̑����܂����B�̑𗦂́A�\�������V�Q���ɑ��ĂS�R���B�������͑O�N�x�Ɠ����R,�R�O�O���~�ŁA�P��������P�O���~����Q�R�O���~�A���ςP�O�U���~�ɂȂ�܂����B
�@���e�I�ɂ́A�����{��k�ЂɊ֘A���������A�����̖@���x��ϗ��Ɋւ��錤���A�e���r�������҂ɗ^����e���Ɋւ��錤���ւ̏����\�����������A���̒�����A�u��Вn�ɗ��ꂽ���y�\�����{��k�Ђɂ����郉�W�I�����𒆐S�Ɂv��6���̎Q�c�@�I�����T���āu�e���r�̑I�����L���҂̊���Ɠ��[�ӌ��ɗ^����e���̃��J�j�Y���̌����v�Ȃǂ��̑�����܂����B
�@�e���r�����U�O�N���}���鍡�N�A�A�[�J�C�u�֘A�̌����������A���{���a�w��́u���a�����E����ɂ�����f���������p�̂��߂̊�b�I���������v��u����Q���ۈ�E����ɂ�������H�L�^�f���̃A�[�J�C�u���Ɋւ��錤���v�Ȃǂ��̑�����܂����B
�@�܂��A�u�A�j���̐l�ވ琬�Ɋւ��������r���������v��u���f�B�A��ʂ������ۘA�g�iICoME2013�j�̊J�Áv�A�u����TV�t�H�[����2013�̊J�Áv�ȂǍ��ۓI�Ȍ����⎖�Ƃ��P�O���̑�����܂����B
�@���̂ق��A���N�x�́A���������̌����҈琬�Ƃ����ϓ_������̌����҂�Q���ւ̏��������肵�܂����B |
�����ΏۂɌ��܂����v���W�F�N�g�́A���N�S�����痈�N�R���܂ł̈�N�ԁA�����A�J���A�����A���Ɠ������{���A���܂Ƃ߂邱�ƂɂȂ�܂��B
|




