 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます) |
| 助成の申請、各種書類の提出はこちらから。 |
|
|
昭和49年(1974年)度から現在まで当基金が実施した助成の対象全てを検索できます。

 |
|
|

<報告① 技術開発部門(平成22年度助成)>

『脳は美をどう感じるか~アートの脳科学』 |
 |
慶應義塾大学文学部
准教授 川畑 秀明 |
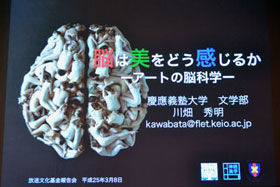 |
美とは何か、芸術とは何か、これまで歴史に名を残してきた芸術家がなぜ偉大なのか、創造力の源泉はどこにあるのか──これらの美や芸術に関する問題について、近年では脳や心の学問からの接近が試みられている。本報告では報告者の近年の研究をもとに、3つの視点から、美や芸術と脳の関係についてまとめた。
まず、芸術とは脳にとって何であろうか。脳は作品を理解と解釈によって鑑賞する。このとき、脳は目の前にある作品の意味を自己との関係の中で捉え、直感的に理解が困難な場合や現実とは異なるものに遭遇したときに問題解決をし、想像力を働かせて足りないものを補おうとする働きがある。その問題解決に対する満足が脳にとっての芸術の評価となる。次に、脳は美をどのように感じるのであろうか。美を感じる脳の仕組みは「報酬系」とよばれるものであり、美に限らず、私たちが報酬を得るときや報酬への期待などに反応するものである。美や魅力、欲求など、志向性のある快に対する脳の仕組みの存在こそが、美の神経回路の正体であり、脳が美を欲する理由でもある。
さらに、芸術や美はどのように役立つのであろうか。現代社会では、多様なメディアや情報端末の普及により、作品を自由に持ち運び、様々な知識を得ることができ、芸術作品に接することの在り方自体が変化している。報告者の研究では、美術コンテンツの鑑賞における「関わりかた」によって、ストレスや気分などの精神的健康への影響を検討している。作品への理解を文章として書き留めたり、作品の模写をしながら鑑賞したりするときの方が、漠然と作品を見るときよりも不安や不機嫌さを静める効果があることを明らかにした。
よく「芸術とはコミュニケーションである」という。今後は、鑑賞者側からのコミュニケーションの在り方がどのように作品の見方を変化させるかについて検討し、表現者と鑑賞者の双方向コミュニケーションの可能性を探っていきたい。 |
平成22年度 助成
「家庭用テレビを用いたバーチャル美術館の効用とその心理脳科学的評価」 |
|
|




