| ■乳幼児のテレビ認知研究の必要性 |
多数あるメディアの中でもテレビはその汎在性・接触時間の点で群を抜くものであり、現代社会では生まれた時から非常に身近な存在である。菅原ら[1]によると、日本では、この20年間で乳児のテレビ視聴時間が20~40分程度増加しており、2003年では0歳時のテレビ視聴時間*は一日1時間44分、スイッチがついているだけの時間もあわせると接触時間が3時間13分にも及ぶ(1歳時では3時間23分)。こうした乳幼児のテレビ視聴時間の増大に伴い、発達環境としてのテレビの功罪について近年多くの議論がされてきているが、実証的データに基づいているものは非常に少ない。議論の大半は根拠が不鮮明なスローガンであることが多いのが実情である。メディアが短期・長期に渡り子どもの発達過程に及ぼす影響は無視できないため、乳児期からの発達過程においてメディアがどう影響するのかを科学的見地から行う必要がある。
私たちの研究室では、乳幼児がテレビ映像をどのように認知しているのかについて、発達認知神経科学的に明らかにする試みを行っている。ここでは、乳児がテレビ映像をどのように認知しているのかを、EEG(脳波)とNIRS(近赤外分光法)により検討した研究をそれぞれ紹介する。 |
*ビデオ、テレビゲームの視聴時間も含む。
|
| ■テレビ映像視聴中の乳児の脳活動 |
まず、他者の行動をテレビで観察しているときとライブで観察しているときの乳児の脳活動の差異をNIRSにより検討した研究を見てみよう。NIRSとは、生体組織に対する透過性の高い近赤外光を用いて、組織を流れている血液中のヘモグロビン酸素化状態を外部から安全に調べる装置である。一般に脳の活動している部位は血流が増加すると言われており、NIRSを用いることで大まかにではあるが脳内のどの部分が強く活動しているのかを知ることができる。
この実験で対象となったのは6~7か月児であり、リアル条件とテレビ条件に分けられた。乳児には、女性が仕掛けのついた玩具を操作している事象を、リアルあるいはテレビで呈示された。その結果、両刺激観察時における頭頂付近の脳活動に有意な差が見いだされ、乳児が現実の世界とテレビの世界に対して区別して反応していることが示された[2]。
次に、テレビ映像視聴中の乳児の脳活動をEEGにより検討した研究を紹介する。EEGとは、脳神経の電気的活動を頭皮上のセンサによって計測する手法である。被験児は4~6か月児で、あらかじめリアル条件とテレビ条件に分けられていた。乳児に呈示したのは、1つの玩具を横に並んだ2つのカップのどちらかで隠した後、隠していない方のカップを持ち上げ玩具がな
いことを示す可能事象と、隠した方のカップを持ち上げ玩具がないことを示す不可能事象であった(図1参照)。 |
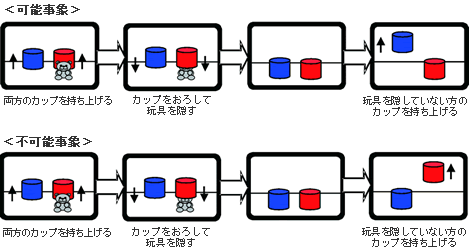
図1. 刺激事象の模式図 |
これまでの様々な研究から、リアルで呈示した場合には可能事象と不可能事象に対する乳児の行動反応が異なることが示されている。本実験を行うことにより、テレビで呈示した場合とリアルで呈示した場合で各事象に対する乳児の行動反応や脳活動が異なるかどうかを明らかにできる。実験中の様子を図2に示す。
|

図2. EEGの実験の様子 |
コップが上がり玩具がないことが示された後の6秒間のEEG周波数特性を解析した結果、リアル条件、テレビ条件ともに、特に右半球の後頭葉から側頭葉にかけて分布するガンマ帯域(25-35Hz)の強度が、可能事象観察時と不可能事象観察時では異なることが示された。また、テレビ条件の方が不可能事象観察時と可能事象観察時の差異が大きい傾向があった。
EEGのガンマ帯域は、脳内の情報統合に関係するとされており、本実験で得られたパターンは、予期した事象と観測した事象の食い違いを反映した神経活動であると解釈される。実験前の予想としては、テレビ条件よりもリアル条件で反応の違いが大きくなると考えていたが、今回の実験では、この予想に反してテレビ条件で不可能事象と可能事象の差が大きく現れた。現時点では、この結果に対する明確な理由を述べることはできず、引き続き被験児を増やして結果の信頼性を高める予定である。
このように、NIRSとEEGともに、リアル条件とテレビ条件で脳活動に差異が見出されている。NIRSは脳活動の部位の特定に、EEGは脳活動の時間的な変化の計測に特に優れており、今後は、こうした計測手法の特徴を活かし、乳児のテレビ認知の特性を検討していきたい。
|
| ■今後の展望 |
| メディアの発達への影響について議論する上でもっとも重要な点は、可能な限り客観的データに基づいて、先入観を排除することである。脳神経レベルの活動を指標にアプローチすることの利点は、①行動に表れにくい認知処理を詳細に検討可能なこと、②成人の脳機能計測とある程度連続性を保ちつつ議論を展開できること、の2点にまとめることができる[3]。乳幼児など若年齢の被験者を対象とした行動実験アプローチでは、注視時間など解釈に曖昧性が残存する測度を用いたり、言語教示が困難であったりする場合が多い。EEG/ERPやNIRSなど乳幼児にも成人にも適用可能な脳活動計測手法は、こうした問題を解決し、かつ、上記2点のメリットを有するため、メディアの発達的影響だけでなく、認知機能全般のメカニズムを探究する上でも今後が期待される。 |




