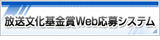 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます) |
| 放送文化基金賞の応募方法がWeb申請に変わりました。 |
|
|
| 守分 寿男(演出家・映像プロデューサー) |
| テレビ番組の優れた演出による放送文化への長年にわたる貢献 |
| テレビとはなにか、まだあまり知られていなかった1957年(昭和32年)以来、半世紀余り、その問いを問いつづけながら番組を創ってきました。番組のひとつひとつが、その時点での精一杯の答えだったと思えます。津軽海峡をはさんで、北海道の風土は亜寒帯にと変ります。その風土のなかで、半年近い氷雪の世界で生きる人たちの姿をまるごと捉えたい。それが出来たかどうか。今回の賞がそんな努力へのご褒美とも思え、ただ感謝です。 |
| 長谷川 勝彦(フリーアナウンサー)
|
| NHKスペシャルをはじめとするドキュメンタリー番組のナレーション |
| この賞を受賞したドキュメンタリーで、私がナレーションさせて頂いたのは、NHKスペシャル『SARSと闘った男』と『硫黄島玉砕戦』、他に番組賞などが4本あります。ナレーターとして番組作りに参加させてもらい、その番組が評価されてきたわけですから、個人としての表彰は結構ですといいたいところですが、そうは言いません。放送文化におけるナレーションの役割がもっと注目され、論じられるべきだと思っているからです。ナレーターの一人として名誉に思うと同時に、後に続く人たちの刺激になればと願います。 |
| 関 芳樹(IBC岩手放送ラジオセンター専任部長)
|
| 地域に根ざした優れたラジオ・テレビドキュメンタリー番組の制作 |
「いわて 風っこェェ、水っこェェ、人っこェェ・・・」
私の番組制作の根底に在るものはこれです。
自然や、食べ物、人情など、岩手には沢山の宝物があります。
“地方の時代”と叫ばれながら、経済優先の今“地方切り捨て”が進行し、交通、医療、教育など様々な分野で地方が新たな問題を抱えてきています。
私たち地方局の役割は、“地方の元気”を応援していくことだとも考えます。これからも岩手の素晴しい風、水、人、そして宝物と出逢えるよう制作者としての腕と感性を磨き、“地方の味”がする番組を作り続けたいと思います。
|
| 塩田 純(NHKチーフ・プロデューサー) |
| テレビドキュメンタリー番組のプロデューサーとしてのめざましい活躍 |
教育テレビのETV特集を中心にドキュメンタリーを作り続けてきました。NHK局内では光があたらない地味な番組を評価していただけたことが、何より嬉しかったです。番組に取り組んだNHKをはじめ多くのプロダクションの皆さんに感謝します。
近年は、アジアを舞台に戦争の記憶を撮ることに力を入れてきました。次々と証言者が亡くなられていく今、「急がなければ」という思いがあります。来年は韓国併合100年を迎えます。日本と朝鮮半島の関係を新たな資料と証言で見つめていこうと考えています。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いします。
|
|




