 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます) |
| 助成の申請、各種書類の提出はこちらから。 |
|
|
昭和49年(1974年)度から現在まで当基金が実施した助成の対象全てを検索できます。

 |
|
|

放送文化基金の平成22年度の助成金贈呈式は、3月4日、東京・平河町の海運クラブで開催されました。毎年この時期に開催される贈呈式は、助成対象の研究者や事業者同士、また放送文化基金とをつなぐ貴重な交流の場となっています。この日も関係者95人が参加し、分野を越えたさまざまなコミュニケーションの輪が広がりました。
贈呈式は、研究報告、目録贈呈、懇親会の3部構成で行いました。
|
|
|
|
<研究報告会>
|
| 基金はこれまで、毎年秋に、助成した研究プロジェクトの研究報告会を別途開催してきました。今回初めての試みとして、贈呈式での研究報告の機会を設けることになり、平成20年度の助成を受けたプロジェクトの中から代表して、文教大学准教授の前嶋和弘さんが、「アメリカの放送メディアにおける政治情報提供の変化と台頭するメディア監視団体」について報告しました。アメリカでかつては政治に対して「客観的な鏡」の役割を担っていたメディアが、イデオロギーを基にする情報提供者そのものに変容していった結果、メディア監視団体という新たなグループが台頭してきたという興味深い最新の動きが報告されました。前嶋さんは22年度助成対象者でもあり、アメリカの政治とメディアの関係についてさらに研究を進められるということで、今回新たに助成を受けた方々にとっても大きな励みとなる研究報告でした。 |
| ▽人文社会・文化 研究報告 |
アメリカの放送メディアにおける政治情報提供の変化と台頭するメディア監視団体
前嶋 和弘(文教大学准教授)
|


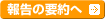 |
<贈呈式>
つぎに行われた目録贈呈では、まず、末松安晴理事が「メディア状況が激変する中で、放送文化を支える皆さんそれぞれの取り組みに期待するところが大きい」と挨拶。引き続き、審査概況について「技術開発」の羽鳥光俊審査委員長と「人文社会・文化」の藤井宏昭審査委員から報告がありました。この後、助成の対象に選定された1人1人に末松理事から目録が贈呈され、代表者として情報フォトニクス研究グループ代表の的場修さんと、牛山純一研究委員会代表の藤本美津子さんが挨拶し、今後の研究への取りくみを語りました。
|
|
| 22年度の助成には、142件の申し込みがあり、審査の結果、「技術開発」で14件、「人文社会・文化」で36件、合計50件(うち海外4件)、5500万円が採択されました。採択された研究や事業は、向こう1年の間に実施されることになっています。 |
|
|
▼今年度採択されたの研究・事業の特徴
●技術開発
申請件数46件の中から、助成対象14件 2,200万円を決定した。採択率は30.4%高精細、大画面、3D時代のテレビを対象に、それらが人間の生理や心理にどのような影響を与えるのか明らかにしようという心理学、脳科学など幅広い分野からの研究が多く採択された。
デバイス・材料の基礎的な分野の申請がこれまでと同様少ないなかで「色情報と距離情報を同時に記録するMEMS三次元カメラ」は、3Dテレビの普及が始まり、より臨場感の高い立体映像を提供するために、手のひら大の三次元カメラを試作するもので、若手研究者による新規性の高い研究として評価された。
このほか、盲ろうという重複したハンディを持った人にとって緊急情報などの放送伝達を可能とする支援ツールの開発、高齢者の色覚特性をデータベース化し、放送への応用をめざすもの、就学児前の幼児を対象に、3D映像となった場合に2D映像時との認識の違いの有無を調査研究するものなどが採択された。
|
●人文社会・文化
申請件数96件(海外8件を含む)の中から、助成対象36件(海外4件を含む)3,300万円を決定した。採択率は37.5%デジタル化、放送史、番組の内容分析など従来型の研究の申請が少なくなったが、今まで以上に放送の存立意義を様々な角度から研究していこうという姿勢が広がってきている。その結果、講師、大学院生など若い研究者への少額助成も含めて、数多くの助成を実施することとなった。
このうち、「「テレビ美術」の意味と役割に関する学際的研究」は散逸が懸念されるテレビ美術の基礎資料を、多様な分野の研究者、専門家が、収集・分析、関係者へのヒヤリングを行うもので、成果が期待される。また、「プロパガンダかジャーナリズムか ―中国「国際放送」の研究―」は時宜にかなった研究として評価された。今年の秋に札幌で開かれる「日韓中テレビ制作者フォーラム」は過去に東京や福岡で開催され、11回目を迎え、制作者の交流が続いているもの。海外からの申請については中国やマレーシアで開かれるシンポジウムの開催など、4件の助成を決定した。 |
|




